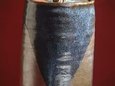郷土情報ネットワーク > 虫明焼
虫明焼
カテゴリ情報
郷土情報ネットワーク > 郷土情報ネットワーク > 11 岡山県立図書館 > 郷土の映像 > 工芸(映像)
| 郷土情報ネットワーク > 郷土情報ネットワーク > 11 岡山県立図書館 > 郷土の映像 > 工芸(映像) |
メタデータ
| タイトル | |
|---|---|
| タイトル | 虫明焼 (ムシアゲヤキ) |
| 郷土情報の種類 | |
| 郷土情報の種類 | 動画 |
| 作成者または作成団体 | |
| 作成者または作成団体 | テレビせとうちクリエイト(制作グループ) (テレビセトウチクリエイトセイサクグループ) |
| 公開者または公開団体 | |
| 公開者または公開団体 | 岡山県立図書館 (オカヤケンリツトショカン) |
| 共同作成者または共同作成団体 | |
| 共同作成者または共同作成団体 | 立石 憲利 (タテイシノリトシ) 邑久町虫明焼作陶会 (オクチョウムシアケヤキサクトウカイ) |
| 郷土情報の概要 | |
| 郷土情報の概要 | 肉厚できめ細かい肌触りとやわらかな曲線。そして、うぐいす色やびわ色など、しっとりとした淡い色調が魅力的な虫明焼。家伝の釉薬や絵付けによる作品は、優雅で気品に満ちています。古くから海上交通の要衝として栄えてきた邑久町虫明地区は作陶に適した土にも恵まれた港町です。虫明焼の詳しい起源は定かではありませんが、現在の形態が確立されたのは江戸時代の中期と言われています。岡山藩主池田家の筆頭家老、伊木家六代目の忠興が、趣味として茶器や花器をお庭窯で焼かせた、京焼系の焼き物が起源とされています。その後、茶人として有名な伊木三猿斎の時代になって、清水焼の作風が伝えられるとともに、独特の釉薬も作り出され、名声を高め伝統を築き上げました。邑久町内には、伊木三猿斎が築いた窯が、今も当時の姿をとどめています。明治に入ると、森葛雄(くずお)香洲(こうしゅう)父子の優れた技法によってこの伝統は受け継がれ、現在は数名の弟子たちが作り続けています。虫明焼の製法は、まず原料の土を乾燥させた後、何回ももみ、土の中に含まれている空気を取り除いて粘りを出します。成型は、ろくろを使ったり、手ひねりで形を整えていきますが、薄作りのため、繊細な作業となります。1度素焼きをした後、絵付けを行い、家伝の釉薬をかけます。この釉薬には、松や栗、わらなどの灰に石の粉を混ぜ合わせたものが使われます。最後に、1300度近い炎で40数時間の本焼きを行い、上絵をつけて、1つ1つ丁寧に仕上げていきます。清水焼の流れをくんだ薄作りのろくろのさえが見事な虫明焼。伝統に加え、作家独特の技法による洗練された造形美や風合いは、岡山県の伝統工芸品にも指定されています。 |
| 場所 | |
| 場所 | 岡山県瀬戸内市邑久町尾張 |
| NDC分類 | |
| NDC分類 | 751:陶磁工芸 |
| 検索キーワード | |
|---|---|
| 検索キーワード | 虫明焼 |
| 対象年齢 | |
| 対象年齢 | 全年齢, 高校生, 中学生, 小学生(高学年), 小学生(低学年以下) |
| 郷土情報の言語 | |
| 郷土情報の言語 | jpn |
| メタデータ作成年月日 | |
| メタデータ作成年月日 | 2004-03-01 |
| メタデータ公開年月日 | |
| メタデータ公開年月日 | 2011-02-27 |
| メタデータ更新年月日 | |
| メタデータ更新年月日 | 2020-02-28 |
| このページのURL | |
|---|---|
| このページのURL | http://digioka.libnet.pref.okayama.jp/detail-jp/id/kyo/M2004090621561437684 |