以前は祇園宮と称していたのを明治2年に改めた
応仁の乱の後の頃、和歌山県熊野神社の神官が、京都八坂神社の分霊(素盞鳴尊)を背負って、現素盞鳴神社に
祀ったという伝説があるそうだ。
時代が下って江戸幕府の観文7年(1667年)岡山藩の藩主池田光政公は備前国内の神社の整理をしたが、この
社は淘汰されなかったばかりでなく、次の藩主綱政公が、正徳2年(1712年)に改めて京都祇園社から素盞鳴尊の
分霊を勧請して、新しく社殿を造営し社領(石高不明)も与えたといわれる。現在の社殿はその時のものであると
考えられる。
綱政公がこの神社を造営した所以については、当時水害・干ばつが相次ぎ疫病が流行ったので、疫病退治の神様と
言われた素盞鳴尊信仰に傾いたという説が有力である。
祭は「おぎおん様」と呼ばれ50~60年前にはあまりに人出が多いので親から行くことを禁じられた家もあったとか。 |
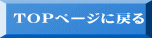
|