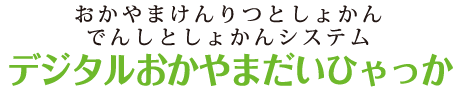きょうどじょうほうネットワーク > 藤井 高尚 《おかやま人物往来》
藤井 高尚 《おかやま人物往来》
カテゴリじょうほう
| きょうどじょうほうネットワーク > 郷土情報ネットワーク > 11 岡山県立図書館 > おかやま人物往来 |
メタデータ
| タイトル | |
|---|---|
| タイトル | 藤井 高尚 《おかやま人物往来》 (フジイ タカナオ オカヤマジンブツオウライ) |
| きょうどじょうほうのしゅるい | |
| きょうどじょうほうのしゅるい | ホームページ |
| さくせいしゃまたはさくせいだんたい | |
| さくせいしゃまたはさくせいだんたい | 岡山県立図書館 (オカヤマケンリツトショカン) |
| こうかいしゃまたはこうかいだんたい | |
| こうかいしゃまたはこうかいだんたい | 岡山県立図書館 (オカヤマケンリツトショカン) |
| きょうどじょうほうのがいよう | |
| きょうどじょうほうのがいよう | 本居宣長門下の高弟として知られる藤井高尚は、江戸時代後期の代表的国学者であり、歌人である。彼は、明和元(一七六四)年、賀陽郡宮内村(現岡山市吉備津)で吉備津宮祠官藤井高久の子として生まれた。 文学的・学問的環境に恵まれた高尚は、少年時代から国学を修め和歌を学んだが、寛政五(一七九三)年、三十歳にして伊勢松阪(現三重県松阪市)に本居宣長を訪ね、その学問に傾倒していった。これによって彼の学者としての活眼が開かれたと言える。高尚自らも中国地方をはじめ、京・大坂・四国などに多くの門人をつくり、その数は二、三百人に及んだという。 彼は、吉備津神社の神官を務めるかたわら平安朝の古典文学研究に大きな業績をあげているほか、文章作法書、音楽、演劇論、和歌、神道など多岐にわたって膨大な著作を残している。 その全著作を一覧することができる資料が『藤井高尚の国学』(昭57・岡山大学附属図書館編)である。本書には全著作が解説付きで紹介され、高尚研究文献目録や年譜も付されている。また、その生涯を通して数多くの歌を詠み続けた、歌人としての高尚を知るには『藤井高尚全歌集』(昭58・工藤進思郎編)があげられる。淡々とした一種独特の世界が広がり、国学者とはまた別の一面をかいま見ることができる。 その他、伝記に『藤井高尚伝』(明43・井上通泰著)がある。本書は、著者が高尚の和歌や著作を収集して著したもので、高尚研究としてまとまった最初のものである。その後、高尚死後百年を記念して『藤井高尚伝』(昭15・吉備津神社編)が編纂された。様々な角度から彼をとらえ、履歴や業績はもちろん人柄や交友関係なども、詳細にまとめられた資料である。 最近の研究には『藤井高尚と松屋派』(昭61・工藤進思郎著)がある。著者がこれまでに発表してきた論文を収めたもので、多くの遺稿や写本類に基づいた研究の成果が著されている。 高尚は天保十一(一八四〇)年八月十五日、七十七歳をもって没した。その生涯は、 国学の研究と門弟の指導のために捧げられたと言っても過言ではない。吉備津神社にはその生涯を顕彰するための頌徳碑と歌碑がある。文政十三(一八三〇)年の建立といわれる歌碑の文字は既に判読できないが、彼の業績は今でも文学史上に刻まれている。 |
| じだい | |
| じだい | 江戸時代(黒船来航前) 1764 ~
1840 |
| ばしょ | |
| ばしょ | 岡山県岡山市吉備津 |
| NDCぶんるい | |
| NDCぶんるい | 289:個人伝記 |
| けんさくキーワード | |
|---|---|
| けんさくキーワード | 217 |
| さんこうじょうほうげんまたはいんようじょうほうげん | |
| さんこうじょうほうげんまたはいんようじょうほうげん | 岡山県総合文化センターニュースNo.377 |
| さんこうじょうほうげんまたはいんようじょうほうげん(URL) | |
| さんこうじょうほうげんまたはいんようじょうほうげん(URL) | 郷谷紀行 |
| たいしょうねんれい | |
| たいしょうねんれい | 全年齢, 高校生, 中学生 |
| きょうどじょうほうのげんご | |
| きょうどじょうほうのげんご | jpn |
| メタデータこうかいねんがっぴ | |
| メタデータこうかいねんがっぴ | 2011-02-27 |
| メタデータこうしんねんがっぴ | |
| メタデータこうしんねんがっぴ | 2020-03-15 |
| このページのURL | |
|---|---|
| このページのURL | http://digioka.libnet.pref.okayama.jp/detail-jp_c/id/kyo/M2004070112162510080 |