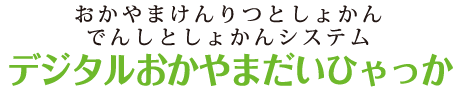きょうどじょうほうネットワーク > 勝山竹細工
勝山竹細工
カテゴリじょうほう
きょうどじょうほうネットワーク > 郷土情報ネットワーク > 11 岡山県立図書館 > 郷土の映像 > 工芸(映像)
| きょうどじょうほうネットワーク > 郷土情報ネットワーク > 11 岡山県立図書館 > 郷土の映像 > 工芸(映像) |
メタデータ
| タイトル | |
|---|---|
| タイトル | 勝山竹細工 (カツヤマタケザイク) |
| きょうどじょうほうのしゅるい | |
| きょうどじょうほうのしゅるい | どうが |
| さくせいしゃまたはさくせいだんたい | |
| さくせいしゃまたはさくせいだんたい | テレビせとうちクリエイト(制作グループ) (テレビセトウチクリエイトセイサクグループ) |
| こうかいしゃまたはこうかいだんたい | |
| こうかいしゃまたはこうかいだんたい | 岡山県立図書館 (オカヤケンリツトショカン) |
| きょうどうさくせいしゃまたはきょうどうさくせいだんたい | |
| きょうどうさくせいしゃまたはきょうどうさくせいだんたい | 立石 憲利 (タテイシノリトシ) 川元 冨士雄 (カワモトフジオ) |
| きょうどじょうほうのがいよう | |
| きょうどじょうほうのがいよう | 農家の庭先などでよく見かける「そうき」と呼ばれる実用的な竹細工。米などの穀物や野菜を運ぶなど、その昔から重宝されてきました。プラスチック製品ができるまでは、「そうき」と呼ばれるザル、カゴ、箕など竹製品は大切な日用品で各地に産地がありました。その素朴な民具を匠たちの技で工芸品の域にまで高めたのが「勝山竹細工」。江戸時代末期に産地としての形が成り立っていたと伝えられています。現在では「盛り籠」や「パン籠」、茶室によく合う「花器」など、時代に合ったさまざまな種類が作られています。「勝山竹細工」は地元にある真竹(まだけ)と葛籠(つづら)を使って作られます。材料となる竹の切り出しは時期が大切です。毎年、11月から12月にかけて、3年から5年たったものを竹やぶから切り出し、風通しの良い日陰で保存しておきます。竹は汚れをきれいに落としてから、竹割り作業に入ります。専用の鉈(なた)で、まず2つに割り、その竹を今度はもっと細いものにして、骨や仕上げの縁の部分を作り、さらに細い「ひご」も作ります。そして、竹を編む作業に入ります。まず枠を決め、そこに「ひご」を縦にかけて骨を横に通していきます。そして今度は骨に「ひご」を通します。ここで竹の節をそろえたり、あるいは微妙にずらすなどして、模様を創り出します。まさに匠の技と言えるでしょう。次第に編み上がっていき、全体の形が整ってきます。縁には、山に自生している、つづらふじのつるを使います。縁につづらふじを使用したものが伝統工芸品として指定されています。あらい上げのざるでも「ひご」の面取りをし、表面を滑らかに仕上げているため米粒のような小さなものでも引っかかりません。竹の表面の青い部分は使い続けるうちに飴色になり艶も出て、新しい製品とは趣の違ったものになる「勝山竹細工」。耐久性と使い勝手の良さに加え、その芸術性が広く人々の心を捉えています。 |
| ばしょ | |
| ばしょ | 岡山県真庭市勝山 |
| NDCぶんるい | |
| NDCぶんるい | 754:木竹工芸 |
| けんさくキーワード | |
|---|---|
| けんさくキーワード | 勝山竹細工 |
| さんこうじょうほうげんまたはいんようじょうほうげん | |
| さんこうじょうほうげんまたはいんようじょうほうげん | TSCナイス5 2002-10-21 |
| たいしょうねんれい | |
| たいしょうねんれい | 全年齢, 高校生, 中学生, 小学生(高学年), 小学生(低学年以下) |
| きょうどじょうほうのげんご | |
| きょうどじょうほうのげんご | jpn |
| メタデータさくせいねんがっぴ | |
| メタデータさくせいねんがっぴ | 2004-03-01 |
| メタデータこうかいねんがっぴ | |
| メタデータこうかいねんがっぴ | 2011-02-27 |
| メタデータこうしんねんがっぴ | |
| メタデータこうしんねんがっぴ | 2020-02-28 |
| このページのURL | |
|---|---|
| このページのURL | http://digioka.libnet.pref.okayama.jp/detail-jp_c/id/kyo/M2004090621562037694 |