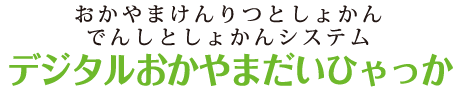きょうどじょうほうネットワーク > 走り神輿(笠岡市真鍋島)
走り神輿(笠岡市真鍋島)
カテゴリじょうほう
きょうどじょうほうネットワーク > 郷土情報ネットワーク > 11 岡山県立図書館 > 郷土の映像 > 郷土芸能(映像)
| きょうどじょうほうネットワーク > 郷土情報ネットワーク > 11 岡山県立図書館 > 郷土の映像 > 郷土芸能(映像) |
メタデータ
| タイトル | |
|---|---|
| タイトル | 走り神輿(笠岡市真鍋島) (ハシリミコシカサオカシマナベジマ) |
| きょうどじょうほうのしゅるい | |
| きょうどじょうほうのしゅるい | どうが |
| さくせいしゃまたはさくせいだんたい | |
| さくせいしゃまたはさくせいだんたい | テレビせとうちクリエイト(制作グループ) (テレビセトウチクリエイトセイサクグループ) |
| こうかいしゃまたはこうかいだんたい | |
| こうかいしゃまたはこうかいだんたい | 岡山県立図書館 (オカヤケンリツトショカン) |
| きょうどうさくせいしゃまたはきょうどうさくせいだんたい | |
| きょうどうさくせいしゃまたはきょうどうさくせいだんたい | 岡山民俗学会 (オカヤマミンゾクガッカイ) |
| きょうどじょうほうのがいよう | |
| きょうどじょうほうのがいよう | 笠岡諸島の真鍋島の秋祭りの見ものは「走り神輿(みこし)」です。300年間続くと言われる漁師達の勇壮な祭りです。笠岡市から南へ約20KMの真鍋島は古い漁村形態を残す島として岡山県のふるさと村に指定されています。真鍋島の鎮守・八幡神社の祭りは旧暦の8月14・15日でしたが、現在はそれに近い土、日で勇壮な走り神輿が行われます。輿守(こしもり)達は金曜日から精進し、宵宮では神輿を担いで“かけならし”という“走り”を繰り返します。約240kgある神輿の、どこを誰が担ぐのか?8人の輿守達が体で神輿を感じる時です。本祭りを御神事といい、朝の4時に輿守達は海で身を清めます。“ずぼごり”と呼ばれます。八幡神社の境内では清めの棒術、そして獅子が舞われます。神輿は3体、島の3つの集落から出ます。神輿は本殿から鳥居までを全速力で走り抜け、大漁旗で飾りつけられたお召(おめし)舟に乗り込みます。昔は船が小さく、2艘の船を丸太でくくりつけていたことから、今も船を綱で結んで一つにしています。満潮を見はかり、御旅所まで海上の渡御が始まります。このとき船上では祝い歌の「舟歌」が唄われます。神社を出て約1時間後、神輿を載せた船が次々に本浦の港に着きます。張りつめた中、輿守達は警護役の合図を待ちます。先頭を切る権限を持つのが先神輿です。つづいて後の神輿がぶつかり合うように走り出します。しきり直しはなくお互いの牽制が続きます。狭い道筋で神輿が並ぶと輿守同士の駆け引きが行われます。気を抜くと前の神輿が一気に走り出し、次の神輿は遅れをとることになります。その緊張感が観客にも伝わり、一体となって、興奮が高まっていきます。島に熱気と興奮を残したまま、一夜が明け「おかえり」の日。夕刻の干潮を待って神輿は八幡神社に帰ります。途中浜辺で最後の「走り」が行われます。祭りの名残を惜しむように「伊勢音頭」が響き渡ります。ろうろうと海を渡るのどかさと、神輿を競い合う男達の激しさが、心に残る祭りです。 |
| ばしょ | |
| ばしょ | 岡山県笠岡市真鍋島 |
| NDCぶんるい | |
| NDCぶんるい | 386:年中行事.祭礼 |
| けんさくキーワード | |
|---|---|
| けんさくキーワード | 走り神輿 |
| たいしょうねんれい | |
| たいしょうねんれい | 全年齢, 高校生, 中学生, 小学生(高学年), 小学生(低学年以下) |
| きょうどじょうほうのげんご | |
| きょうどじょうほうのげんご | jpn |
| メタデータさくせいねんがっぴ | |
| メタデータさくせいねんがっぴ | 2004-03-20 |
| メタデータこうかいねんがっぴ | |
| メタデータこうかいねんがっぴ | 2011-02-27 |
| メタデータこうしんねんがっぴ | |
| メタデータこうしんねんがっぴ | 2020-02-28 |
| このページのURL | |
|---|---|
| このページのURL | http://digioka.libnet.pref.okayama.jp/detail-jp_c/id/kyo/M2004090709512637722 |