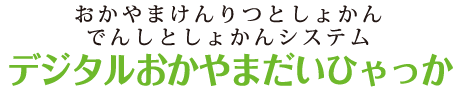明治4年(1871)の戸籍法に基づいて、旧岡山県は44の大区を設定した。各大区の中にいくつかの小区があった。第21区には1番から3番までの小区があり、3番小区の中に塩田村(現和気郡佐伯町)が入っていた。この図は明治6年(1873)6月に作成されたものであり、大区長は戸長、小区長は副戸長と呼ばれていたことが読みとれる。明治5年(1872)の壬申地券の発行にともなう地目(ちもく)、地番の確定を主目的としていたと考えられる。明治5年10月30日に大蔵省から「地券渡方規則」(*1)の増補改訂版が布達されている。この史料には「(前略)検地帳名寄帳小拾帳等ニ突合サル共現地ノ景况ニ隨ヒ總テ地引繪圖可差出旨説示可致事」(*2)という条文があり、地引絵図作成を明治政府が指示していることがわかる。明治6年7月の地租改正条例公布の前提となったことはいうまでもないだろう。本館所蔵の『小田県管轄第十六区下道郡一区服部村絵図』(KM391/5)と比較してみると地目の色分けがほぼ共通していることがわかる。したがって明治政府が作成方法について各府県に指示を出していたと考えられる。註(*1)明治5年2月に「地券渡方規則」の第1条から第14条までが、9月に第15条から第40条までが布達された。第15条から第40条までについては10月に増補改正版が出されている。註(*2)「地券渡方規則」の第23条である。
つづきをとじる