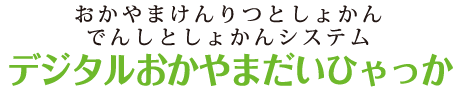きょうどじょうほうネットワーク > 岡山県史 第5巻,中世 2
岡山県史 第5巻,中世 2
カテゴリじょうほう
| きょうどじょうほうネットワーク > 目次情報 > 郷土資料目次情報 |
メタデータ
| タイトル | |
|---|---|
| タイトル | 岡山県史 第5巻,中世 2 |
| きょうどじょうほうのしゅるい | |
| きょうどじょうほうのしゅるい | もじ |
| さくせいしゃまたはさくせいだんたい | |
| さくせいしゃまたはさくせいだんたい | 岡山県史編纂委員会/編纂 |
| こうかいしゃまたはこうかいだんたい | |
| こうかいしゃまたはこうかいだんたい | 岡山県 |
| きょうどじょうほうのがいよう | |
| きょうどじょうほうのがいよう | 守護の領域支配と国人 守護赤松氏一門の発展と嘉吉の乱 (赤松氏とその一門 守護大名赤松義則 p.2 赤松氏とその一門 赤松庶流家の台頭 p.2 赤松氏とその一門 赤松満祐と赤松持貞 p.2 将軍義教と赤松氏 義教の将軍襲職と赤松満祐 p.15 将軍義教と赤松氏 義教と赤松庶流家 p.15 将軍義教と赤松氏 義教の強権政治 p.15 嘉吉の乱 将軍弑逆 p.24 嘉吉の乱 井原御所足利義尊 p.24 嘉吉の乱 備作の情勢と守護赤松氏の没落 p.24) 守護の領域支配と国人 嘉吉の乱後の備作地方 (山名と赤松(二) 山名氏の備前支配 p.36 山名と赤松(二) 山名氏の美作支配 p.36 山名と赤松(二) 赤松満政と山名氏 p.36 山名と赤松(二) 赤松則尚と山名氏 p.36 山名と赤松(二) 禁闕の変 p.36 赤松氏の再興 赤松遺臣と神璽奉還 p.45 赤松氏の再興 赤松政則の家督 p.45 赤松氏の再興 赤松氏の宿老浦上則宗 p.45 赤松氏の再興 備前国新田荘をめぐって p.45 備中守護細川氏 細川満之 p.62 備中守護細川氏 細川頼重 p.62 備中守護細川氏 細川氏久 p.62) つづきをみる 守護の領域支配と国人 応仁の乱と国人領主の成長 (応仁の乱 大乱の勃発と赤松政則 p.72 応仁の乱 赤松氏の播・作・備三国の回復 p.72 応仁の乱 国人領主の動向 p.72 応仁の乱 浦上則宗と備前国 p.72 山名と赤松(三) 山名持豊の死 p.83 山名と赤松(三) 細川勝元の死 p.83 山名と赤松(三) 大乱の終息 p.83 山名と赤松(三) 山名政豊の美作浸入 p.83 山名と赤松(三) 備前国福岡合戦 p.83 国人領主勢力の成長 山名氏の備作撤退 p.96 国人領主勢力の成長 赤松政則の死 p.96 国人領主勢力の成長 政則没後の領国 p.96) 群雄と下克上の世相 守護代勢力の台頭 (備前浦上氏と松田氏 守護と守護代 p.108 備前浦上氏と松田氏 備前と赤松氏 p.108 備前浦上氏と松田氏 備前守護代浦上行景と三石城 p.108 備前浦上氏と松田氏 赤松政則時代の備前守護代 p.108 備前浦上氏と松田氏 備前松田氏の系譜 p.108 備前浦上氏と松田氏 村宗登場以前 則国・則景・宗助 p.108 備前浦上氏と松田氏 竜ノ口合戦 p.108 備前浦上氏と松田氏 『備前軍記』の信憑性 p.108 備前浦上氏と松田氏 紀太郎祐宗のこと p.108 浦上村宗の野望 「魔法」にこった細川政元 p.124 浦上村宗の野望 政元の暗殺 p.124 浦上村宗の野望 澄之の四十日天下 p.124 浦上村宗の野望 澄元・高国の対立 p.124 浦上村宗の野望 高国政権の成立 p.124 浦上村宗の野望 赤松義村の立場 p.124 浦上村宗の野望 洞松院夫人の仲介 p.124 浦上村宗の野望 浦上村宗と主君赤松義村の対立 p.124 浦上村宗の野望 村宗の弟宗久、兄に反して敗走す p.124 浦上村宗の野望 澄元の反攻、之長の自刃 p.124 浦上村宗の野望 備前の情況 p.124 浦上村宗の野望 播磨の情況 p.124 浦上村宗の野望 村宗、播磨の覇権を握る p.124 浦上村宗の野望 将軍義晴の襲職 p.124 浦上村宗の野望 村宗、義村を暗殺 p.124 浦上村宗の挫折 内輪取合合戦 p.151 浦上村宗の挫折 書写山の決戦 p.151 浦上村宗の挫折 浦上村宗の上洛 p.151 浦上村宗の挫折 高国陣営の内紛 p.151 浦上村宗の挫折 三好元長の堺進出 p.151 浦上村宗の挫折 「堺幕府論」について p.151 浦上村宗の挫折 浦上村宗の動きと高国の流寓 p.151 浦上村宗の挫折 村宗、柳本賢治を誅殺す p.151 浦上村宗の挫折 村宗、高国を擁して上洛を待つ p.151 浦上村宗の挫折 大物崩れ、村宗戦死 p.151 美作・備中の守護代 美作の武士勢力の大要 p.172 美作・備中の守護代 美作守護代 p.172 美作・備中の守護代 備中守護の変遷 p.172 美作・備中の守護代 備中の国人たち p.172) 群雄と下克上の世相 群雄の争覇 (村宗没後の状況 浦上近江守国秀 p.178 村宗没後の状況 赤松政村の復権 p.178 村宗没後の状況 三好元長、堺顕本寺に死す p.178 村宗没後の状況 宇喜多氏の出自 p.178 村宗没後の状況 島村豊後入道貫阿弥 p.178 尼子氏の美作進出 尼子氏の系譜 p.188 尼子氏の美作進出 尼子氏の美作進出 p.188 尼子氏の美作進出 尼子氏、美作・備中を略定 p.188 尼子氏の美作進出 備中連島の海賊三宅和泉守国秀 p.188 尼子氏の美作進出 吉備津神社の梵鐘 p.188 尼子氏の美作進出 尼子晴久、備前・美作・備中など六カ国守護 p.188 尼子氏の美作進出 畿内の情勢 p.188 尼子氏の美作進出 尼子・大内・毛利の角逐 p.188) 群雄と下克上の世相 宇喜多直家の活躍 (宇喜多直家の台頭 直家の出仕 p.206 宇喜多直家の台頭 浦上政宗のこと p.206 宇喜多直家の台頭 政宗・宗景不和の原因 p.206 宇喜多直家の台頭 宇喜多興家の復権 p.206 宇喜多直家の台頭 浦上政宗父子の横死 p.206 宇喜多直家の台頭 浦上誠宗のこと p.206 宇喜多直家の台頭 浦上宗景の自立 p.206 宇喜多直家の台頭 宇喜多直家、乙子城主となる p.206 宇喜多直家の台頭 直家、沼城を奪う p.206 宇喜多直家の台頭 ■所元常を誅殺、竜ノ口城を奪う p.206 備中三村氏との死闘 庄氏と石川氏 p.220 備中三村氏との死闘 成羽城主三村氏の台頭 p.220 備中三村氏との死闘 三村家親の活躍 p.220 備中三村氏との死闘 宇喜多直家、三村家親を興禅寺で暗殺 p.220 備中三村氏との死闘 家親の遺臣、沼城を攻めて敗死す p.220 備中三村氏との死闘 宇喜多・三村両氏の激突、明禅寺合戦 p.220 備中三村氏との死闘 三村家親の苦難 p.220 備中三村氏との死闘 三村家親死と常山女軍 p.220 戦国大名への途 浦上宗景の一部としての宇喜多直家 p.236 戦国大名への途 天神山城に移る p.236 戦国大名への途 宗景、上洛して織田信長に謁す p.236 戦国大名への途 直家、岡山城に移る p.236 戦国大名への途 直家、浦上宗景と断ち毛利氏と結ぶ p.236 戦国大名への途 直家、天神山城を陥れる p.236 戦国大名への途 直家、播磨に進出する p.236 戦国大名への途 直家、毛利氏と断つ p.236 戦国大名への途 八浜合戦、直家の死 p.236) 中世後期荘園の世界 荘園支配の変質 (在地勢力の台頭 荘園と地頭 p.252 在地勢力の台頭 福岡荘と頓宮氏 p.252 在地勢力の台頭 武士の狼藉 p.252 建武政権と荘園 新見荘と東寺百合文書 p.256 建武政権と荘園 東寺領新見荘の成立 p.256 建武政権と荘園 建武政権と新見荘 p.256 建武政権と荘園 建武政権と地頭職 p.256 領家職相論 法印信尊と新見九郎貞直 p.262 領家職相論 領家職の伝領 p.262 領家職相論 領家職ゆれる p.262 領家職相論 法印信尊と東寺の和解 p.262 領家職相論 小槻氏と東寺の相論 p.262 領家職相論 小槻氏と東寺の和解 p.262 押妨される荘園 多治部屋形跡 p.272 押妨される荘園 多治部備中守師景 p.272 押妨される荘園 美作での濫妨 p.272 押妨される荘園 備前での濫妨 p.272 押妨される荘園 金岡荘の百姓言上状 p.272 押妨される荘園 備中での濫妨 p.272) 中世後期荘園の世界 守護勢力の荘園支配 (明徳の乱と荘園 新見荘と明徳の乱 p.283 明徳の乱と荘園 明徳二年間事 p.283 明徳の乱と荘園 最勝光院方評定引付 p.283 明徳の乱と荘園 新見道存の別名請 p.283 明徳の乱と荘園 正体なき新見荘 p.283 守護勢力の代官請 新見清直の代官請 p.293 守護勢力の代官請 山伏岩奈須宣深の代官請 p.293 守護勢力の代官請 垪和為清の代官請 p.293 守護勢力の代官請 安富宝城の代官請 p.293 守護勢力の代官請 安富智安の代官請 p.293 寄合する農民 新見荘の三職 p.313 寄合する農民 直務支配の実現 p.313 寄合する農民 上使の派遣 p.313 寄合する農民 祐成・祐深注進状 p.313 直務支配の末路 田所金子衡氏 p.328 直務支配の末路 代官祐清の下向 p.328 直務支配の末路 不思議なる在所 p.328 直務支配の末路 代官祐清の殺害 p.328 直務支配の末路 地頭政所の再建 p.328) 中世後期荘園の世界 荘園の解体と土一揆 (応仁の乱と新見荘 譲位段銭 p.349 応仁の乱と新見荘 備中の土一揆 p.349 応仁の乱と新見荘 新見荘の土一揆 p.349 応仁の乱と新見荘 土一揆の終焉 p.349 国人領主の成長 国人領主金子衡氏 p.357 国人領主の成長 国人領主多治部氏 p.357 国人領主の成長 国人領主新見国経 p.357 国人領主の成長 新見荘の終焉 p.357 備中国上原郷 上原郷の所在 p.364 備中国上原郷 郷名を名乗る荘園 p.364 備中国上原郷 東福寺領上原郷の成立 p.364 備中国上原郷 南北朝内乱期の上原郷 p.364 備中国上原郷 荘官と名主 p.364 備中国上原郷 上原郷の農民生活 p.364 備中国上原郷 荘園の一揆 p.364 備中国上原郷 その後の上原郷 p.364 諸荘の動向 山科家領 p.401 諸荘の動向 万里小路家領 p.401 諸荘の動向 『蔭凉軒日録』に見える荘園 p.401) 中世後期荘園の世界 荘園の商業と交通 (荘園の商業 市庭の成立 p.409 荘園の商業 西大寺の市庭 p.409 荘園の商業 福岡の市庭 p.409 荘園の商業 新見荘の市庭 p.409 荘園の商業 市庭の賑い p.409 荘園の商業 割賦取引 p.409 荘園の商業 備前刀 p.409 中世の海上交通 瀬戸内の海 p.431 中世の海上交通 入船帳の世界 p.431 中世の海上交通 地域の商人たち p.431 備前焼 須恵器の貢納国 p.440 備前焼 初期備前焼 p.440 備前焼 山を登った窯 p.440 備前焼 グイビガ谷窯 p.440 備前焼 若代出土壷 p.440 備前焼 福岡の市 p.440 備前焼 再び山麓へ p.440 備前焼 不老山トンネルと水ノ子岩 p.440 備前焼 大甕と擂鉢 p.440 備前焼 現代備前と桃山 p.440 備前焼 葉茶壷 p.440 備前焼 建水と水指 p.440) 宗教と法の中世的展開 密教と阿弥陀信仰 (報恩大師信仰の成立 神仙の世界 p.464 報恩大師信仰の成立 報恩の伝承 p.464 報恩大師信仰の成立 金山寺と報恩 p.464 報恩大師信仰の成立 美髯四八カ寺 p.464 浄土信仰と別所 極楽往生 p.471 浄土信仰と別所 新山別所 p.471 浄土信仰と別所 滝山別所 p.471 浄土信仰と別所 有木別所 p.471 浄土信仰と別所 埋経の風習 p.471 浄土信仰と別所 時宗聖の来訪 p.471 俊乗房重源の活躍 重源の出自と出家 p.477 俊乗房重源の活躍 重源と栄西と法然 p.477 俊乗房重源の活躍 勧進造営と吉備地方 p.477 俊乗房重源の活躍 備前での活動 p.477 俊乗房重源の活躍 備中での活動 p.477) 宗教と法の中世的展開 禅宗の弘まり (栄西と臨済禅 栄西の出自と出家 p.488 栄西と臨済禅 栄西の入宋と修行 p.488 栄西と臨済禅 臨済禅の伝来 p.488 栄西と臨済禅 宋風喫茶法の移入 p.488 臨済禅の備作地方伝播 円爾と東福寺派の進出 p.501 臨済禅の備作地方伝播 備中井山宝福寺 p.501 臨済禅の備作地方伝播 東福寺・南禅寺の初期寺領 p.501 臨済禅の備作地方伝播 寂室元光 p.501 五山禅林の発展 五山・十刹・諸山の制 p.512 五山禅林の発展 備作地方の安国寺 p.512 五山禅林の発展 臨済宗諸寺院の所領 p.512 曹洞禅の普及 曹洞禅の伝来と峨山派の発展 p.523 曹洞禅の普及 曹洞禅の備作地方進出 p.523) 宗教と法の中世的展開 法華宗の伝播と発展 (日蓮と立正安国 備前法華のおこり p.530 日蓮と立正安国 日蓮の出自 p.530 日蓮と立正安国 鎌倉の日蓮 p.530 日蓮と立正安国 佐渡の日蓮 p.530 日蓮と立正安国 身延の日蓮 p.530 日蓮と立正安国 国主諌暁 p.530 日蓮と立正安国 釈尊御領 p.530 日蓮と立正安国 日蓮の道理 p.530 日蓮と立正安国 折伏の基盤 p.530 日蓮と立正安国 念仏・禅の排斥 p.530 日蓮と立正安国 無戒の宣言 p.530 日蓮と立正安国 堂寂光土 p.530 日蓮と立正安国 平等の救済 p.530 日蓮と立正安国 専修唱題 p.530 法華教団の西進 三黜三御赦の時代 p.552 法華教団の西進 妙顕寺 p.552 法華教団の西進 日像と富商 p.552 法華教団の西進 大覚の西国布教 p.552 法華教団の西進 西国門徒と妙顕寺 p.552 法華教団の西進 四海唱導 p.552 法華教団の西進 日尊・日静の上洛 p.552 法華教団の西進 日陣・日什の伝道 p.552 法華教団の西進 四条門流の分立 p.552 法華教団の西進 神天上の法理 p.552 法華教団の西進 神祇の拝・不拝 p.552 法華教団の西進 番神と鎮守 p.552 西国法華教団の繁栄 本能寺の開創 p.573 西国法華教団の繁栄 日隆の地方伝道 p.573 西国法華教団の繁栄 種子島と本能寺 p.573 西国法華教団の繁栄 なべかむり日親 p.573 西国法華教団の繁栄 無双の行者 p.573 西国法華教団の繁栄 専持法華の主張 p.573 西国法華教団の繁栄 室町前期の宗内情勢 p.573 西国法華教団の繁栄 不受不施の制戒 p.573 西国法華教団の繁栄 折伏伝道への傾斜 p.573 西国法華教団の繁栄 寛正の盟約 p.573 西国法華教団の繁栄 応仁の乱と洛内法華宗の繁栄 p.573 西国法華教団の繁栄 地方への教線伸張 p.573) 宗教と法の中世的展開 備作地域の法と規範 (中世紀における法と裁判の一態様 備前国可真郷本免田所職相論 地域と法・規範 p.592 中世紀における法と裁判の一態様 備前国可真郷本免田所職相論 備前国可真郷本免田所職相論 p.592 中世紀における法と裁判の一態様 備前国可真郷本免田所職相論 明法勘文 p.592 中世紀における法と裁判の一態様 備前国可真郷本免田所職相論 相論の裁決 p.592 備前国金山寺領の竹木伐採の禁 禁制と置文・起請文 禁制 p.598 備前国金山寺領の竹木伐採の禁 禁制と置文・起請文 竹木伐採の禁 p.598 備前国金山寺領の竹木伐採の禁 禁制と置文・起請文 「三野郡地主」三野佐信 p.598 備前国金山寺領の竹木伐採の禁 禁制と置文・起請文 置文と起請文 p.598 美作国塩湯郷地頭職後藤良貞の掟書と置文 美作国塩湯郷地頭職掟書 p.610 美作国塩湯郷地頭職後藤良貞の掟書と置文 掟書の法的性格 p.610 美作国塩湯郷地頭職後藤良貞の掟書と置文 後藤良貞置文 p.610 備作地域の村と民衆の規範意識 中世後期の村と規範意識 p.623 備作地域の村と民衆の規範意識 名主・沙汰人宛幕府奉行人奉書 p.623 備作地域の村と民衆の規範意識 「御百姓」意識 p.623 備作地域の村と民衆の規範意識 名主・百姓と官途 p.623) つづきをとじる |
| ばしょ | |
| ばしょ |
|
| NDCぶんるい | |
| NDCぶんるい | 217.5:岡山県 |
| けんさくキーワード | |
|---|---|
| けんさくキーワード | 郷土資料目次情報 |
| さんこうじょうほうげんまたはいんようじょうほうげん | |
| さんこうじょうほうげんまたはいんようじょうほうげん | [タイトルコード]1005010152007 |
| たいしょうねんれい | |
| たいしょうねんれい | 全年齢, 高校生 |
| きょうどじょうほうのげんご | |
| きょうどじょうほうのげんご | jpn |
| メタデータさくせいねんがっぴ | |
| メタデータさくせいねんがっぴ | 1991 |
| メタデータこうかいねんがっぴ | |
| メタデータこうかいねんがっぴ | 2011-02-16 |
| このページのURL | |
|---|---|
| このページのURL | http://digioka.libnet.pref.okayama.jp/detail-jp_c/id/kyo/M2008011911410663259 |