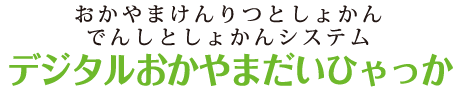きょうどじょうほうネットワーク > 新修倉敷市史 2,古代・中世
新修倉敷市史 2,古代・中世
カテゴリじょうほう
| きょうどじょうほうネットワーク > 目次情報 > 郷土資料目次情報 |
メタデータ
| タイトル | |
|---|---|
| タイトル | 新修倉敷市史 2,古代・中世 (シンシュウクラシキシシ 2 コダイ チュウセイ ) |
| きょうどじょうほうのしゅるい | |
| きょうどじょうほうのしゅるい | もじ |
| さくせいしゃまたはさくせいだんたい | |
| さくせいしゃまたはさくせいだんたい | 倉敷市史研究会/編集 (クラシキシシケンキュウカイ) |
| こうかいしゃまたはこうかいだんたい | |
| こうかいしゃまたはこうかいだんたい | 山陽新聞社 (サンヨウシンブンシャ) |
| きょうどじょうほうのがいよう | |
| きょうどじょうほうのがいよう | 天下分け目の備中国―古代中世における倉敷周辺の歴史的位置づけ 倉敷周辺の戦い p.2 天下分け目の備中国―古代中世における倉敷周辺の歴史的位置づけ 岡山県の位置 p.7 つづきをみる 天下分け目の備中国―古代中世における倉敷周辺の歴史的位置づけ 歴史的位置づけ p.12 古代社会の成立と展開 吉備社会の生成 p.18 古代社会の成立と展開 吉備社会の生成 神話・伝承のなかから(はじめに p.18 吉備の児島の生成 p.18 神武東征説話 p.18 墳丘墓の出現 p.18 楯築遺跡のもつ意味 p.18) 古代社会の成立と展開 吉備社会の生成 吉備氏の展開(各豪族集団の形成と動向 p.26 倉敷市域の古墳 p.26 東アジア世界の中で p.26) 古代社会の成立と展開 大和政権の地方支配と吉備 p.31 古代社会の成立と展開 大和政権の地方支配と吉備 大和政権と吉備氏(吉備氏のおこり p.31 吉備の産土神 p.31 楽神の性格 p.31 吉備津彦の到来(四道将軍など)p.31 温羅との戦い p.31) 古代社会の成立と展開 大和政権の地方支配と吉備 大和政権と児島(ヤマトタケルの伝承 p.39 欽明・敏達朝と児島 p.39) 古代社会の成立と展開 大和政権の地方支配と吉備 吉備の国造(吉備の県 p.43 国造の設置 p.43 律令国造 p.43 備前の国造 p.43 備中の国造 p.43) 古代社会の成立と展開 大和政権の地方支配と吉備 大化の改新と吉備地方(大化の改新と吉備の豪族 p.50 改新後の政情と吉備 p.50 鬼ノ城 p.50) 古代社会の成立と展開 <コラム> 日畑廃寺あたり p.57 律令制下の倉敷地方 壬申の乱と倉敷 p.60 律令制下の倉敷地方 壬申の乱と倉敷 壬申の乱と吉備地方の状況(壬申の乱と吉備地方 p.60 吉備の分割 p.60) 律令制下の倉敷地方 律令体制と倉敷周辺 p.63 律令制下の倉敷地方 律令体制と倉敷周辺 倉敷周辺の郡郷(山陽道 p.63 備前・備中の駅 p.63 国と国府 p.63 備前国の郡郷(里)p.63 備中国の郡郷(里)p.63 都羅郷 p.63 児島郷 p.63 深井郷 p.63 大市郷 p.63 阿智郷 p.63 阿智郷 p.63 間人郷 p.63 木簡に見られる郡郷 p.63) 律令制下の倉敷地方 律令体制と倉敷周辺 浅口郡と飛鳥寺(中央寺院と倉敷 p.71) 律令制下の倉敷地方 律令体制と倉敷周辺 民衆の負担(律令体制下の貢納体制 p.73 調と農民 p.73 調と鉄 p.73 庸と農民 p.73 その他の負担 p.73 兵役 p.73 出挙 p.73 備中国大税負死亡人数帳 p.73) 律令制下の倉敷地方 律令体制と倉敷周辺 条里制の整備(条里制 p.84 坪 p.84 条里制の分布 p.84 倉敷市内の条里制地割遺構 p.84 窪屋郡条里 p.84 林地区の条里制 p.84 児島地区の条里制 p.84 窪屋・都宇両郡の条里制プラン p.84) 律令制下の倉敷地方 律令体制と倉敷周辺 備前・備中の古代説話(川島河の大蛇 p.92 禅師弘済 p.92 ひきのまき人 p.92 穀物を断つ聖 p.92 白髪部猪麿 p.92 備前国の一人の沙弥 p.92 備中国賀陽良藤 p.92 地蔵によって命を助けられる p.92 備中の国の阿清 p.92) 律令制下の倉敷地方 律令制の変容 p.104 律令制下の倉敷地方 律令制の変容 中央の政治情況と吉備(律令初期の動揺 p.104 僧道鏡と和気清麻呂 p.104) 律令制下の倉敷地方 律令制の変容 中央官僚と吉備(国司たち p.107 藤原園人と吉備 p.107 藤原保則と民衆 p.107 保則の仁政 p.107) 律令制下の倉敷地方 律令制の変容 在地土豪の中央進出(備前の和気氏 p.112 下道郡の吉備真備 p.112 真備の入唐 p.112 再度入唐 p.112 官人としての真備 p.112) 律令制下の倉敷地方 律令制の変容 初期荘園(大寺院の土地所有 p.118 初期荘園 p.118) 律令制下の倉敷地方 律令制の変容 平安初期の政治と社会(長岡京遷都と征夷事業 p.120 平安京造営と平安初期政治 p.120 荘園の盛行 p.120 平安初期の倉敷周辺 p.120) 律令制下の倉敷地方 律令制の変容 九世紀の東国と瀬戸内のようす(東国の?馬の党 p.127 瀬戸内の海賊(一)p.127 藤原園人の進言 p.127 瀬戸内の海賊(二)p.127 海賊対策 p.127) 王朝国家と院政・平氏政権 王朝国家の成立 p.136 王朝国家と院政・平氏政権 王朝国家の成立 王朝国家の成立(律令制社会の変貌 p.136 王朝国家 p.136 地方支配の特徴 p.136 人から土地へ p.136 菅原道真の左遷 p.136 延喜荘園整理令 p.136) 王朝国家と院政・平氏政権 王朝国家の成立 瀬戸内の海賊―海で刃向かう人々―(承平天慶の乱 p.143 平将門の乱 p.143 藤原純友の乱 p.143 日振島の海賊 p.143 純友の出奔 p.143 乱の本格化 p.143 純友の追捕 p.143 海賊の残党 p.143) 王朝国家と院政・平氏政権 王朝国家の成立 鹿田荘事件と瀬戸内海航路(安和の変 p.151 備前守藤原理兼の赴任 p.151 鹿田荘事件 p.151 鹿田荘事件と中央政治 p.151 鹿田荘と海上交通 p.151 チャーター船 p.151 藤原高遠の歌 p.151) 王朝国家と院政・平氏政権 王朝国家の成立 摂関期の政治と国司制度(摂関政治 p.159 摂関時代の政治 p.159 摂関時代の太政官組織 p.159 六衛府・検非違使・蔵人 p.159 国司制度の変容 p.159 成功 p.159 任国への下向 p.159 境迎と神拝 p.159 因幡国一宮 p.159 総社と一宮 p.159 遙任制と在庁官人 p.159 国司のエピソード p.159 尾張国解文 p.159 苛政上訴善状提出 p.159 備前国の善状 p.159 貢納制と変質 p.159) 王朝国家と院政・平氏政権 王朝国家の成立 備前・備中の国の位置づけ(国の格づけ p.180 公卿兼国 p.180 公卿経歴国 p.180 国のランクづけ p.180 ト食国 p.180 大嘗会 p.180 古代の関 p.180 「西の関所」p.180) 王朝国家と院政・平氏政権 院政・平氏政権と倉敷周辺 p.192 王朝国家と院政・平氏政権 院政・平氏政権と倉敷周辺 院政の成立(後三条天皇の政治 p.192 後三条天皇の院庁始め p.192 院政と院の近臣 p.192 白河院政 p.192 鳥羽院政 p.192 保元の乱 p.192 後白河院政 p.192 平治の乱 p.192 難波恒房と雷 p.192) 王朝国家と院政・平氏政権 院政・平氏政権と倉敷周辺 平氏政権の成立とその滅亡―海に生きる政権―(平 正盛 p.199 平 忠盛 p.199 平 清盛 p.199 平氏と海外貿易 p.199 鹿ヶ谷事件 p.199 平氏打倒の動き p.199) 王朝国家と院政・平氏政権 院政・平氏政権と倉敷周辺 平氏と備前・備中地方(平正盛と海賊 p.204 平忠盛と海賊 p.204 備前守と海賊 p.204 源頼朝の挙兵 p.204 木曽義仲の入京 p.204 西海の平氏 p.204) 王朝国家と院政・平氏政権 院政・平氏政権と倉敷周辺 平氏政権と備前・備中の武士―海をはさむ戦い―(片田舎の無骨な侍 p.211 藤原成親と難波経遠 p.211 成親の最期 p.211 治承寿永の内乱と備作の武士 p.211 妹尾太郎兼康 p.211 妹尾兼康の最期 p.211 水島の合戦 p.211 平氏の反撃 p.211 一の谷と備作武士 p.211 藤戸合戦 p.211) <コラム> 水島の合戦史跡を訪ねて p.227 <コラム> 藤戸の合戦史跡を訪ねて p.228 平安期の社会と文化 平安中・後期の倉敷地方 p.232 平安期の社会と文化 平安中・後期の倉敷地方 王朝国家期の倉敷地方(荘園整理令 p.232 備前・備中国の動向 p.232 備前刀 p.232 大嘗会悠紀主基詠歌 p.232 女真族の来襲 p.232 備中吉備津神社事件 p.232 新山の別所 p.232) 平安期の社会と文化 平安中・後期の倉敷地方 院政・平氏政権期の倉敷地方(備前・備中国の動向 p.239 備前国通生荘 p.239 児島の泊 p.239) 平安期の社会と文化 平安期の荘園―倉敷市域および周辺の荘園―(荘園の発達 p.243 荘園の発達 荘園とは p.243 荘園の発達 初期荘園 p.243 荘園の発達 雑役免系荘園 p.243 荘園の発達 寄進地系荘園 p.243 荘園の発達 勅免地系荘園 p.243 荘園の発達 国衙領と開発領主 p.243 荘園の発達 別名の公認 p.243 荘園の発達 在庁官人 p.243 倉敷市域の荘園 p.249 倉敷市域の荘園 通生荘 p.249 倉敷市域の荘園 万寿荘 p.249 倉敷市域の荘園 富田荘 p.249 倉敷市域の荘園 子位荘 p.249 倉敷周辺の荘園 p.251 倉敷周辺の荘園 神崎荘・上東郷 p.251 倉敷周辺の荘園 鹿田荘 p.251 倉敷周辺の荘園 肥土荘 p.251 倉敷周辺の荘園 足守荘 p.251 倉敷周辺の荘園 生石荘 p.251 倉敷周辺の荘園 田上本荘 p.251 倉敷周辺の荘園 佐方荘・多気荘 p.251 倉敷周辺の荘園 橋本荘 p.251 倉敷周辺の荘園 駅里荘 p.251 倉敷周辺の荘園 大井荘 p.251 倉敷周辺の荘園 利生荘 p.251) 平安期の社会と文化 古代の社会と文化 p.255 平安期の社会と文化 古代の社会と文化 倉敷地域の神社祭祀(律令時代の神祗 p.255 倉敷地域の式内社 p.255) 平安期の社会と文化 古代の社会と文化 仏教文化の展開(仏教伝来と地方への伝播 p.260 県下の飛鳥時代寺院跡 p.260 県下の白鳳時代寺院跡 p.260 倉敷地域の山上寺院 p.260 報恩大師開基伝承の寺々 p.260) 平安期の社会と文化 古代の社会と文化 倉敷地方の平安期寺院(浅原の安養寺 p.269 安養寺と浄土教 p.269) 平安期の社会と文化 古代の社会と文化 祥瑞思想の浸透(祥瑞とは p.272 備前・備中から p.272) 武家政権の登場と倉敷周辺 鎌倉幕府の成立と公家政権 p.276 武家政権の登場と倉敷周辺 鎌倉幕府の成立と公家政権 鎌倉幕府の成立と守護地頭の設置(平氏の滅亡と京都・鎌倉 p.276 源平合戦と備前・備中 p.276 守護・地頭の設置 p.276 「通説的」理解の動揺 p.276 惣追捕使土肥実平の下向 p.276 土肥実平の軍政と地域のようす p.276 戦乱・飢饉・地震の文治元年 p.276 備前・備中の支配 p.276 地頭佐々木盛綱の支配 p.276) 武家政権の登場と倉敷周辺 鎌倉幕府の成立と公家政権 重源の活動と備前・備中(荒廃からの復興と重源 p.293 備前・備中での重源の活動 p.293 重源による交通路整備 p.293 瀬戸内水運の整備事業 p.293) 武家政権の登場と倉敷周辺 承久の乱と倉敷周辺 p.303 武家政権の登場と倉敷周辺 承久の乱と倉敷周辺 承久の乱(建久以後の政局の推移 p.303 後鳥羽上皇による院政 p.303 頼朝死後の幕府 p.303 後鳥羽の討幕計画 p.303) 武家政権の登場と倉敷周辺 承久の乱と倉敷周辺 頼仁親王と児島(承久の乱後の処置 p.308 頼仁親王の児島配流 p.308 将軍になる可能性のあった頼仁親王 p.308 児島の墓・石塔 p.308) 武家政権の登場と倉敷周辺 承久の乱と倉敷周辺 乱後の公武関係と備前・備中(承久の乱の人々への影響 p.314 承久京方と備前・備中 p.314 藤原秀康と備前・備中 p.314 備中吉備津宮と新捕地頭 p.314 西園寺公経・九条道家と北条氏 p.314 文永・弘安の役 p.314 モンゴル襲来と瀬戸内 p.314 幕府の支配権強化 p.314 悪党・海賊の蜂起 p.314) 鎌倉時代の社会と文化 備前・備中地方の所領単位(中世の所領単位 p.328) 鎌倉時代の社会と文化 備前・備中地方の所領単位 中世の所領単位(中世の所領単位 p.328 大田文 p.328) 鎌倉時代の社会と文化 備前・備中地方の所領単位 備前国の郷保(鎌倉時代の備前国郷保 p.329 枚石郷 p.329 弘西郷 p.329 三野新郷 p.329 伊福郷 p.329 津島郷 p.329 野田保 p.329 三宅郷 p.329 波智郷 p.329) 鎌倉時代の社会と文化 備前・備中地方の所領単位 備中国の郷保(鎌倉時代の備中国郷保 p.333 隼島保 p.333 大市郷 p.333 三須郷 p.333 赤浜保 p.333 山手保 p.333 久米荘 p.333 庭妹郷 p.333 板倉郷 p.333 阿宗郷 p.333 服部郷 p.333 刑部郷 p.333 野山郷 p.333 久米保 p.333 吉河保 p.333 二万郷 p.333 原郷 p.333 上原郷 p.333 下原(郷)p.333 大島保 p.333 戸見保 p.333) 鎌倉時代の社会と文化 備前・備中地方の所領単位 倉敷市域の荘園(得芳荘 p.340 大市荘 p.340 阿智荘 p.340 生坂荘 p.340 子位荘 p.340 渋江荘 p.340 万寿荘 p.340 穂太荘 p.340 富田荘 p.340) 鎌倉時代の社会と文化 備前・備中地方の所領単位 備前国の隣接郡域荘園(鹿田荘 p.346 大安寺荘 p.346 三野新荘 p.346 新堤保 p.346 児島荘 p.346 波佐川荘 p.346 豊岡荘 p.346 枳束荘 p.346) 鎌倉時代の社会と文化 備前・備中地方の所領単位 備中国の隣接郡域荘園(河面荘 p.349 妹尾荘 p.349 生石荘 p.349 足守荘 p.349 大井荘 p.349 多気荘 p.349 巨勢荘 p.349 吉備津宮 p.349 水内荘 p.349 橋本荘 p.349 田上荘 p.349 園荘 p.349 小坂荘 p.349) 鎌倉時代の社会と文化 備前・備中地方の所領単位 文応の大嘗会(阿智荘役 p.355 一国平均役 p.355) 鎌倉時代の社会と文化 中世所領の内部構造 p.358 鎌倉時代の社会と文化 中世所領の内部構造 所領の内部構造と農民の生活(荘園の内部構造 p.358 人給田 p.358 除田と定田 p.358 中世の農業暦 p.358 在家役 p.358 二毛作の成立 p.358) 鎌倉時代の社会と文化 中世所領の内部構造 名と階層構成(名とは何か p.363 名の地域差 p.363 名の時代的変化 p.363) 鎌倉時代の社会と文化 中世所領の内部構造 地頭の荘園侵略(地頭とは何か p.366 地頭と下司 p.366 地頭と下司の違い p.366 鎌倉幕府と荘園(制)p.366 地頭請と下地中分 p.366 西国御家人 p.366) 鎌倉時代の社会と文化 中世宗教の社会的展開 p.371 鎌倉時代の社会と文化 中世宗教の社会的展開 熊野五流の展開(社会に浸透した鎌倉仏教 p.371 児島の五流修験 p.371 熊野信仰と修験道 p.371 『長床縁由興廃伝』に見える伝承 p.371 熊野神の海上ルート p.371 伯耆桜山寺の住僧、児島から高野山へ p.371 熊野修験と海上交通 p.371) 鎌倉時代の社会と文化 中世宗教の社会的展開 在地寺社の動向―海からの宗教と山の宗教―(海からの信仰と山の宗教 p.381 浅原安養寺と栄西 p.381 朝原の円満院・阿弥陀院 p.381 西岡廃寺と日差山廃寺 p.381 海上交通の活発化と宗教の展開 p.381 河口部海際にあった藤戸寺 p.381 連島の宝島寺 p.381 児島通生の般若院 p.381 寂弁の中興と大般若経 p.381 「海からもたらされた」大般若経 p.381 海からの本尊 p.381 寺院の由緒と「弘安」年号 p.381 弘安ごろの社会の大変動 p.381) 鎌倉時代の社会と文化 <コラム>(熊野の里―郷内地区を歩く― p.402) 第七章 中世後期の政治と社会 福山合戦と南北朝の内乱 p.406 第七章 中世後期の政治と社会 福山合戦と南北朝の内乱 倒幕の動き(天皇家の分裂と後醍醐天皇の登場 p.406 正中の変と元弘の乱 p.406 宗良親王と備前児島吹上 p.406 鎌倉幕府の滅亡 p.406 備前・備中での動向 p.406) 第七章 中世後期の政治と社会 福山合戦と南北朝の内乱 備前・備中と建武の新政(建武の新政と備中国渋江荘 p.413 建武の新政崩壊への道 p.413 挙兵した備前児島の勢力 p.413 足利尊氏の九州への敗走 p.413 室津の軍議と備前児島到着 p.413) 第七章 中世後期の政治と社会 福山合戦と南北朝の内乱 福山合戦と児島高徳の動向(福山合戦の前夜 p.420 足利軍備前・備中に進攻 p.420 児島高徳の再挙兵 p.420 備中福山合戦 p.420 合戦の決着 p.420 福山合戦の足利方勢力 p.420 福山合戦後の児島高徳一族 p.420 その後の児島高徳の動向 p.420 佐々木信胤の寝返り p.420 『太平記』の信憑性 p.420) 第七章 中世後期の政治と社会 福山合戦と南北朝の内乱 児島高徳の人物論と出自(高徳の抹殺 p.432 高徳の復活 p.432 高徳の出自 p.432 高徳の終焉の地 p.432 高徳の実像 p.432 『太平記』の作者論 p.432 再び高徳は実在か架空か p.432) 第七章 中世後期の政治と社会 守護職の変遷 p.445 中世後期の政治と社会 守護職の変遷 備前国守護の変遷(中世後期の守護 p.445 最初の備前守護松田盛朝 p.445 備前守護細川顕氏 p.445 赤松氏の備前守護就任 p.445 康暦の政変と児島の情勢 p.445 嘉吉の乱前後の備前守護 p.445 応仁の乱以後の備前守護 p.445) 中世後期の政治と社会 守護職の変遷 備中国守護の変遷(最初の備中守護南宗継 p.452 秋庭氏・宮氏・渋川氏 p.452 細川備中守護家 p.452 細川頼重・氏久・勝久 p.452 備中守護の分郡支配 p.452 細川之持 p.452 細川政春以後 p.452) 中世後期の政治と社会 守護支配の展開とその終焉 p.462 中世後期の政治と社会 守護支配の展開とその終焉 備前国児島郡分郡守護の成立(飯尾真覚の立場 p.462 児島郡における細川氏 p.462 分郡守護成立の契機 p.462 備前国小豆島の帰属 p.462 細川持常の児島郡獲得の意図 p.462 戦国期の児島郡分郡支配 p.462) 中世後期の政治と社会 守護支配の展開とその終焉 備中守護細川氏の支配(体制の変化と守護補任 p.462 細川氏について p.462 両守護体制 p.462 守護奉行人制 p.473 備中一宮社務職 p.462 備中惣社宮造営事業 p.462 細川管領家の関与 p.473 遷宮行事にかかわる周辺寺院 p.473) 中世後期の政治と社会 守護支配の展開とその終焉 備中大合戦(守護代庄元資の反乱 p.483 守護細川勝久の反撃 p.483 合戦の再燃 p.483 合戦の前哨戦 p.483 備中大合戦の意義 p.483) 中世後期の政治と社会 <コラム> 兵どもが夢の後、備中福山城跡 p.493 荘園・寺社の様相と海に向かう地域 中世後期の荘園と武家勢力の押領 p.496 荘園・寺社の様相と海に向かう地域 中世後期の荘園と武家勢力の押領 備前国通生荘と荘園領主たち(西園寺家領通生本荘 p.496 大覚寺領通生新荘 p.496 その後の展開 p.496 三条西家領通生本荘 p.496 通生荘の荘域 p.496) 荘園・寺社の様相と海に向かう地域 中世後期の荘園と武家勢力の押領 備中国万寿荘と新熊野社(備中国万寿荘 p.505 守護勢力の侵略 p.505 その後の押妨 p.505 万寿本荘荘官盛秀の土倉興行 p.505 万寿荘からの年貢未進 p.505 荏胡麻の栽培 p.505 その後の万寿荘 p.505) 荘園・寺社の様相と海に向かう地域 中世後期の荘園と武家勢力の押領 備中国富田荘・戸見保(領主への課役負担と下司職 p.515 富田荘と中央の政争 p.515 戸見保について p.515 文明年間の富田荘・戸見保 p.515) 荘園・寺社の様相と海に向かう地域 中世後期の荘園と武家勢力の押領 その他の市内の荘園(備前国児林荘と櫃石島 p.521 備前国連島荘 p.521 備中国生坂荘 p.521 備中国渋江荘 p.521 備中国武並保 p.521 備中国得芳荘・阿智荘 p.521 備中国平田郷 p.521 備中国穂井田荘 p.521 吉備津社領 p.521) 荘園・寺社の様相と海に向かう地域 水運の展開と河口都市・港町の繁栄 p.529 荘園・寺社の様相と海に向かう地域 水運の展開と河口都市・港町の繁栄 児島付近の海上航路の変化と港湾の整備(鎌倉期以前の航路 p.529 港としての下津井 p.529 南北朝・室町・戦後期の航路 p.529) 荘園・寺社の様相と海に向かう地域 水運の展開と河口都市・港町の繁栄 水運で栄えた連島・西阿知と下津井(連島船の動向 p.534 河川と内海の中継地 p.534 物資集積地の西阿知 p.534 西阿知の地形的状況 p.534 下津井港の繁栄 p.534 海からの恵みと熊野信仰 p.534 宝島寺聖教類に見る連島周辺 p.534 棟礼から見た中世の連島 p.534) 荘園・寺社の様相と海に向かう地域 水運の展開と河口都市・港町の繁栄 薩摩で討滅された連島の三宅国秀(三宅国秀をめぐる史料 p.549 事件の概要 p.549 国秀に琉球征服の野望ありや? p.549 島津氏の遠謀 p.549) 荘園・寺社の様相と海に向かう地域 児島修験の隆盛と中央・地方寺社 p.558 荘園・寺社の様相と海に向かう地域 児島修験の隆盛と中央・地方寺社 児島山伏と東寺・新熊野神社(南北朝期以降の関係史料 p.558 東寺灌頂院御影供執事頭役 p.558 覚王院宋弁僧正 p.558 執事の職務と門徒追放の背景 p.558 新熊野山伏と児島山伏 p.558 智蓮光院宣深僧正 p.558) 荘園・寺社の様相と海に向かう地域 児島修験の隆盛と中央・地方寺社 児島山伏と聖護院門跡(備前児島と応仁の乱 p.567 聖護院門跡 p.567 聖護院道興の巡錫 p.567 道興の児島来訪と社領の侵略 p.567 備前児島の上野氏 p.567 『新熊野山縁記』所収の文書 p.567 道興の西国下向の目的 p.567 永正十五年の訴訟 p.567) 荘園・寺社の様相と海に向かう地域 児島修験の隆盛と中央・地方寺社 熊野信仰の広がり(先達と御師 p.576 備前・備中からの参詣者 p.576 檀那職の売買 p.576 海上交通と熊野信仰 p.576 清田八幡神社の棟礼 p.576 至徳・応永の修造 p.576) 下剋上の世と倉敷 瀬戸内をめぐる戦い p.586 下剋上の世と倉敷 瀬戸内をめぐる戦い 海に開かれた児島(下剋上の世の胎動 p.586 瀬戸内の水軍 p.586 厳島合戦 p.586 伊予水軍の力 p.586 阿波・讃岐国の動向 p.586 四国の香西氏児島をうかがう p.586 香西宗心の野望 p.586) 下剋上の世と倉敷 瀬戸内をめぐる戦い 本太城と本太の合戦(海に浮かぶ「児島」p.595 児島の歴史を考えるとき p.595 本太城の位置づけ p.595 本太城の立地 p.595 史料に見える「本太」p.595 児島と連島 p.595) 下剋上の世と倉敷 瀬戸内をめぐる戦い 永禄・元亀・天正の本太合戦(永禄の合戦 p.602 永禄十一年 p.602 小早川隆景と村上武吉 p.602 村上武吉の打渡状 p.602 元亀の合戦 p.602 阿波篠原氏の乱入 p.602 天正二年の合戦 p.602 天正八年の合戦 p.602) 下剋上の世と倉敷 備前・備中をめぐる攻防 p.612 下剋上の世と倉敷 備前・備中をめぐる攻防 宇喜多氏の台頭(宇喜多氏の出自 p.612 宇喜多能家と直家 p.612 策略家宇喜多直家 p.612) 下剋上の世と倉敷 備前・備中をめぐる攻防 備中をうかがう尼子氏(尼子氏の出自 p.616 尼子詮久 p.616 尼子氏の美作進出 p.616 『美作太平記』に見る尼子氏 p.616 尼子氏の備中守護 p.616 中国地方の覇権をめぐって p.616 尼子晴久の備後三吉攻め p.616 尼子晴久の安芸国出陣 p.616 大内義隆の尼子攻め p.616 大内義隆の死 p.616 尼子氏の幸山城攻め p.616 尼子氏の経山城攻め p.616) 下剋上の世と倉敷 備前・備中をめぐる攻防 備中の覇者三村氏(東国武士の西遷 p.626 三村氏の系譜 p.626 三村家親の松山城入部 p.626 三村氏の児島への関心 p.626 尼子氏と戦う三村氏 p.626 宇喜多氏による三村家親暗殺 p.626 明禅寺崩れ p.626 海を越えた諸衆の支配 p.626 毛利氏と宇喜多氏の結びつき p.626 毛利氏の佐井田城攻め p.626 三村氏の滅亡 p.626 常山城の合戦 p.626) 下剋上の世と倉敷 備前・備中をめぐる攻防 毛利氏の備中侵略(三村氏の離脱 p.639 国吉城・譲葉城攻め p.639 鬼身城攻め p.639 備中松山城の落城 p.639 いざ児島へ、常山へ p.639 常山合戦、女軍鶴姫の活躍 p.639 児島の一円支配に向けて p.639 八浜合戦 p.639 小串と天城を結ぶ児島の「海の道」p.639) 下剋上の世と倉敷 <コラム> 「川の道」から「海の道」へ―高梁川から西阿知・連島・瀬戸内海へ― p.651 戦国大名と天下統一への途 高松城水攻めと倉敷(日幡衆と日幡城 p.654) 戦国大名と天下統一への途 高松城水攻めと倉敷 日幡衆と日幡城(吉備津の地 p.654 境目城の一つ日幡城 p.654 日幡城の立地 p.654 軍記物の中の日幡城 p.654 拠点日幡城 p.654 日幡衆と吉備津神社 p.654 日幡城の役割 p.654 日幡・辛川・今保を結ぶ三角形 p.654 羽柴秀吉と上原氏 p.654 日幡城と宇喜多秀家 p.654 「衆」の意味するもの p.654 逆心 p.654) 戦国大名と天下統一への途 高松城水攻めと倉敷 高松城と日差山(天下統一への途 p.668 羽柴軍の中国入り p.668 高松城攻略へ p.668 吉川元長の書状 p.668 調略 p.668 羽柴秀吉の密着 p.668 密書が意味するもの p.668 軍記物に表れた勝者と敗者 p.668 羽柴秀吉、岡山から西へ p.668 備前・備中国の境目城 p.668 備中加茂城 p.668 清水宗治の最期 p.668 本能寺の変 p.668) 戦国大名と天下統一への途 毛利氏による備中分割 p.684 戦国大名と天下統一への途 毛利氏による備中分割 備中国での毛利氏と細川氏(備中守護細川氏 p.684 児島は宇喜多氏、連島は細川氏 p.684 備中の細川通頼 p.684 細川通薫 p.684 連島は備前か備中か p.684 境界としての連島 p.684) 戦国大名と天下統一への途 毛利氏による備中分割 高梁川の東と西(羽柴氏と毛利氏の和睦 p.691 高梁川の内と外 p.691 秀吉の天下統一 p.691 毛利氏にとっての高梁川 p.691 児島と宇喜多秀家 p.691 宇喜多秀家と豊臣秀吉 p.691 連島 p.691 交易を物語る下津井 p.691 児島酒・藤戸石 p.691 人の「自由」な道、川と海 p.691) 戦国大名と天下統一への途 倉敷の中世城郭(中世の城郭 p.702 倉敷市内の分布状況 p.702 鼻高山城跡 p.702 戸山城跡 p.702 岩山城跡 p.702 神水山城跡 p.702 本太城跡 p.702 川越山城跡 p.702 黒山城跡 p.702 鷹巣城跡 p.702 日幡城跡 p.702 松島城跡 p.702 万寿城跡 p.702 片島城跡 p.702 森本松山城跡 p.702) 戦国大名と天下統一への途 <コラム> 中世城郭を歩く p.727 別編 備中の刀剣 はじめに(鉄の大生産地備中 p.730) 別編 備中の刀剣 鉄の生産と流通(備中の鉄と刀剣 p.731 備中の鉄産出と輸送 p.731 鉄と税 p.731) 別編 備中の刀剣 備中刀工の居住地(作刀に記された居住地 p.735 製作地の地理的位置 p.735 青江と万寿荘 p.735) 別編 備中の刀剣 備中青江物の時代区分と作風(青江刀工の時代区分 p.741) 別編 備中の刀剣 備中青江物の時代区分と作風 古青江(古青江の刀工と製作年代 p.747 古青江の作風と特色 p.747) 別編 備中の刀剣 備中青江物の時代区分と作風 中青江(中青江の刀工と製作年代 p.751 中青江の作風と特色 p.751) 別編 備中の刀剣 備中青江物の時代区分と作風 末青江(末青江の刀工と時代区分 p.753 末青江の作風と特色 p.753) 別編 備中の刀剣 妹尾鍛冶(妹尾鍛冶とその特色 p.756) 別編 備中の刀剣 水田鍛冶(水田鍛冶の出現と展開 p.758) 別編 備中の刀剣 <コラム> 日本刀の見どころ p.765 別編 備中の刀剣 <コラム> 古刀と新刀 p.767 別編 古代・中世の美術文化財 浅原・安養寺の金銅仏二? p.770 別編 古代・中世の美術文化財 浅原・安養寺の金銅仏二? 白鳳期金銅誕生仏をめぐって(安養寺の金銅誕生仏 p.770 白鳳時代の小金銅仏の地方伝播 p.770 中国地方に在銘金銅仏の存在 p.770 竹元寺銅造観音菩薩立像 p.770) 別編 古代・中世の美術文化財 浅原・安養寺の金銅仏二? 安養寺の銅造如来立像をめぐって(安養寺銅造如来立像 p.774) 別編 古代・中世の美術文化財 安養寺の木彫毘沙門天群像と平安時代の仏像(安養寺木彫毘沙門天群像 p.776 平安時代における木彫仏の地方伝播 p.776 特定尊像の集中制作 p.776 吉備津御前神の本地 p.776 日差山と庚申山の毘沙門天磨崖仏 p.776 宝島寺天王形立像二? p.776 素盞嗚神社聖観音立像 p.776 遍照院聖観音立像 p.776 薬師院薬師如来坐像 p.776) 別編 古代・中世の美術文化財 鎌倉・南北朝期以後の彫刻通観(般若院阿弥陀如来立像 p.783 誓願寺阿弥陀如来坐像 p.783 宝島寺菩薩頭 p.783 鴻八幡宮狛犬と仏師慶尊 p.783 円通寺銅造地蔵半跏像と萱谷半重郎 p.783) 別編 古代・中世の美術文化財 石造美術の伝来と児島地方(天石門別保布羅神社の釈塔様 p.788 総願寺跡石造宝塔 p.788 藤戸寺石造五重層塔 p.788) 別編 古代・中世の美術文化財 児島五流修験の発展と中世文化(五流尊瀧院石造大宝塔 p.794 尾道・浄土寺宝塔との様式関係 p.794 新熊野山用木造唐櫃 p.794 熊野道地蔵石仏 p.794 本莊八幡宮石鳥居 p.794 聖護院系と東寺系の抗争 p.794 熊野神社本殿群 p.794 熊野大権現長床 p.794 清田八幡神社本殿 p.794 由加神社本殿 p.794 蓮台寺銅鐘 p.794) 別編 古代・中世の美術文化財 寺院建築通観(遍照院三重塔 p.804 五流尊瀧院他四カ院三重塔 p.804 蓮台寺本堂と多宝塔 p.804 宝島寺仁王門 p.804 行願寺仁王門 p.804 地蔵院経堂及び輪蔵 p.804) 別編 古代・中世の美術文化財 中世仏画通観(宝島寺と清瀧寺の白衣観音図 p.808 倉敷市の李朝仏画 p.808 宝島寺三蔵幀画 p.808 地蔵院の李朝仏画 p.808 心鏡寺阿弥陀三尊来迎図 p.808) 資料編補遺 古代・中世編 p.813 付録 国司補任表 p.837 つづきをとじる |
| ばしょ | |
| ばしょ | 岡山県倉敷市中央1丁目27 |
| NDCぶんるい | |
| NDCぶんるい | 217.5:岡山県 |
| けんさくキーワード | |
|---|---|
| けんさくキーワード | 郷土資料目次情報 |
| さんこうじょうほうげんまたはいんようじょうほうげん | |
| さんこうじょうほうげんまたはいんようじょうほうげん | [タイトルコード]1009810119183 |
| たいしょうねんれい | |
| たいしょうねんれい | 全年齢, 高校生 |
| きょうどじょうほうのげんご | |
| きょうどじょうほうのげんご | jpn |
| メタデータこうかいねんがっぴ | |
| メタデータこうかいねんがっぴ | 2011-02-24 |
| メタデータこうしんねんがっぴ | |
| メタデータこうしんねんがっぴ | 2018-08-02 |
| このページのURL | |
|---|---|
| このページのURL | http://digioka.libnet.pref.okayama.jp/detail-jp_c/id/kyo/M2008011911434763379 |