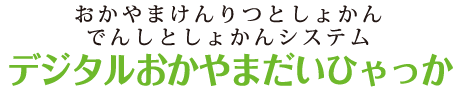きょうどじょうほうネットワーク > 総社市史 古代中世史料編
総社市史 古代中世史料編
カテゴリじょうほう
| きょうどじょうほうネットワーク > 目次情報 > 郷土資料目次情報 |
メタデータ
| タイトル | |
|---|---|
| タイトル | 総社市史 古代中世史料編 (ソウジャシシ コダイチュウセイシリョウヘン) |
| きょうどじょうほうのしゅるい | |
| きょうどじょうほうのしゅるい | もじ |
| さくせいしゃまたはさくせいだんたい | |
| さくせいしゃまたはさくせいだんたい | 総社市史編さん委員会/編集 (ソウジャシシヘンサンイインカイ) |
| こうかいしゃまたはこうかいだんたい | |
| こうかいしゃまたはこうかいだんたい | 総社市 (ソウジャシ) |
| きょうどじょうほうのがいよう | |
| きょうどじょうほうのがいよう | 古代編 (奈良時代以前 p.3 奈良時代 p.42 平安時代 p.113) 中世編編年史料 (鎌倉時代 p.269 南北朝・室町・安土桃山時代 p.290) つづきをみる 中世編家わけ史料 (九条家文書(上原郷関係)p.373 吉備津神社文書 p.545 赤木家文書 p.576 池上家総社宮文書 p.579 佐野家文書 p.604 清水家文書 p.610 中島家文書 p.613 難波家関係文書 p.624 禰屋家関係文書 p.632 林家文書 p.648 宝福寺文書 p.649) 中世編軍事物 (太平記(抜粋)p.671 中国兵乱記 p.688) 補遺 p.851 古代編細目次 奈良時代以前 古事記 (孝安段(大吉備諸進命は孝安の皇子 p.3) 孝霊段(吉備一族の始租は孝霊の二皇子とする p.3)) 古代編細目次 奈良時代以前 日本書紀 孝霊二年二月丙寅条(吉備臣の始租は孝霊皇子の稚武彦 p.4) 古代編細目次 奈良時代以前 古事記 開化段(吉備品遅君の租は息長日子王 p.5) 日本書紀 崇神十年九月甲午条(吉備津彦が四道将軍の一人として西道に向かう p.5) 日本書紀 崇神六十年七月己酉条(吉備津彦らが出雲振根を誅する p.6)) 古代編細目次 奈良時代以前 (古事記 景行段(若建吉備津日子の娘が小碓命らを生む p.7) 日本書紀 景行四年二月甲子条(吉備兄彦皇子は景行の子 p.7) 日本書紀 景行二十七年十二月条(日本武が吉備の穴海の悪神を殺す p.7) 日本書紀 景行二十八年二月乙丑条(日本武が吉備穴済神を平らぐ p.8)) 古代編細目次 奈良時代以前 古事記 景行段(吉備臣らの租、御■友耳県建日子が倭建命の東征に参加する p.8) 古代編細目次 奈良時代以前 日本書紀 (景行四十年七月戊戌条(日本武の東征に吉備彦らが随伴する p.9) 景行四十年是歳条(吉備武彦が日本武と別れて越に向かう p.9) 景行五十一年八月壬子条(吉備武彦の娘が日本武の妃となり二皇子を生む p.10)) 古代編細目次 奈良時代以前 古事記 景行段(大吉備建比売が倭建命妃となり建貝児王を生む p.10) 古代編細目次 奈良時代以前 日本書紀 (神功皇后摂政前紀(吉備臣の租、鴨別が熊襲を征服するp.10 ) 応神二十二年三月丁酉条(応神妃兄媛が故郷の吉備に帰るp.11) 応神二十二年四月条(応神が兄媛の船を望見して歌を詠むp.11) 応神二十二年九月丙戌条(応仁が淡路を経て吉備に幸す p.12) 応神二十二年九月庚寅条(吉備一族の始租伝承と県分封記事 p.12)) 古代編細目次 奈良時代以前 先代旧事本紀 国造本紀(吉備一族および吉備地域の国造 p.13) 古代編細目次 奈良時代以前 古事記 仁徳段(黒日売と仁徳との恋愛物語 p.15 吉備国児嶋郡の仕丁が仁徳の浮気を語る p.17) 古代編細目次 奈良時代以前 日本書紀 (仁徳四十年二月条(吉備品遅部雄■らが隼別皇子・雌鳥皇女を追討 p.17) 仁徳六十七年是歳条(笠臣の租、県守が川嶋河の大■を殺すp.18 ) 雄略元年三月是月条(吉備の稚媛が雄略の妃となり二皇子を生む p.19) 雄略七月八月条(前津屋が雄略の攻撃をうけて滅ぶ p.19) 雄略七年是歳条(田狭・弟君の雄略に対する反乱伝承 p.20) 雄略八年二月条(吉備臣小梨らが新羅を授けて高句麓と戦う p.22) 雄略九年三月条(吉備上道釆女大海が紀小弓の妻となる p.23) 雄略九年五月条(上道釆女大海が韓奴を室屋に送る p.23) 雄略二十三年八月丙子条(雄略が星川皇子の反乱を予想し室屋らに遺詔す p.24 征新羅将軍吉備臣尾代が蝦夷の反乱を平らぐ p.25) 清寧即位前期(星川皇子が反乱し燔殺される p.25 上道臣ら星川の反乱を応援しようとして果さず p.26) 顕宗元年四月丁未条(吉備臣を山官の副とし山守部を支配させる p.27) 継体二十四年九月条(吉備韓子那多利らが近江毛野に殺される p.27) 安閑二年五月甲寅条(備後国・■■国に屯倉が設置された p.28) 欽明二年四月条(吉備臣が任那日本府次官として外交にかかわる p.28) 欽明五年三月条(百濟の聖明王が吉備臣らの外交を批評する p.29) 欽明五年十一月条(百濟の聖明王が吉備臣らの本国送還を求める p.30) 欽明十六年七月壬午条(蘇我稲目らが吉備五郡に白猪屯倉を置く p.31) 欽明十七年七月己卯条(稲目らが児嶋屯倉を置き瑞子を田令とする p.32) 欽明三十年正月辛卯条(胆津が白猪屯倉の田部の丁籍を検定する p.32) 欽明三十年四月条(胆津が白猪史となり田令の副となる p.32) 敏逹三年十月丙甲条(馬子が白猪屯倉の名籍を白猪史胆津に授ける p.33) ■明二年(六三〇)正月戊寅条(蚊屋釆女が蚊屋皇子を生む p.33) 大化元年(六四五)九月戊辰条(吉備笠臣垂が古人皇子の謀反に組する p.33) 大化元年(六四五)九月丁丑条(笠臣垂が古人皇子の謀反を密告する p.33)) 古代編細目次 奈良時代以前 白髪部五十戸木簡(「五十戸」および貢進物付札の最古の史料 p.34) 古代編細目次 奈良時代以前 日本書紀 ( 天武元年(六七二)六月丙戌条(吉備国守当麻公広嶋が近江方の使に斬られる p.34) 天武二年(六七三)三月壬寅条(吉備国分割の初見史料 p.35) 天武八年(六七九)三月己丑条(吉備大宰石川王が吉備にて病死する p.35) 天武十一年(六八二)七月戊午条(吉備国等が気候不順のため五穀実らず p.36) 天武十三年(六八四)十一月戊甲条(下道臣・笠臣に朝臣を賜姓する p.36)) 古代編細目次 奈良時代以前 続日本紀 ( 文武元年(六九七)■十二月己亥条(備中国等が飢えて賜給をうける p.36) 藤原宮出土木簡(軽部里からの貢進物付札 p.37 加夜評の貢進物付札 p.38 二万部里から鯛を大■として貢進した p.38 矢田部里からの春税の付札 p.38 下道朝臣吉備麻呂名の木簡 p.39) 文武四年(七〇〇)十月己未条(吉備■領に上毛野朝臣小足を任ずる p.39) 大宝元年(七〇一)三月壬寅条(備中の田を阿倍御主人に賜う p.39) 大宝二年(七〇二)九月辛巳条(備中国等に賑恤する p.40) 大宝三年(七〇三)正月甲子条(山陽道巡察使に穂積朝臣老を任ずる p.40) 慶雲元年(七〇四)四月壬午条(備中国等に賑恤する p.40)) 古代編細目次 奈良時代以前 下道■勝母骨蔵器銘 和銅元年(七〇八)十一月二十七日(下道■勝・■依の母骨蔵器の銘文 p.40) 古代編細目次 奈良時代 続日本紀 (和銅五年(七一二)七月壬午条(備中国等に始めて綾錦を織らせる p.42) 霊亀二年(七一六)八月癸亥条(真備が遺唐留学生として出国する p.42) 養老三年(七一九)七月庚子条(備中国等を管する■察使を任ずる p.43) 養老五年(七二一)八月癸巳条(備中国を管する■察使を替える p.43)) 古代編細目次 奈良時代 太政官府 類■三代格 養老六年(七二二)八月二十九日(備中国司らの入京に駅馬の使用を認める p.43) 古代編細目次 奈良時代 続日本紀 (養老六年(七二二)八月丁卯条(備中国等の国司の駅馬の使用を許す p.44) 神亀三年(七二六)八月乙亥条(備中国等の新任国司に食を給する p.45) 天平元年(七二九)四月癸亥条(山陽道の駅家をつくるため駅起稲を充てる p.45)) 古代編細目次 奈良時代 (勅類■三代格 天平三年(七三一)六月二十四日(備中国等の戸座に時服・月料を給する p.46) 続日本紀 天平三年(七三一)十一月丁卯条(山陽道鎮撫使に多治比真人県守を任ずる p.46) 続日本紀 天平四年(七三二)九月甲辰条(備中国等に遺唐使船をつくらせる p.47)) 古代編細目次 奈良時代 ( 播磨国正税帳(備中国■穂積朝臣老人らが播磨国を通過する p.47) 出雲国計会帳 天平六年(七三四)(備中国が百姓の本貫を遷す公文を出雲国等に出す p.48)) 古代編細目次 奈良時代 備中国風土記逸文(賀夜郡の松岡に国司・郡司らが御宅を新造する p.48 下道郡彌磨郷に関する伝説 p.49 宮瀬・宮瀬川の地名説話 p.49) 古代編細目次 奈良時代 (続日本紀 天平七年(七三五)四月辛亥条(真備が帰朝して書籍や諸物を献ずる p.50) 扶桑略記 天平七年(七三五)四月辛丑条(真備の持ち帰った書籍等と帰朝に関する伝説 p.50) 続日本紀 天平八年(七三六)正月辛丑条(真備に外従五位下を授位する p.51) 太政官符 類■符宣抄 天平九年(七三七)六月二十六日(山陽道等の国司に天然痘の予防官符を下す p.51)) 古代編細目次 奈良時代 続日本紀 (天平十年(七三八)五月庚午条(山陽道等の健児を停止する p.53) 天平十年(七三八)七月癸酉条(真備らに梅樹の詩を詠ぜしむ p.53) 天平十年(七三八)八月甲申条(山陽道諸国の借■を停める p.53)) 古代編細目次 奈良時代 官人歴名(下道朝臣広口が綾司に出仕する p.54) 古代編細目次 奈良時代 楊貴氏墓誌 天平十一年(七三九)八月十二日(真備の母の楊貴氏墓誌 p.55) 古代編細目次 奈良時代 備中国大税負死亡人帳 天平十一年(七三九)(天平十一年度の大税を負って死亡した人の歴名 p.56) 古代編細目次 奈良時代 続日本紀 (天平十二年(七四〇)八月癸未条(広嗣が真備・玄■の失脚をはかる p.60) 天平十三年(七四一)七月辛亥条(真備が東宮学士となる p.61) 天平十五年(七四三)六月丁酉条(真備が春宮大夫となる p.61) 天平十六年(七四四)九月甲戌条(山陽道巡察使が任命された p.61)) 古代編細目次 奈良時代 経師等調度充帳 天平十七年(七四五)(下道朝臣直言が福倍に付して文選音議を送る p.62) 古代編細目次 奈良時代 続日本紀 (天平十八年(七四六)四月丙戌条(山陽道鎮撫使を任ずる p.63) 天平十八年(七四六)十月丁卯条(真備に吉備朝臣の姓を賜う p.63) 天平十九年(七四七)二月戊辰条(備中国等に賑恤する p.63) 天平十九年(七四七)十一月丙子条(真備が右京大夫を兼任する p.63)) 古代編細目次 奈良時代 平城宮木簡 ( 天平十九年(七四七)二月九日(賀夜郡阿宗里から白米を貢進した p.64)(賀陽郡の人、漆部色人が庸米を貢進した p.64 賀夜郡から鉄一連を貢納した p.65 賀夜郡大井郷から鍬十口を貢進した p.65 八■郷から造酒用の春米を貢進した p.65 賀陽郡から俵を貢進した p.66 賀陽郡から貢進物付札 p.66 吉備命婦木簡 p.66 式部省関係木簡に吉備泉の名がみえる p.67 造宮関係の木簡に下道朝臣の名がある p.67 下道人守木簡 p.68)) 古代編細目次 奈良時代 千部法華経充本帳 天平二十年(七四八)(賀陽田主が千部法華経の写経に従事する p.68) 古代編細目次 奈良時代 続日本紀 (天平二十年(七四八)十一月己丑条(下道朝臣乙吉備らに朝臣を賜姓する p.69) 天平勝宝元年(七四九)七月甲午条(孝謙天皇即位し真備従四位上となる p.70) 天平勝宝二年(七五〇)正月己亥条(真備が筑前守に左遷される p.70)) 古代編細目次 奈良時代 造東大寺司移 天平勝宝二年(七五〇)五月二十六日(備中国等に帰郷中の衛士の位記を送る p.70) 古代編細目次 奈良時代 (続日本紀 天平勝宝三年(七五一)十一月丙戌条(真備が入唐副使となる p.71) 続疏出納帳 天平勝宝四年(七五二)五月二十三日(備中宮より四天王経等を請う p.71)) 古代編細目次 奈良時代 丹裏古文書第三十八号(仕丁貢進歴名に備中国より一人をあげる p.72) 古代編細目次 奈良時代 (続日本紀 天平勝宝六年(七五四)正月癸丑条(真備の船が屋久嶋を経て牟漏埼に漂着する p.74) 扶桑略記 天平勝宝六年(七五四)正月晦日条(真備から鑑真に日本への渡航を求める p.74) 唐大和上東征伝(吉備真備から鑑真に来日を請す p.74)) 古代編細目次 奈良時代 (日本国見在書目録(吉備真備が東観漢記を招来する p.75) 続日本紀 天平勝宝六年(七五四)四月庚午条(真備が大宰大弐となる p.75) 続日本紀 天平勝宝六年(七五四)十一月辛酉条(山陽道巡察使が任命された p.76) 続日本紀 天平勝宝八歳(七五六)六月甲辰条(真備が怡土城を築く p.76) 続日本紀 天平勝宝八歳(七五六)十月丁亥条(山陽道等の春米の海運時の賠償制を定める p.76) 続日本紀 天平勝宝八歳(七五六)十二月己亥条(備中国等の国分寺に幡等を施入する p.76)) 古代編細目次 奈良時代 (造東大寺司牒(備中国司らが人夫への粮米支給を停める p.77) 続日本紀 天平宝字二年(七五八)正月戊寅条(山陽道巡察使が任命された p.77) 画師行事功銭注進文 天平宝字二年(七五八)三月十七日(下道吉備が彩色画師として作業し功銭を受ける p.77)) 古代編細目次 奈良時代 続日本紀 (天平宝字二年(七五八)十二月戊甲条 唐の内乱の波及に備え真備に建議させる p.79) 天平宝字三年(七五九)三月庚寅条(真備が国防について建議する p.79) 天平宝字三年(七五九)五月甲戌条(山陽道等の地域の物価は右平準署が掌る p.80) 天平宝字三年(七五九)九月壬午条(新羅遠征のための造船を山陽道等に命ずる p.80) 天平宝字三年(七五九)十二月丙甲条(備中国等の隠没田を勘検する p.80)) 古代編細目次 奈良時代 雑物請用帳(備中国貢納の■が一疋六三〇文で交易される p.81) 古代編細目次 奈良時代 続日本紀 ( 天平宝字四年(七六〇)正月丙寅条(下道朝臣黒麻呂の位階を進む p.82) 天平宝字四年(七六〇)正月癸未条(山陽道巡察使が任命された p.83) 天平宝字四年(七六〇)三月丁亥条(備中国等に賑給する p.83) 天平宝字四年(七六〇)八月辛未条(備中国等の■を小治田宮に転じて貯える p.83) 天平宝字四年(七六〇)十一月丙甲条(真備が大宰府で軍略を教授する p.84)) 古代編細目次 奈良時代 奉写一切経所解案(下道福足が校生として勤務し布施を受ける p.84) 古代編細目次 奈良時代 造法華寺金堂所解(造法華寺金堂所の財源に備中の長絹・調■あり p.86) 古代編細目次 奈良時代 (続日本紀 天平宝字六年(七六二)三月戊甲条(備中国等が旱する p.89) 続日本紀 天平宝字六年(七六二)四月庚戌条(下道朝臣黒麻呂が隠岐守となる p.89) 下智万呂啓(下道上万呂が案主として署する p.89)) 古代編細目次 奈良時代 続日本紀 ( 天平宝字七年(七六三)八月壬甲条(備中国等に賑給する p.90) 天平宝字七年(七六三)八月戊子条(山陽道等旱し節度使を停止する p.90)) 矢田部益足買地券文 天平宝字七年(七六三)十月十六日(郷長矢田部益足が白髪部■登富比売の買地券を立券する p.90) 古代編細目次 奈良時代 (造円堂所牒 天平宝字七年(七六三)十二月二十日(賀陽臣兄人が鼓吹大令史として造円堂所牒に署する p.92) 続日本紀 ( 天平宝字八年(七六四)正月己未条(真備が造東大寺長官となる p.92) 続日本紀 天平宝字八年(七六四)正月丙寅条(備中国等に賑給する p.93)) 古代編細目次 奈良時代 施薬院解 天平宝字八年(七六四)七月二十五日(蚊屋釆女の宣により施薬院に薬が送られた p.93) 古代編細目次 奈良時代 続日本紀 (天平宝字八年(七六四)八月甲戌条(山陽道等早疫する p.94) 天平宝字八年(七六四)九月乙巳条(真備が従三位となる p.95)) 古代編細目次 奈良時代 奉写御執経所牒 天平宝字八年(七六四)十月十七日(真備命婦の宣により四天王経十巻を請う p.95) 古代編細目次 奈良時代 続日本紀 ( 天平神護元年(七六五)正月己亥条(恵美押勝の乱後の備中国関係者の授位記事 p.96) 天平神護元年(七六五)三月癸巳条(備中国等の租税を免除する p.96) 天平神護元年(七六五)五月庚戌条(馬養造人上に印南野臣を賜姓する p.97) 天平神護元年(七六五)六月辛酉条(賀陽臣小玉女らに朝臣を賜姓する p.97) 天平神護二年(七六六)正月甲子条(真備を中納言とする p.97) 天平神護二年(七六六)三月丁卯条(真備を大納言とする p.98) 天平神護二年(七六六)五月戊午条(真備が訴訟につき新制を建議する p.98) 天平神護二年(七六六)五月癸亥条(下道臣色夫多に朝臣を賜姓する p.98) 天平神護二年(七六六)九月丙子条(山陽道巡察使に藤原雄田麻呂を任ずる p.98)) 古代編細目次 奈良時代 (成唯識宝生論巻第二奥書 天平神護二年(七六六)十月八日(吉備朝臣由利が一切経等を写経する p.99) 続日本紀 天平神護二年(七六六)十月壬寅条(真備を右大臣に任ずる p.99) 左方頭等解 天平神護二年(七六六)十二月十七日(下道蔭麿が左方頭等解に史生として署する p.99)) 古代編細目次 奈良時代 続日本紀 ( 神護景雲元年(七六七)五月癸酉条(下道朝臣色夫多が備後介となる p.100) 神護景雲元年(七六七)九月戊申条(真備が対馬の墾田等を献じて嶋■とする p.100) 神護景雲元年(七六七)十月壬戌条(吉備真備一族らの位階を進む p.101) 神護景雲二年(七六八)二月癸巳条(下道朝臣黒麻呂を越前介とする p.101) 神護景雲二年(七六八)三月乙巳条(山陽道巡察使が交通路の負担の軽減をはかる p.101) 神護景雲三年(七六九)二月癸亥条(真備に正二位を授ける p.101) 宝亀元年(七七〇)八月癸巳条(称徳天皇の崩御に際し真備ら光仁をたてる p.102) 宝亀元年(七七〇)八月丙午条(吉備朝臣由利が伝奏のことを専ら行う p.102) 宝亀元年(七七〇)十月丙申条(真備が致仕を乞い許されず p.103) 宝亀元年(七七〇)十月癸丑条(賀陽朝臣小玉女の位階を進む p.104) 宝亀三年(七七二)九月癸卯条(山陽道巡察使派遣する p.104) 宝亀五年(七七四)正月壬寅条(吉備朝臣由利が■ずる p.104) 宝亀六年(七七五)三月乙未条(備中国等の国司の員数を増す p.104) 宝亀六年(七七五)十月壬戌条(吉備真備の■伝 p.105) 宝亀七年(七七六)正月戊申条(山陽道検税使が任命された p.106)) 古代編細目次 奈良時代 (五百木部真勝解 宝亀七年(七七六)一月二一日(備中宮主の書き入れあり p.106) 矢田部首人足刻字■ 宝亀七年(七七六)(矢田部首人足刻字■ p.106)) 古代編細目次 奈良時代 続日本紀 ( 宝亀十年(七七九)二月甲申条(下道朝臣長人が遺新羅使となる p.107) 宝亀十年(七七九)七月丁丑条(下道朝臣長人が新羅より帰る p.107) 延暦三年(七八四)正月己卯条(下道朝臣長人が外従五位となる p.107) 延暦三年(七八四)三月乙酉条(下道朝臣長人が大和介となる p.107) 延暦三年(七八四)三月丙申条(吉備泉が父真備の功により罪を軽くされる p.108)) 古代編細目次 奈良時代 造東大寺司王義之書法返納注文案 延暦三年(七八四)三月二十九日(下道臣が造東大寺司返納注文案に署する p.108) 古代編細目次 奈良時代 東大寺使解 延暦六年(七八七)六月二十六日(賀陽釆女の宣により桂心若干を施薬院に給する p.109) 古代編細目次 奈良時代 続日本紀 ( 延暦九年(七九〇)四月乙丑条(備中国等に賜給する p.110) 延暦十年(七九一)四月丙寅条(真備らの作成した■定律令を整備し施行する p.111)) 古代編細目次 奈良時代 (太政官符類■三代格 延暦十一年(七九二)六月十四日(備中国に健児五十人を復活する p.111) 太政官符政事要略 延暦十四年(七九五)七月二十七日(備中国の提案により調物未進の弁済方法を改む p.113) 古代編細目次 平安時代 (日本紀略 延暦十五年(七九六)甲午条(吉備魚主に山陽道諸国の賊を捕えさす p.114) 日本後紀 ( 延暦十六年(七九七)二月乙丑条(賀陽豊年が文章博士と学士を兼ねる p.114) 日本後紀 延暦十八年(七九九)二月乙未条(備中国等に賜給する p.115) 日本後紀 延暦十八年(七九九)七月乙丑条(備中国の去年の租を免ずる p.115) 日本後紀 延暦二十四年(八〇五)十二月壬寅条(備中国等の庸を免ずる p.115) 日本後紀 大同元年(八〇六)四月乙巳条(下道朝臣継成の任官記事 p.115) 日本後紀 大同元年(八〇六)四月辛亥条(賀陽豊作が陰陽頭となる p.116)) 古代編細目次 平安時代 (日本逸史 大同元年(八〇六)五月丁亥条(山陽道観察使が任命された p.116) 大同元年牒 新抄格勅符 大同元年(八〇六)(備中国に神封や寺封が置かれていた p.116)) 古代編細目次 平安時代 太政官符 類■三代格 大同二年(八〇七)十月二十五日(備中国等の駅馬の数を減ずる p.117) 古代編細目次 平安時代 (日本後紀 ( 大同二年(八〇七)五月乙未条(賀陽豊年を兼下野守とする p.119) 日本後紀 大同二年(八〇七)五月庚子条(山陽道観察使が備中国等の負担体系変更を提案 p.119) 類■国司 大同四年(八〇九)六月丙申条(備中国等が大宰■の公■を負担する p.119)) 古代編細目次 平安時代 日本紀略 大同四年(八〇九)九月壬戌条(新たに山陽道観察使が任命された p.120) (日本後紀 弘仁元年(八一〇)九月癸丑条(賀陽豊年を播磨守とする p.120) 日本後紀 弘仁五年(八一四)閏七月壬午条(吉備泉の卒伝 p.120) 日本後紀 弘仁六年(八一五)六月丙寅条(賀陽朝臣豊年の卒伝 p.121)) 古代編細目次 平安時代 参考 新撰姓氏録(吉備一族の祖先伝承 p.122) 古代編細目次 平安時代 弘仁式 主税(備中国の正税公■等の数量を定める p.123) (続日本後紀 天長十年(八三三)三月己酉条(下道郡が主基国となる p.123) 続日本後紀 天長十年(八三三)十一月戊辰条(悠紀・主基殿に立てられた標の図柄の内容 p.124)) 古代編細目次 平安時代 続日本紀 ( 承和二年(八三五)五月癸酉条(備中国等の年料貢賊の練糸を生糸にかえる p.125) 承和三年(八三六)四月辛卯条(備中国に振給する p.125) 承和五年(八三八)二月戊戌条(山陽道諸国司等に海賊を捕えさす p.125) 承和七年(八四〇)六月庚申条(山陽道等の駅戸の田租を3年間免ずる p.125) 承和八年(八四一)八月戊午条(自国宛以外の駅伝符を開き見るを禁ずる p.126) 承和十四年(八四七)十月甲寅条(吉備津彦命神の神階を叙位する p.126) 承和十五年(八四八)二月辛亥条(吉備津彦命神の神階を進む p.126)) 古代編細目次 平安時代 太政官符 類■三代格 ( 嘉祥二年(八四九)九月三日(山陽道等の水夫の身役をとどめ米を出させる p.127) 嘉祥二年(八四九)十月一日(備中国の米百廿斛を京庫に進めさす p.127)) 古代編細目次 平安時代 日本文徳天皇実録 ( 仁寿二年(八五二)二月丁巳条(吉備津彦命神の神階を進む p.128) 仁寿二年(八五二)八月辛酉条(吉備津彦命神に神戸を封ずる p.128) 斉衡二年(八五五)二月癸亥条(吉備津神社の鈴鏡鳴る p.129) 斉衡二年(八五五)四月乙卯条(吉備津彦名神に奉幣する p.129) 天安元年(八五七)正月丁未条(賀陽朝臣姑子に叙位する p.129) 天安元年(八五七)六月戊辰条(吉備津彦命神の神階を進む p.129)) 古代編細目次 平安時代 日本三代実録 ( 貞観元年(八五九)十一月辛未条(賀陽朝臣姑子の位階を進む p.129) 貞観四年(八六二)三月壬申条(賀陽朝臣宗成らの本貫を左京に移す p.130) 貞観四年(八六二)五月丁亥条(備中国等の人夫を差発して海賊を追捕する p.130) 貞観五年(八六三)正月癸未条(滋善宿彌宗人の卒伝 p.130) 貞観六年(八六四)正月甲午条(賀陽朝臣宗成の位階を進む p.131) 貞観六年(八六四)二月壬戌条(宮原神の神階を進む p.131) 貞観六年(八六四)二月癸未条(賀陽朝臣宗成を安房守とする p.131) 貞観六年(八六四)十月戊辰条(宮原神の神階を進む p.132) 貞観七年(八六五)五月丙申条(賀陽朝臣宗成を備後介とする p.132) 貞観八年(八六六)五月壬戌条(備中国等の馬革・甲の修理数を減ずる p.132) 貞観九年(八六七)正月己酉条(賀陽朝臣乙三野に授位する p.132) 貞観九年(八六七)九月己亥条(長年銭を納官し進銭の人に稲を給する p.133) 貞観九年(八六七)十一月乙巳条(備中国等に徹底した海賊の取締りを命ずる p.133)) 古代編細目次 平安時代 太政官符 貞観交替式(備中国の年料春米の呼称法を変える p.134) 古代編細目次 平安時代 日本三代実録 ( 貞観十二年(八七〇)二月丁未条(備中国等に鋳銭のための銅を採らせる p.135) 貞観十六年(八七四)八月乙丑条(下道朝臣門継の卒伝 p.135) 貞観十八年(八七六)八月辛卯条(備中国に検非違使を置く p.135) 元慶元年(八七七)四月庚寅条(陽成天皇の大嘗会に都宇郡を主基とする p.135) 元慶元年(八七七)七月戊午条(都宇郡の年貢物を絹にあらためる p.136) 元慶元年(八七七)十一月丁巳条(主基国都宇郡風俗の歌舞を演じ衣被を献ずる p.136) 元慶元年(八七七)十一月戊午条(備中国司らの位階を進めて物を賜う p.136) 元慶元年(八七七)十一月壬戌条(主基国を努めた都宇郡の官人百姓らに賜禄する p.137) 元慶元年(八七七)十二月丁亥条(備中国等の庸米を免ずる p.137) 元慶二年(八七八)二月癸酉条(笠目神の神階を進む p.137) 元慶二年(八七八)四月辛卯条(備中国で白雀を獲る p.137) 元慶二年(八七八)五月甲辰条(備中国の柘弓百枝等の武器を採進させる p.138) 元慶三年(八七九)五月戊寅条(印南野臣宗雄らに同祖の故に笠朝臣を賜う p.138) 元慶五年(八八一)五月戊午条(山陽道等の諸国司に海賊の取締りを命ずる p.138) 元慶五年(八八一)十月辛卯条(窪屋郡人真髪部成道が殺人を犯して遠流となる p.139) 仁和二年(八八六)二月乙丑条(備中国採銅使に新印を賜う p.139) 仁和二年(八八六)二月丙寅条(備中国等に薦■を求めて野鳥を払い取る p.139)) 古代編細目次 平安時代 太政官符 類■三代格 寛平元年(八八九)十月二一日(採備備中国銅使の提案により勘会法を改正する p.139) 古代編細目次 平安時代 文朝文粋 巻第二 意見封事 意見十二箇条(三善清行が下道郡彌磨郷の推移を述べる p.140) 古代編細目次 平安時代 政事要略 巻七十 ■禅雑事十(巫覡による奇異のことに関し賀夜郡大領みゆ p.141) 古代編細目次 平安時代 扶桑要略 寛平八年(八九六)九月二十二日条(賀屋郡の富豪賀陽良藤が狐にばかされる p.142) 古代編細目次 平安時代 今昔物語集 巻十六 第十七話(賀陽良藤が狐を妻とし観音の功徳で助けられる p.144) 古代編細目次 平安時代 太政官符 類■三代格 ( 寛平九年(八九七)一月二十五日(備中国より定額の釆女一人を出す p.147) 寛平十年(八九八)二月二十七日(備中国司の解により前司任終年の雑米の返沙取扱いを改める p.148) 延喜二年(九〇二)三月十三日(備中国等に田租を■稲で徴することを禁ず p.147)) 古代編細目次 平安時代 藤原保則伝(藤原保則が備中・備前の国司として善政を行う p.150) 古代編細目次 平安時代 太政官符 別■符宣抄 延喜十年(九一〇)十二月二十七日(備中国等の春米を貢納額を増す p.152) 古代編細目次 平安時代 扶桑略記 延喜十四年(九一四)四月二十八日条(清行が下道郡彌磨郷の課丁の減少を論ずる p.153) 古代編細目次 平安時代 太政官符 別■符宣抄 延喜十四年(九一四)八月二十五日(備中国等の厨家への貢進物の品名・数量を定む p.154) 古代編細目次 平安時代 輔仁本革(備中国より産出する薬物をあげる p.156) 古代編細目次 平安時代 延喜交替式(備中国の春米運京の期限を八月三十日以前とす p.157) 延喜式 (巻十 神祗十 神名下(窪屋・賀夜・下道郡内の式内社 p.157) 巻十一 太政官(備中国司の赴任には海路で食を給された p.158) 巻十五 内蔵寮(備中国から内蔵寮へ■子・蜜などを貢進した p.159) 巻二十二 民部上(備中国の郡名と上国・中国の区分を記す p.159) 巻二十三 民部下(備中国等の鋳銭司に対する返抄の取扱い p.160 備中国の年料春米の種類と量を定める p.160 備中国等の年料租春米と取扱い法を定める p.160 備中国の年料別貢雑物として紙麻を定める p.161 備中国の貢進する蘇の量と年番を定める p.161 備中国の交易雑物の品名と量を定める p.162) 巻二十四 主計上(備中国の調糸の品質を定める p.162 備中国の貢進物の品名や京上の日数を定める p.163) 巻二十五 主計下(備中国等の採掘する銅■の文書の取扱を定める p.164) 巻二十六 主税上(備中国の正税等の数量・費用を定める p.164 備中国等の損田等の検使の日限を定める p.164 備中国等の採銅量及び取扱いなどを定める p.165 備中国等の禄物の価法を定める p.165 備中国等の駅馬の直法を定める p.166 備中国等の駅馬の死損分を定める p.166 備中国等の雑物を運漕する功賃を定める p.167) 巻二十八 兵部省(備中国等の健児の人数を定める p.168 備中国等の貢進すべき武器の種類等を定める p.168 備中国等の駅馬の数を駅毎に定める p.169) 巻三一 宮内省(備中国等の例貢の後■について定める p.170) 巻三十三 大膳下(備中国等貢進の菓子について定める p.170) 巻三十四 木工寮(備中国等の所進の雑物の品名・数量を定める p.171) 巻三十七 典薬寮(備中国の年料雑薬の貢進品目・数量を定める p.171) 巻三十九 内膳司(備中国の年料の■及び取扱いについて定める p.172)) 古代編細目次 平安時代 本朝世紀 ( 承平五年(九三五)六月辛卯条(山陽道等の海賊の追捕を諸社に祈願する p.173) 天慶二年(九三九)十二月丁巳条(備中国等に純友の追捕を命ずる p.174)) 古代編細目次 平安時代 日本紀略 天慶三年(九四〇)正月丁卯条(山陽道追捕使に小野好古を任ずる p.174) 古代編細目次 平安時代 (長寛勘文 天慶三年(九四〇)二月一日条(吉備津彦命等に神位記を授け海賊の追捕を祈る p.175) 貞信公記 天慶三年(九四〇)二月二十日条(備中軍が海賊に敗北し逃散する p.175) 吏部王記 天慶四年(九四一)六月十一日条(備中国等が海賊の動静を伝える p.175)) 古代編細目次 平安時代 (本朝世紀 (天慶四年(九四一)八月七日条(山陽道追捕使小野好古が凱旋する p.176) 本朝世紀 天慶四年(九四一)十月二十三日条(山陽道等の諸国の警固使等を停止する p.176) 吏部王記 天慶九年(九四六)五月十三日条(下道郡を主基とする p.176)) 古代編細目次 平安時代 (帝王編年記(村上天皇の名■会の主基とする p.177) 貞信公記 天暦二年(九四八)六月四日条(備中国等の隠納米を検出して施米等に充てる p.177)) 古代編細目次 平安時代 (太政官符 類■符宣抄 天暦三年(九四九)九月十一日(備中国より仕える中宮職の戸座を交替させる p.178) 西宮記 天暦五年(九五一)三月二十日条(備中国等の仁王会のための供米を定める p.178)) 古代編細目次 平安時代 扶桑略記 天徳四年(九六〇)九月二十八日条(造宮のあたり備中国等の四面廊を割当てる p.179) 古代編細目次 平安時代 清■王書状 康保三年(九七一)五月三日(多仁村の官米の運送に備中国の船人があたる p.180) 古代編細目次 平安時代 太政官符 符宣抄 天禄二年(九七一)七月十九日(備中国等に米などの進納を命ずる p.181) 古代編細目次 平安時代 日本紀略 ( 天延元年(九七三)五月三日条(備中国等を薬師寺造営にあてる p.182) 天元二年(九七九)四月二十一日条(備中国都宇郡に異物が降る p.182)) 古代編細目次 平安時代 (康頼本草(備中国より石■を産出する p.183) 衛門府月奏文 長保元年(九九九)四月一日(泰保平が前年の備中国大粮使となる p.183)) 古代編細目次 平安時代 (権記一 長保元年(九九九)十一月七日条(備中国等が貢納させられる p.185) 権記二 寛弘五年(一〇〇八)十一月十四日条(備中国の連年の減省につき論議する p.185)) 古代編細目次 平安時代 太政官符 類■符宣抄 長和二年(一〇一三)十二月七日(備中国より進める戸座を交替させる p.186) 古代編細目次 平安時代 (御堂関白記 長和五年(一〇一六)四月七日条(下道郡が後一条天皇の大■会の主基となる p.187) 扶桑略記 長和五年(一〇一六)十一月十五日条(下道郡が主基として大■会を供奉する p.187) 大■会悠紀主基詠歌 長和五年(一〇一六)条(大■会の詠歌で備中国の地名を詠みこむ p.187)) 古代編細目次 平安時代 左経記 寛仁元年(一〇一七)十月二日条(備中吉備津彦神社等の神宝を支配する p.192) 古代編細目次 平安時代 ■心院源信僧都行実(源信が備中の千体仏等を彫ると云う p.193) 古代編細目次 平安時代 小右記 (寛仁元年(一〇一七)十月六日条(石清水宮に備中の封戸を供料として献ずる p.194) 治安三年(一〇二三)五月二十日条(備中国等の山階寺の庄園が收公される p.195) 万寿二年(一〇二五)七月二十二日条(藤原実資のもとに備中の相撲人が参来する p.195)) 古代編細目次 平安時代 左経記 ( 万寿三年(一〇二六)十一月四日条(備中国等の不堪文を奏す p.196) 長元七年(一〇三四)八月十九日条(備中国が美福門の造営を神嘉殿西廊に改めらる p.196)) 古代編細目次 平安時代 (小野宮年中行事 永承元年(一〇四六)二月条(備中国が春季仁王会の料米を負担する p.197) 新猿薬記 四郎君条(四郎君の貯える諸国の名産物に備中刀をあげる p.197)) 古代編細目次 平安時代 (百錬抄 康平四年(一〇六一)十一月二十五日条(吉備津彦が焼亡する p.198) 百錬抄 康平五年(一〇六二)二月十二日条(吉備津宮焼亡の事等を定申する p.198) 厳島神主佐伯景弘解 康平七年(一〇六四)十二月二十一日(備中国司藤原定綱が吉備津宮を造営する p.198)) 古代編細目次 平安時代 蔵人所牒 朝野郡載 治暦元年(一〇六五)九月一日(備中国等に紙墨の進上を命ずる p.199) 古代編細目次 平安時代 土右記 治暦五年(一〇六九)五月二十日条(吉備津宮が覆勘文を進める p.200) 土右記 治暦五年(一〇六九)六月十三日条(吉備津宮が覆勘文を進める p.200) 備中国吉備津社氏人解 延久二年(一〇七〇)十月二十八日(吉備津彦社の氏人らが神主代官の補任を請う p.200)) 古代編細目次 平安時代 神■官解 延久二年(一〇七〇)十一月七日(神■官が賀陽致貞を神主代官に補任する p.201) 古代編細目次 平安時代 成尋阿■梨母集 延久三年・四年(一〇七一・七二)(成尋阿■梨が備中新山別所で修行する p.203) 古代編細目次 平安時代 官宣是 朝野郡載 応徳二年(一〇八五)九月十五日(入道性信親王が備中国の封戸等を喜多院に付す p.205) 古代編細目次 平安時代 太皇大后宮職解 朝野郡載 応徳二年(一〇八五)十月三十日(藤原伊房が備中国等の私稲を法定院に付す p.206) 古代編細目次 平安時代 為房■記 寛治元年(一〇八七)四月二十三日条(備中国賀陽郡を堀河天皇の大■会の主基とする p.207) 古代編細目次 平安時代 元亨釈書 巻第十七(吉備津宮の神官藤井久任が出家して焼身往正す p.209) 古代編細目次 平安時代 拾遺往生伝(藤井久任の往生奇談 p.210) 古代編細目次 平安時代 賀茂社古代庄園御厨(賀茂社領に富田庄あり p.211) 古代編細目次 平安時代 中右記 (永長二年(一〇九七)二月十日条(備中国等に行幸のための作道の公事が割当てられる p.212) 長治元年(一一〇四)十一月十日条(藤原宗忠が備中等の封戸を春日社に奇進する p.213) 古代編細目次 平安時代 着駄勘文 永久三年(一一一五)十二月二十日(備中国人、内藤安行が官物を詐取し徒刑となる p.213) 古代編細目次 平安時代 (帝王編年記 保安四年(一一二三)十一月十八日条(下道郡が大■会の主基となる p.215) 後拾遺往生伝(備中出身の黒谷上人善意の往生伝 p.215)) 古代編細目次 平安時代 東大寺印蔵文書目録 久安三年(一一四七)四月十七日(備中国等の東大寺領荘園の印蔵文書を注進する p.216) 古代編細目次 平安時代 台記 久安五年(一一四九)九月二十五日条(備中国等に諸物の貢進を課す p.217) 古代編細目次 平安時代 今昔物語集 (巻十七 第四話(地蔵菩薩を念じて主人に殺されるを免れる p.218) 巻十七 第十八話(僧阿清が地蔵菩薩の助けにより蘇生する p.221)) 古代編細目次 平安時代 本朝世紀 久安七年(一一五一)一月二十六日条(備中国とうが貢納物の減免を認められる p.223) 古代編細目次 平安時代 兵範記 (保元二年(一一五七)三月二十六日条(備中国に後涼殿の造営を課せられる p.224) 保元二年(一一五七)七月十五日条(備中国等の紙などを法成寺に付与する p.224) 保元三年(一一五八)六月二十七日条(備中国の相撲人が参河国に勝つ p.223) 保元三年(一一五八)十一月二十六日条(備中国の所領相続争いについて審議する p.226)) 古代編細目次 平安時代 安楽寿院領等荘園目録案(備中国駅口庄は安楽寿院の所領 p.226) 古代編細目次 平安時代 神■官諸社年貢注文 永万元年(一一六五)六月(神■官が諸社へ年貢を注文する p.228) 古代編細目次 平安時代 兵範記 (仁安三年(一一六八)四月二十八日条(備中国賀夜郡が高倉天皇の大■会の主基となる p.229) 仁安三年(一一六八)十月二十三日条(大■会のための備中抜穂使が国を出立する p.229)) 古代編細目次 平安時代 (帝王編年記 嘉応元年(一一六九)十一月二十二日条(大■会が挙行される p.230) 兵範記 嘉応元年(一一六九)十二月二十四日条(藤原成親が備中国に配流される p.230 藤原成親が備中国に配流される p.231)) 古代編細目次 平安時代 百錬抄 嘉応元年(一一六九)十二月二十八日条(成親を召還し本官に選任する p.231) 古代編細目次 平安時代 (生石荘田堵賀陽清仲解 嘉応二年(一一七〇)八月九日条(生石庄の田堵賀陽清仲が足守庄の田畠を耕作す p.232) 官宣是 承安元年(一一七一)十二月十二日条(備中国田上本庄等を宝塔院に奇進する p.232)) 古代編細目次 平安時代 主殿寮年預伴守方問注記 承安二年(一一七二)九月(備中の納油について主殿寮年預らが陳状する p.234) 古代編細目次 平安時代 土佐国雑掌紀頼兼主殿寮沙汰人伴守方問注記(備中の油等について土佐国雑掌らが陳状する p.236) 古代編細目次 平安時代 八条院領目録 安元二年(一一七六)二月(八条院領目録に生石庄あり p.241) 古代編細目次 平安時代 平家物語 巻二 大納言死去章(藤原成親が備中国庭瀬郷にて横死する p.242) 古代編細目次 平安時代 (壬生家譜 治承四年(一一八〇)六月九日条(小規国宗が備中山手保を建立開墾する p.243) 吉記一 治承五年(一一八一)六月十五日条(備中国等が興福寺金堂造営を負担する p.243)) 古代編細目次 平安時代 後白河院院庁下文案 養和元年(一一八一)十二月二日(備中国上田本庄等の乱防を停止する p.244) 古代編細目次 平安時代 玉葉 (寿永二年(一一八三)十月十七日条(備中国人らが木曽義仲の軍勢と戦う p.246) 寿永二年(一一八三)閏十月十四日条(木曽義仲が備中に赴くとの風聞あり p.247)) 古代編細目次 平安時代 平家物語 巻八 妹尾最期章(備中の平家方の妹尾兼康の最期 p.247) 古代編細目次 平安時代 (吾妻鏡 元暦元年(一一八四)二月十八日条(梶原景時・土肥実平が備中国等を守護する p.253)吾妻鏡 元暦元年(一一八四)三月二十四日条(土肥実平が備中国の所務を行う p.253) 梶原景時書状(梶原景時が文覚に足守郷の知行を保障する p.253) 僧文覚起請文 元暦二年(一一八五)一月十九日(文覚が足守庄等の由来を明らかにする p.254)) 古代編細目次 平安時代 吾妻鏡 (文治元年(一一八五)四月二十九日条(頼朝が妹尾郷を崇徳院法華堂に奇進する p.256) 文治元年(一一八五)六月二日条(能円らを備中国等に配流する p.257) 文治二年(一一八六)六月二十一日条(備中の守護地頭等にも横暴停止を求められる p.257)) 古代編細目次 平安時代 (後白河法皇院宣 文治四年(一一八八)七月二十四日(葦守庄等の役夫工を免ずる p.259) 石清水八幡宮記録 文治四年(一一八八)十月二十日条(水内庄が石清水八幡宮寺領となる p.260) 主殿寮年預伴守方解状 建久元年(一一九〇)四月二十六日(備中国が主殿寮に油・米等を弁進する p.261) 後白河院庁下文案 建久元年(一一九〇)十二月(備中国田上本庄等での乱妨を禁ずる p.262) 成勝寺年中相折帳(成帳寺年中相折帳に備中国からの納物あり p.263) 徳島県雲辺寺千手観音像銘(備中の仏師経尋が観音像をつくる p.265)) 中世編Ⅰ編年史料細目次 鎌倉時代 (南無阿弥陀仏作善集(重源が備中別所の浄土堂を修復し丈六弥陀像一体を安置する p.269) 明月記 建保元年(一二一三)十二月二十四日条(備中国府に宇佐使が到着して七日間滞在する p.271) 後鳥羽院■記 建保二年(一二一四)四月三日条(前右大臣藤原忠経が備中国衛領三ケ所を給わる p.271) 後高倉上皇院宣 承久四年(一二二二)二月十日(葦守庄が神護守に返付される p.272) 承久三年四年日次記 貞応元年(一二二二)四月十六日条(下道郡が大■会の主基国となる p.272) 帝王編年記 貞応元年(一二二二)十一月二十三日条(下道郡が大■会の主基国となる p.273) 関東挙状案 寛喜元年(一二二九)十二月十七日(幕府が■領家職を惟明親王妃に与える p.273) 関東請文 寛喜二年(一二三〇)三月三日(■庄は寛喜年間には金剛勝院領であった p.274) 百錬抄 (仁治三年(一二四二)四月二十六日条(下道郡が大■会の主基国となる p.274)仁治三年(一二四二)九月十七日条(備中国へ大■会の主基使が下向する p.275)) 俊増書状 文永元年(一二六四)八月六日(二万郷内にあった神領畠の作毛を円光法師等が刈取る p.275) 小槻有家請文案 六月六日(小槻有家が山手保等を官務に付けることを承諾する p.275) 小槻有家奏聞状案 文永六年(一二六九)四月二十一日(小槻有家が山手保の返還を要求する p.277)(山手保について小槻有家がかさねて奏聞する p.278) 備中国宣 建治2年(一二七六)十二月四日(備中守護代時綱の守重名内での濫妨を停止する p.282) 左衛門尉公成奉書 建治二年(一二七六)十二月六日(僧弁尊に守重名内の田畠を領知させる p.282) 平等院所司申状 弘安二年(一二七九)十一月三日(橋本庄の庄官が年貢・公事等を未進する p.283) 一遍聖絵 弘安十年(一二八七)条(軽部宿で一遍上人が教願の往生をみとどける p.284) 続史愚抄 正応元年(一二八八)十一月二十二日条(備中国司が大■祭で標山を曵く p.285) 善法寺尚清処分状写 応長元年(一三一一)十二月十五日(善法寺尚清が水内庄を同寺権別当康清に譲る p.286) 続史愚抄 文保二年(一三一八)四月二十三日条(備中国が大■会の主基国となる p.289)) 中世編Ⅰ編年史料細目次 南北朝・室町・安土桃山時代 (足利尊氏書下案 建武三年(一三三六)五月二十五日(足利尊氏が備中福山等の敵勢を没落させる p.290) 続史愚抄 暦応元年(一三三八)四月二十八日条(備中国が大■会の主基国となる p.291) 備中国司橘知任安堵状 暦応二年(一三三九)一月十日(橘知任が東福寺に上原郷領家職を安堵する p.291) 一宮社法 康永元年(一三四二)六月二十八日(阿曽のかな屋村から備前一宮へ初穂を奉納する p.292)) 中世編Ⅰ編年史料細目次 南北朝・室町・安土桃山時代 (花園法皇院宣 貞和元年(一三四五)十二月三日(花園法皇が山城長福寺に薗東庄を奇進する p.293) 東福寺諸荘園目録 貞和三年(一三四七)七月(住山が東福寺の諸荘園文書目録を作成する p.294) 玉燭宝典裏書(二階堂行秀が備中国真壁郷を幕府に請う p.296) 光厳上皇院宣 貞和四年(一三四八)八月十一日(光厳上皇が長福寺の薗東庄寄附を承認する p.297) 後村上天皇論是写 九月二十日(後村上天皇が水内北庄公文に年貢納入を命じる p.297)) 中世編Ⅰ編年史料細目次 南北朝・室町・安土桃山時代 (某施行状案 文和元年(一三五二)十月七日(幕府が河辺郷内一分地頭職を雅楽以秀に交付す p.299) 後光厳天皇論旨 延文元年(一三五六)六月十六日(後光厳天皇が長福寺に薗東庄などを安堵する p.299) 後光厳天皇論旨 延文元年(一三五六)十一月三十日(後光厳天皇が上原郷での国衛違乱を停止する p.300)) 中世編Ⅰ編年史料細目次 南北朝・室町・安土桃山時代 後村上天皇論旨写 正平十七年(一三六二)十一月二十二日(後村上天皇が水内北荘での其の濫妨を停止する p.300) 中世編Ⅰ編年史料細目次 南北朝・室町・安土桃山時代 (左近将監某施行状写 貞治三年(一三六四)十月十四日(幕府が弘石資政の水内北庄での濫妨を停止する p.301) 左近将監某施行状 貞治四年(一三六五)九月八日(再び弘石資政の水内北庄での濫妨を停止する p.301)) 中世編Ⅰ編年史料細目次 南北朝・室町・安土桃山時代 (道ゆきふり 応安四年(一三七一)(今川貞世が軽部川を超えて西下する p.302) 室町将軍家奉行人施工状 応安六年(一三七三)十二月十四日(重ねて弘石らの水内北庄での濫妨を停止する p.303) 室町将軍家奉行人施工状写 応安七年(一三七四)十二月二十四日(重ねて弘石らの水内北庄での押妨を停止する p.303) 室町将軍家奉行人施工状 応安七年(一三七四)十二月二十四日 p.304 室町将軍家奉行人施工状 応安八年(一三七五)二月九日(幕府が水内北庄を石清水八幡宮雑掌に交付する p.304)) 中世編Ⅰ編年史料細目次 南北朝・室町・安土桃山時代 (後円融上皇院宣 永徳二年(一三八二)六月二十四日(後円融上皇が原上郷を東福寺の寄進する p.305) 常在光寺目安案 永徳三年(一三八三)五月(常在光寺が備中国上庄東方地頭職等を請う p.305) 後小松天皇宣旨 永徳三年(一三八三)六月二十五日(後小松天皇が田上庄東方等の太神宮役夫工米以下諸役を免除す p.306)) 中世編Ⅰ編年史料細目次 南北朝・室町・安土桃山時代 (管領斯波義将奉書 応永二年(一三九五)十二月七日(幕府が再び河西某の薗東庄領家職を停止する p.307) 下原六地蔵・不動磨崖仏刻銘 応永五年(一三九九)八月(道清が大願主となり下原の磨崖仏を彫る p.308) 某奉書 応永六年(一三九九)七月二十三日(薗東庄を長福寺主に与える p.308) 教言■記 応永十二年(一四〇五)十二月十五日条(備中守護細川満之が死亡する p.309) ■日山宗派図(宝福寺住持秀厳九■が入寂する p.310) 続史愚抄 応永二十二年(一四一五)四月二十八日条(下道郡が大■会の主基国となる p.313) 大■会仮名記 応永二十二年(一四一五)四月条(下道郡が大■会の主基国となる p.313) 続史愚抄 応永二十二年(一四一五)十一月二十一日条(備中国司が大■祭で標山を曵く p.314)) 中世編Ⅰ編年史料細目次 南北朝・室町・安土桃山時代 (蔭凉軒目録 永享七年(一四三五)七月十九日条(宗育が宝福寺首座となる p.314) 東福寺領備中上原郷年貢算用状案 永享十一年(一四三九)二月(上原郷給主性現が年貢算用状を作成する p.315) 蔭凉軒日禄 永享十一年(一四三九)六月二十日条(元璋が宝福寺首座となる p.318)) 中世編Ⅰ編年史料細目次 南北朝・室町・安土桃山時代 細川勝元施行状 嘉吉元年(一四四一)三月十二日(幕府が上原郷領家職段銭人夫等を免除する p.318) 中世編Ⅰ編年史料細目次 南北朝・室町・安土桃山時代 徳阿弥請文 嘉吉元年(一四四一)十月十三日(水内庄代官徳阿弥が石清水八幡宮に請文を出す p.319) 中世編Ⅰ編年史料細目次 南北朝・室町・安土桃山時代 室町将軍家御教書 文安四年(一四四七)九月十六日(幕府が水内庄を善法寺法印権大僧都に与える p.319) 中世編Ⅰ編年史料細目次 南北朝・室町・安土桃山時代 岩屋寺常行堂古瓦銘 享徳三年(一四五四)二月十五日(岩屋寺常行堂の屋根を葺替える p.320) 中世編Ⅰ編年史料細目次 南北朝・室町・安土桃山時代 (細川勝元施行状 長禄三年(一四五九)十一月十日(細川勝元が細川氏久に命じて水内庄を善法寺阿子々丸代に沙汰させる p.320) 細川氏久■写状 長禄三年(一四五九)十二月二十日(細川氏久が石川源三等に命じて水内庄の年貢を善法寺阿子々丸代に渡さす p.321) 高橋光秀請文 長禄三年(一四五九)十二月二十六日(高橋光秀が水内庄処務職を請負う p.321) 蔭凉軒日禄 (長禄四年(一四六〇)九月二十二日(宗兌が宝福寺首座となる p.322) 寛正三年(一四六二)二月九日条(幕府が祖国寺領庄園に陣夫を課すのを停止する p.323)) 中世編Ⅰ編年史料細目次 南北朝・室町・安土桃山時代 (室町将軍家御教書写 寛正四年(一四六三)七月十日条(幕府が石清水八幡宮の水内北庄知行を承認する p.323) 蔭凉軒日禄 寛正五年(一四六四)三月十七日条(恵雄が宝福寺首座となる p.323)) 中世編Ⅰ編年史料細目次 南北朝・室町・安土桃山時代 (続史愚抄 文正元年(一四六六)四月二十二日条(下道郡が大■会の主基国となる p.324) 蔭凉軒日録 文正元年(一四六六)四月二十三日条(下道郡が大■会の御供を献上する p.324)) 中世編Ⅰ編年史料細目次 南北朝・室町・安土桃山時代 (足利将軍義政過書 応仁二年(一四六八)二月十五日(細川勝元の被官五人が備中へ下向する p.324) 備前国熊山霊仙寺梵鐘銘 応仁二年(一四六八)十一月十五日(大工左衛門尉が備前国熊山霊仙寺の梵鐘を鋳る p.325)) 中世編Ⅰ編年史料細目次 南北朝・室町・安土桃山時代 (高橋光秀請文 文明三年(一四七一)十一月十五日(高橋光秀が水内庄の代官職を請負う p.326) 足利義政御内書案 文明四年(一四七二)七月二十八日(将軍足利義政が備中国へ階銭を課す p.326) 道岡経房請文 文明五年(一四七三)三月十四日(道岡経房が水内庄の代官職を請負う p.327) 室町幕府奉行人下知状 文明五年(一四七三)八月十六日(幕府が善法寺享清に■代郷を知行させる p.326) 大乗院寺社雑事記 文明九年(一四七七)九月七日条(薬師寺与一が領知知行のため備中へ赴く p.328) 足利義政安堵状 文明十年(一四七八)四月三日(足利義政が山城長福寺に薗東庄等を安堵する p.328) 穴観音種子十三仏刻銘 文明十一年(一四七九)(周歓が穴観音種子十三仏を彫る p.329) 新見荘代官山田具忠書状 文明十四年(一四八二)八月十三日(上原庄・日羽郷等の庄主が討たれる p.330) 蔭凉軒日録 文明十七年(一四八五)九月十三日条(上原庄・日羽郷等の庄主が討たれる p.331 常在光寺が備中守護の奉書横領を訴える p.332) 蔭凉軒日録 文明十七年(一四八五)九月十三日条(常在光寺が備中守護の奉書横領を訴える p.332) 文明十七年(一四八五)十一月十三日条(等收西堂が備中宝福寺に入る p.332) 蔭凉軒日録 文明十七年(一四八五)十一月十七日条(桂室和尚が阿宗郷地頭職を周茂■食に与える p.333) 蔭凉軒日録 文明十七年(一四八五)十一月二十四日条(東稔首座が宝福寺住持となる p.333) 蔭凉軒日録 文明十八年(一四八六)五月九日条(石河左京進が河辺郷代官職を競望する p.334) 蔭凉軒日録 文明十八年(一四八六)五月十三日条(幕府が石河左京進の河辺郷代官職競望を退ける p.334)) 中世編Ⅰ編年史料細目次 南北朝・室町・安土桃山時代 鹿苑日録 長享元年(一四八七)■十一月五日条(日羽庄主が引合紙一束を鹿苑院へ送る p.335) 鹿苑日録 長享二年(一四八八)二月十三日条(備中守護細川氏久が日羽庄の兵糧米免除を謝す p.335) 蔭凉軒日録 長享二年(一四八八)七月一日条(常在光寺が寺領並びに衆僧数等を書立て蔭凉軒 p.336) 蔭凉軒日録 長享二年(一四八八)七月五日条(常在光寺領所々土貢目録 p.337) 蔭凉軒日録 延徳二年(一四九〇)八月六日条(石河右京進が討死する p.338)) 中世編Ⅰ編年史料細目次 南北朝・室町・安土桃山時代 東福寺領諸荘園目録 延徳二年(一四九〇)九月三日(東徳寺領諸荘園目録 p.339) 中世編Ⅰ編年史料細目次 南北朝・室町・安土桃山時代 蔭凉軒日録 (延徳三年(一四九一)十一月二日条(庄伊豆守が守護方と備中取合いの合戦を起こす p.340) 延徳三年(一四九一)十一月十日条(管領細川政元等が備中へ進発のための暇を請う p.341) 延徳三年(一四九一)十二月二日条(細川勝久が庄伊豆守退治のため備中進発する p.341) 延徳四年(一四九二)二月二十四日条(備中で合戦が起こる p.341) 延徳四年(一四九二)三月十一日条(宝篋院が細川政元の使節として備中備後へ下る p.343) 延徳四年(一四九二)三月十六日条(泰甫和尚が細川政元の使節として備中へ下る p.342) 延徳四年(一四九二)四月六日条(庄伊豆守が細川勝久に敗れて没落する p.342) 延徳四年(一四九二)四月七日条(香西五郎左衛門が敵三人を討ち切腹する p.343) 延徳四年(一四九二)五月五日条(蔭凉軒主が備中守護細川勝久等に書状を送る p.343) 明応二年(一四九三)六月十八日条(羽田源左衛門が備中国衛領は一万六千貫の在所と語る p.343)) 中世編Ⅰ編年史料細目次 南北朝・室町・安土桃山時代 広幸書状写 文亀元年(一五〇一)十二月十日(広幸が杉三郎兵衛尉と水内庄本主方の年貢を契約する p.344) 中世編Ⅰ編年史料細目次 南北朝・室町・安土桃山時代 (華光英厳希雄禅師法嗣守腋禅師略伝 永正十一年(一五一四)十一月二日(守腋禅師が華光寺で死亡した p.345) 高橋光資書状写 永正十四年(一五一七)十二月七日(高橋光資が水内庄半済方の年貢未進に事情等を伝える p.345) 高橋光実書状 十二月二日(高橋光実が水内庄本主半済方の年貢を進納する p.346)) 中世編Ⅰ編年史料細目次 南北朝・室町・安土桃山時代 (三田光宝請文 大永二年(一五二二)六月二十八日(三田光宝が水内庄代官職を請負う p.348) 甲清譲状 天文二十一年(一五五二)九月(駿河小路甲清が清満丸に水内庄等を譲る p.349) 三田家実書状 永禄九年(一五六六)三月十日(三田家実が水内庄の年貢五貫文を進納する p.349) 上田家親書状 元亀三年(一五七二)六月二十八日(上田実親が水内庄の年貢進納を約束する p.350)) 中世編Ⅰ編年史料細目次 南北朝・室町・安土桃山時代 (小早川隆景誓紙 天正二年(一五七四)■十一月一日(小早川隆景が清水宗治等に誓紙を与える p.351) 坪付■年貢注文断簡 天正四年(一五七六)十二月(福武佐渡守が三須郷の坪付並びに年貢注文を書き立てる p.352) 八田部郷之内6貫文之地田畠坪付 天正五年(一五七七)五月二十二日(桂景信等が国貞景氏に八田部郷の内6貫文の地を与える p.355) 清水宗治書状 十一月十一日(清水宗治が笠岡へ下ることを伝える p.357) 木下祐久書状 天正十一年(一五八三)五月八日(木下祐久が小早川隆重に高松講和の実行を促す p.359) 小早川隆景書状 天正十一年(一五八三)十月二十五日(境界決定のため蜂須賀正勝等が下向する p.360) 羽柴秀吉書状 天正十一年(一五八三)十二月二三日(羽柴秀吉が高山城等を請取るよう命ずる p.360) 羽柴秀吉書状 天正十二年(一五八四)一月二日(羽柴秀吉が虎倉城等の請取りにつき指示する p.361) 羽柴秀吉書状 天正十二年(一五八四)一月五日(羽柴秀吉が境目の城の請取りを督促する p.363) 安国寺恵■書状 天正十二年(一五八四)一月十一日(安国寺恵■が毛利輝元の決断を促すよう伝える p.364) 鵜飼元辰書状 天正十二年(一五八四)四月一日(鵜飼元辰が中島元行へ備中の情勢を伝える p.368)) 中世編Ⅱ家わけ史料細目次 九条家文書(上原郷関係) 関東下知状案 貞応二年(一二二三)六月三十日(御家人が吉備津宮放生会大頭役等を努める p.373) 中世編Ⅱ家わけ史料細目次 九条家文書(上原郷関係) 関東下知状 永仁七年(一二九九)四月六日(上原郷が東福寺領となる p.374) 中世編Ⅱ家わけ史料細目次 九条家文書(上原郷関係) 六波羅下知状案 正安元年(一二九九)十二月二十三日(上原郷の検注につき地頭代と雑掌が対立する p.374) 中世編Ⅱ家わけ史料細目次 九条家文書(上原郷関係) 東福寺住持山■恵雲■宗像長氏往返状 正安元年(一二九九)十二月二十七日(東福寺住持が上原郷に関し保証を求める p.376) 中世編Ⅱ家わけ史料細目次 九条家文書(上原郷関係) (六波羅下知状 正和二年(一三一三)七月二十七日(上原郷の地頭代を国衛在庁官人が襲う p.377) 上原郷国方年貢請取状 正和五年(一三一六)十二月二十九日(上原郷の年貢を国衛にも納入する p.379)) 中世編Ⅱ家わけ史料細目次 九条家文書(上原郷関係) 上原郷領家方年貢皆済状 元弘三年(一三三三)九月四日(貞弘が上原郷の領家方への年貢を皆済する p.379) 中世編Ⅱ家わけ史料細目次 九条家文書(上原郷関係) (備中国留守所下文案 建武三年(一三三六)四月十二日(備中国衛が散位家長を原郷上下郷司職に任命す p.380) 上原郷所務代官家長書状 四月十九日(散位家長が補任状案を示し近日の入部を報ずる p.380) 光厳院々宣 建武三年(一三三六)十月二十六日(光厳院が上原郷領家職を東福寺に寄進する p.381) 吉備津宮雑掌覚■申状案 建武五年(一三三八)八月(上原郷が吉備津宮放生会大頭役を務める p.381) 佐兵衛尉時基請文 建武五年(一三三八)八月二十九日(佐兵衛尉時基が吉備津宮神役の勤仕を約束する p.382)) 中世編Ⅱ家わけ史料細目次 九条家文書(上原郷関係) (光厳院々宣 暦応二年(一三三九)十二月二十八日(光厳院が上原郷領家職を安堵する p.383) 足利直義安堵状案 暦応四年(一三四一)■四月十三日(足利直義が東福寺へ上原郷を安堵する p.384) 領家方請取状包紙 暦応四年(一三四一)十二月二十七日(領家方請取状包紙 p.384) 中御門経季奉書 泰永三年(一三四四)二月二十八日(上原郷が東福寺請所と認められる p.384)) 中世編Ⅱ家わけ史料細目次 九条家文書(上原郷関係) (源公俊打渡状 観応三年(一三五二)八月二十三日(源公俊が上原郷領家職下地を寺家雑掌に与える p.385) 大蔵丞朝泰打渡状 観応三年(一三五二)八月二十三日(上原郷領家職下地が寺家雑掌に与えられる p.385)) 中世編Ⅱ家わけ史料細目次 九条家文書(上原郷関係) (後光厳天皇綸旨案 文和二年(一三五三)九月十二日(天皇が上原郷の知行を万里小路仲房に命じる p.386) 室町将軍足利尊氏御教書 文和二年(一三五三)十二月二十八日(吉備津宮神人等の上原郷での濫妨を止めさせる p.386) 足利尊氏御判御教書案 文和四年(一三五五)八月二十八日(尊氏が原上郷を万里小路家雑掌に還付させる p.387) 左衛門尉頼秀打渡状案 文和四年(一三五五)九月八日(頼秀が原上郷を万里小路家雑掌に与える p.387) 室町幕府引付頭人奉書 延文二年(一三五七)七月五日(佐々木高氏が美作彦四郎の押領を止めさせる p.387)) 中世編Ⅱ家わけ史料細目次 九条家文書(上原郷関係) (室町幕府引付衆奉書 貞治三年(一三六四)六月十一日(佐々木高氏が野山周防入道の押領を止めさせる p.388) 東福寺雑掌真賀申状案 貞治三年(一三六四)六月(真賀が上原郷での野山周防入道の押妨を訴える p.389) 室町将軍足利義満御教書案 応安六年(一三七三)十二月十四日(足利義満が石原新兵衛尉等の押妨を止めさせる p.390)) 中世編Ⅱ家わけ史料細目次 九条家文書(上原郷関係) (万里小路家雑掌重安申状案 永和三年(一三七七)八月(万里小路家雑掌重安が石原等の押妨を訴える p.390) 室町将軍足利義満御教書 (永和四年(一三七八)六月十五日(足利義満が上原郷下地を寺家雑掌に与える p.391) 室町将軍足利義満御教書 永和四年(一三七八)六月二十日(足利義満が重ねて石原等の押妨を止めさせる p.392) 備中国守護渋川志奉行人連署奉書 (永和四年(一三七八)十月十七日(渋川満頼が上原郷を万里小路家に与えさせる p.392) 備中国守護渋川志奉行人連署奉書 永和四年(一三七八)十二月三日(渋川満頼が上原郷を東福寺雑掌に与えさせる p.393) 備中国守護代打渡状 永和四年(一三七八)十二月十八日(吉見弾正少■が上原郷を寺家雑掌に与える p.393) 備中国守護代打渡状 泰暦元年(一三七九)五月三日(上原郷地頭職・領家職を寺家雑掌に与える p.394)) 中世編Ⅱ家わけ史料細目次 九条家文書(上原郷関係) (上原郷領家半済分守護方請取状 泰暦元年(一三七九)六月十一日(守護方が上原郷領家方の半済分を請け取る p.395) 上原郷領家年貢請取状 泰暦元年(一三七九)六月二十三日(守護方が東福寺へ上原郷の年貢を納入する p.396) 上原郷領家半済職打渡状 泰暦元年(一三七九)八月二十四日(上原郷領家半済職を東福寺雑掌に与える p.396) 渋川満頼請文 泰暦二年(一三八〇)一月二十三日(渋川満頼が上原郷のことにつき請文を出す p.397) 沙弥昌秀等借状 泰暦二年(一三八〇)四月二十四日(石川昌秀が十貫文を借り請ける p.397) 上原郷領家方半済請料請取状 泰暦二年(一三八〇)十二月二十七日(東福寺が守護方へ上原郷半済分を納める p.398)) 中世編Ⅱ家わけ史料細目次 九条家文書(上原郷関係) (万里小路家雑掌請取状 永徳二年(一三八二)七月十日(万里小路家が領家職を東福寺に寄進する p.398) 室町将軍足利義満御教書案 至徳二年(一三八五)七月二十五日(足利義満が真壁氏等をして半済停止を命ずる p.399) 守護方両使上原郷打渡状 至徳二年(一三八五)十月十一日(守護方が真壁氏等に上原郷の打渡状を差出す p.399) 真壁景康打渡状 至徳二年(一三八五)十月二十一日(真壁氏が上原郷半済職を東福寺雑掌に与える p.400)) 中世編Ⅱ家わけ史料細目次 九条家文書(上原郷関係) 太政官牒写 嘉慶二年(一三八八)五月二十五日(北朝が上原郷の伊勢神宮役工米等を免除する p.401) 官宣旨写 嘉慶二年(一三八八)五月二十五日(北朝が上原郷の伊勢神宮役夫工米等を免除する p.402) 官宣旨写 嘉慶二年(一三八八)五月二十五日(北朝が上原郷の伊勢神宮役夫工米を免除する p.403) 室町将軍足利義満御教書案 嘉慶三年(一三八九)二月七日(足利義満が上原郷役夫工米等の催促を停止する p.404)) 中世編Ⅱ家わけ史料細目次 九条家文書(上原郷関係) 備中国守護渋川満頼■行状案 康応元年(一三八九)四月二十七日(備中守護渋川満頼が義満の御教書を遵行する p.405) 中世編Ⅱ家わけ史料細目次 九条家文書(上原郷関係) (上原郷未進徴符案 明徳三年(一三九二)十二月二十一日(上原郷が夏銭を未納する p.405 上原郷が地頭麦・半済麦を未納する p.408) 備中国守護遵行状 明徳三年(一三九二)十二月二十三日(渋川満頼が上原郷半済分を東福寺雑掌に付する p.409) 沙弥明照書状案 十二月二十三日(香厳院追善として上原郷半済分を東福寺に寄進する p.410) 渋川満頼書状 明徳四年(一三九三)二月十五日(渋川満頼が上原郷半済職を東福寺雑掌に与える p.411) 上原郷半済職打渡状 明徳四年(一三九三)三月十六日(氏康が上原郷半済職を東福寺雑掌に与える p.411) 乗三書状案 三月十六日(東福寺上使乗三が夏所務未進等の完済を伝える p.412) 上原郷名主百姓等目安状 明徳四年(一三九三)九月(上原郷名主百姓等が夏麦皆損のため年貢免除を訴える p.414) 妙範書状案 四月二十七日(妙範が安部筑前判官入道等の違乱を訴える p.415) 上原郷名主百姓等申状 八月二十八日(上原郷百姓が訴訟に上った使者の私曲を詫びる p.416) 乗三書状 十月十三日(乗三が真壁氏の圧政を伝え善処を求める p.417)) 中世編Ⅱ家わけ史料細目次 九条家文書(上原郷関係) 上原郷政所光心書状 (十月十九日(光心が上原郷の夏麦等の未進を弁明する p.419 光心が上原郷の不時の支出等を弁明する p.420 光心が東福寺に起請文を提出する p.421) 十二月七日(光心が書状を東福寺の送り弁明する p.423)) 中世編Ⅱ家わけ史料細目次 九条家文書(上原郷関係) (上原郷半済方散用状 応永三年(一三九六)十月十五日(乗三等が上原郷半済方秋分ぼ算用状を注進する p.426) 上原郷内得岡名田畠土貢目安 応永五年(一三九八)五月(乗三等が上原郷得岡名田畠土貢目安を注進する p.429) 段銭京済奉書案 応永六年(一三九九)九月一日(上原郷段銭京済の国司催促を止めるよう伝える p.434) 上原郷百姓等雑用免除注文 応永六年(一三九九)(上原郷百姓等が雑用免除を注文する p.435) 段銭京済奉書案 応永七年(一四〇〇)七月二十日(上原郷段銭京済の国司催促を止めるよう伝える p.436) 上原郷秋畠検見帳 応永八年(一四〇一)九月十日(祥玉等が秋畠を検見し畠の流失目録を注進する p.436) 上原郷秋畠損亡注進状 応永八年(一四〇一)九月十日(祥玉が上原郷の秋畠損亡について注進する p.438) 給主祥玉書状 五月二日(祥玉が東福寺へ麦年貢納入について書状を送る p.439 祥玉が東福寺へ公文職等を渡したと回答する p.440 祥玉が東福寺へ山田地頭所につき書状を送る p.441) 給主祥玉書状 九月二日(祥玉が東福寺へ守護方の段銭催促等を注進する p.441) 上原郷御倉造料下行注文 応永九年(一四〇二)十月(明隠が上原郷御倉造営料支払いを求める p.442) 吉備津宮公文所親家書状 六月七日(吉備津宮が放生会流鏑馬役勤仕の請文を求める p.444) 延持・貞守連署一献分請取状 応永十三年(一四〇六)七月二日(吉備津宮流鏑馬役免除につき請取状を出す p.444) 延持・貞守連署一流鏑馬役免状案 応永十三年(一四〇六)七月二日(上原郷地頭方の吉備津宮流鏑馬役免除を伝える p.445) 沙弥正運書状包紙 応永十四年(一四〇七)(上原郷山田沙弥正運が東福寺に請文を差出す p.445)) 中世編Ⅱ家わけ史料細目次 九条家文書(上原郷関係) (上原郷内検帳前米銭渡状 嘉吉三年(一四四三)十月十七日(■■が上原郷内検帳前米銭を庄主に渡す p.446) 河西満秀名田畠去渡状 嘉吉三年(一四四三)十二月十七日(河西満秀が山田跡名田畠を東福寺に渡す p.446)) 中世編Ⅱ家わけ史料細目次 九条家文書(上原郷関係) (某寄附状案 文安元年(一四四四)二月九日(上原郷内の正公文職等を重ねて東福寺に寄進 p.447) 上原郷公田員数注進状 文安元年(一四四四)七月(納所受■等が上原郷公田の員数を注進する p.448) 上原郷百姓等目安 文安元年(一四四四)十一月五日(上原郷百姓が目安状により光心の非法を訴える p.448) 某事書案 文安元年(一四四四)十二月(某が光心の改易につき五ケ条の事書を言上する p.453)) 中世編Ⅱ家わけ史料細目次 九条家文書(上原郷関係) (上原郷上使在荘下用注文 宝徳二年(一四五〇)一月(永広が在荘下用算用書を提出する p.454) 石川昌秀・庄貞光連署渡状案 宝徳二年(一四五〇)二月十六日(石川昌秀が上原郷の下地を庄主に返付する p.459) 道賀・氏性連署奉書案 宝徳二年(一四五〇)二月二十五日(庄貞光が上原郷■所分を石川道寿代に与える p.460) 上原郷公事借銭注文 宝徳三年(一四五一)一月十一日(自慶が上原郷の公事借銭注文を注進する p.461)) 中世編Ⅱ家わけ史料細目次 九条家文書(上原郷関係) (石川道寿書状案 享徳元年(一四五二)八月二十六日(石川道寿が上原郷■所分名田を庄主に渡す p.462) 石川道寿書状 八月二十六日(石川道寿が上原郷■所分名田を庄主に渡す p.463) 石川道寿書状案 享徳元年(一四五二)十月十六日(石川道寿が■所分返付につき請取状を出す p.463) 石川道寿寄進状 享徳元年(一四五二)十月(石川道寿が上原郷■所分を東福寺に寄進する p.464) 石川道寿渡状 享徳元年(一四五二)十月(石川道寿が年貢免除等を求める p.464) 友吉源兵衛友吉名田地引文案 享徳元年(一四五二)十二月三日(友吉源兵衛が年貢未進につき田地を売る p.465) 竜■院永広書状案 十二月三日(永広が東福寺に■山八幡宮上葺の承認を求める p.466) 穴田宝英書状 享徳二年(一四五三)十二月二十一日(穴田宝英が繁公記室禅師に書状を送る p.467) 恵源書状案 一月十八日(恵源が上原政所へ長谷寺の事のつき返書する p.468) 家正彦五郎申状案 享徳三年(一五四五)一月三十日(家正彦五郎が年貢未進につき上申する p.468) 友吉源兵衛田地引文案 享徳三年(一五四五)二月十六日(友吉源兵衛が年季を限り田地を引き渡す p.469) 竜■院永広書状案 四月十三日(永広が■山八幡宮社役田の年季売りを求める p.470) ■山八幡宮造営役田売券案 享徳三年(一五四五)六月十三日(永広等が■山八幡宮社役田を売り渡す p.471) 竜■院永広書状案 十一月五日(永広が八幡宮造営等につき東福寺の書状を送る p.472) 白賀有友申状案 享徳四年(一四五五)二月十二日(白賀有友が有吉名年貢未進につき書状を送る p.474) 某書下案 享徳四年(一四五五)四月(某が■山八幡宮造営勧進米を借用する p.475)) 中世編Ⅱ家わけ史料細目次 九条家文書(上原郷関係) 友吉二郎三郎田地引文案 康正元年(一四五五)十月十日(友吉二郎三郎等が源兵衛の請人となり田地を引渡す p.476) 中世編Ⅱ家わけ史料細目次 九条家文書(上原郷関係) 上原郷内検帳 長禄元年(一四五七)十月二十六日(東温等が内検帳を注進し起請文を捧げる p.478) 中世編Ⅱ家わけ史料細目次 九条家文書(上原郷関係) 給主恵弘・源致家正名田畠売券案 長禄三年(一四五九)三月十二日(恵弘が家正名田畠を十余貫文で売る p.485) 中世編Ⅱ家わけ史料細目次 九条家文書(上原郷関係) 家正名覚書案(家正名売却につき庄主が沽券に加判する p.485) 中世編Ⅱ家わけ史料細目次 九条家文書(上原郷関係) 上原郷内検帳 (文明十一年(一四七九)十月(給主寿因が上原郷内検帳を注進する p.486) 文明十三年(一四八一)三月(給主寿因が上原郷内検帳を注進する p.493)) 中世編Ⅱ家わけ史料細目次 九条家文書(上原郷関係) 備中国守護奉行人連署奉書 二月九日(石川道寿等が国の干渉を止めるよう命じる p.515) 中世編Ⅱ家わけ史料細目次 九条家文書(上原郷関係) (竜■院永広書状 二月十日(永広が算用につき東福寺に書状を送る p.516) 竜■院永広書状案 六月十二日(永広が東福寺長老に年貢納入等を申し送る p.517) 竜■院永広書状 六月(永広が東福寺へ長谷寺等につき申し伝える p.519)) 中世編Ⅱ家わけ史料細目次 九条家文書(上原郷関係) 薬師寺永可書状 八月二十七日(薬師寺永可が東福寺へ年貢未進のことを伝える p.520) 中世編Ⅱ家わけ史料細目次 九条家文書(上原郷関係) 上原郷名々畠流失注文 八月二十八日(上原郷百姓が畠の流失注文を東福寺へ送る p.521) 中世編Ⅱ家わけ史料細目次 九条家文書(上原郷関係) 竜■院永広書状 八月二十八日(永広が上原郷の川成につき東福寺に書状を送る p.523) 中世編Ⅱ家わけ史料細目次 九条家文書(上原郷関係) 上原郷百姓等申状 九月二十三日(上原郷百姓らが日損について東福寺に訴える p.524 上原郷百姓等が東福寺に流失地を報告する p.525 上原郷百姓等が東福寺に流失地を報告する p.525) 中世編Ⅱ家わけ史料細目次 九条家文書(上原郷関係) 東福寺都寺昌聞・納所源材連署書状 九月二十四日(東福寺が損亡検見につき書状を送る p.526) 中世編Ⅱ家わけ史料細目次 九条家文書(上原郷関係) 上原郷年々未進目録 九月(永広が東福寺へ年貢未進目録を送る p.526) 中世編Ⅱ家わけ史料細目次 九条家文書(上原郷関係) 竜■院永広書状 (十月四日(永広が東福寺に書状を送り上原郷支証延引を弁明する p.527) 十月二十三日(永広が上原郷年貢未進につき東福寺に伝える p.528)) 中世編Ⅱ家わけ史料細目次 九条家文書(上原郷関係) 東福寺評定衆書状案 十一月一日(東福寺が上使を送り庄主の上洛を促す p.532) 中世編Ⅱ家わけ史料細目次 九条家文書(上原郷関係) 文勇書状 十一月三日(文勇が上原郷損亡につき東福寺に伝える p.533) 中世編Ⅱ家わけ史料細目次 九条家文書(上原郷関係) 東福寺評定衆受■・啓福連署書状案 十一月八日(東福寺が上原庄主の上洛延期を命ずる p.534) 中世編Ⅱ家わけ史料細目次 九条家文書(上原郷関係) 石川昌秀・庄貞光連署状 十一月十五日(石川昌秀・称貞光が上原庄主の書状を送る p.535) 中世編Ⅱ家わけ史料細目次 九条家文書(上原郷関係) 給主源致・玄作連署書状 (十一月二十日(源致・玄作が光心の悪行を東福寺に報告する p.537) 十二月八日(源致・玄作が上原郷につき東福寺に報告する p.539 源致等が上原郷年貢未進につき東福寺に伝える p.540)) 中世編Ⅱ家わけ史料細目次 九条家文書(上原郷関係) 庄道賀・石川道寿連署書状 十二月十四日(庄道賀等が年貢未進につき東福寺に伝える p.541) 中世編Ⅱ家わけ史料細目次 九条家文書(上原郷関係) (井手替地分注文(上原郷内家正名の井手替地分注文 p.542) 井手替地渡残分注文(上原郷内の井手替地渡残分注文 p.543)) 中世編Ⅱ家わけ史料細目次 九条家文書(上原郷関係) 上原郷関係包紙類(上原郷関係包紙類 p.544) 中世編Ⅱ家わけ史料細目次 吉備津神社文書 (庄永充・石河満経連署請文 応永三十年(一四二三)四月二十八日(守護代石河満経等が吉備津宮領の年貢を請負う p.545) 吉備津宮正殿御上葺棟札写 応永三十二年(一四二五)十二月二十九日(吉備津宮正殿の上葺が行われる p.546) 吉備津宮正殿御遷宮次第 応永三十三年(一四二六)一月(新山寺等が吉備津宮正殿遷宮に舞童を出す p.548) 石川掃部助久経請文写 宝徳二年(一四五〇)三月二十六日(石川久経が吉備津宮社務代職となり請文を出す p.549) 流鏑馬料足納帳(阿曽・三須等が吉備津宮へ流鏑馬料足を納める p.550) 吉備津宮梵鐘陰刻銘 永正一七年(一五二〇)四月九日(林但馬守藤原家朝が吉備津宮の鐘を鋳造する p.555) 坪付注文 大永六年(一五二六)十二月十三日(阿曽の鋳物師が吉備津宮へ五升鍋を奉納する p.556) 石川源三書状 十月十六日(国中棟別から寺家・社家を除く p.557) 石川左衛門尉家久書状 (天文七年(一五三八)四月十二日(吉備津宮社領の名主百姓の取締りを命ずる p.557) 天文七年(一五三八)五月十七日(石川家久が吉備津宮へ出入りの糺明を約束する p.558) 二月二十六日(石川家久が吉備津宮社塔を元の通り守らせる p.559) 安正御符沽券 弘治二年(一五五六)十二月十三日(安正が日羽郷御符を売渡す p.559) 庄為資書状 永禄元年(一五五八)四月二十日(庄為資が浦友のため出入りを裁判する p.560) 難波田右衛門尉外三名連署書状 二月十三日(難波田右衛門尉等が御贄を千百喉と定める p.560) 石川三郎五郎久智書状 (三月二十三日(石川久智が百姓の年貢無沙汰を取締る p.561) 十月二十四日(石川久智が栗坂表神領の百姓の言い分を糺す p.562) 十二月十三日(石川久智が吉備津宮神主からの書状に答える p.562) 十月九日(石川久智が神主宗三郎へ樽肴の礼を述べる p.563) 十二月十三日(石川久智が吉備津宮神主へ樽の礼を述べる p.563)) 佐野忠職・河内■資連署書状 八月五日(吉備津宮神人方が兵具を持つことを許す p.564) 清水長左衛門尉宗治書状 天正七年(一五七九)四月八日(清水宗治が吉備津神職の出入りを調停する p.565) 清水長左衛門尉宗治外二名連署書状 天正八年(一五八〇)十一月五日(清水宗治等が神職へ土地の配分を約束する p.565) 清水宗治・佐野忠職連署書状 二月二十六日(吉備津宮社領三カ郷に反銭を賦課する p.567) 経近左衛門太郎旦那職売券 天正十六年(一五八八)四月七日(経近左衛門太郎が草田村等の旦那職を売渡す p.568) 吉備津宮廻廊棟札(中島大炊助等が吉備津宮廻廊一間を寄進する p.568) 吉備津宮廻廊供養法華経(版本)端書■奥書(水内の女性が死後の冥福を祈り法華経を納める p.569) 経近左衛門五郎旦那職売券 文禄五年(一五九六)三月十三日(経近左衛門五郎が阿曽おくさこの旦那職を永代売渡す p.570) 吉備津宮惣解文(備中諸郷から産物等を吉備津宮へ納める p.571)) 中世編Ⅱ家わけ史料細目次 赤木家文書 (織田信長感状写 天正五年(一五七七)十二月五日(織田信長が播磨国佐用郡諸城攻略の功を称える p.576) 小早川隆景感状写 天正十年(一五八二)五月五日(小早川隆景が赤木与四郎の百貫の地を与える p.577) 毛利輝元感状写 天正十三年(一五八五)八月六日(毛利輝元が赤木蔵人の軍功に対して太刀と馬を与える p.577) 小早川隆景感状写 天正十三年(一五八五)八月十日(小早川隆景が赤木蔵人の軍功に対して太刀と馬を与える p.578)) 中世編Ⅱ家わけ史料細目次 池上家文書 総社宮文書 備中国惣社宮造営帳写 応永三十三年(一四二六)九月二十日(総社宮が造営される p.579 総社宮が造営される p.591) 中世編Ⅱ家わけ史料細目次 佐野家文書 (龍善坊増乗書状 明応七年(一四九八)六月三日(龍善坊が大山先逹につき中之坊を懲らしめる p.604) 石川源三書状 八月十四日(石川源三が佐野次郎左衛門の敗戦を慰める p.605) 某書状断簡(某が渋江衆等の立石城籠城を促す p.605) 某書状 六月二十七日(石川源三あて某返書 p.606) 石川通経書状 十一月二十三日(石川通経が次郎左衛門尉の申し分を認める p.607) 某書状 四月十一日(某が年貢・公事等を佐野二郎左衛門に託す p.607) 岡市之丞書状 文禄五年(一五九六)一月二十日(東三須百姓が郷役を勤仕できないと訴える p.608)) 中世編Ⅱ家わけ史料細目次 清水家文書 (小早川隆景起請文写 天正二年(一五七四)■十一月一日(清水長左衛門等に小早川隆景が起請文を与える p.610) 清水宗治書状 天正十年(一五八二)三月三十日(清水宗治が嫡子源三郎に書状を送る p.611) 毛利輝元書状 天正十年(一五八二)六月二十六日(毛利輝元が清水景治に太刀・刀を与える p.612)) 中世編Ⅱ家わけ史料細目次 中島家文書 (小早川隆景書状 (天正三年(一五七五)九月十一日(小早川隆景が中島大炊助に知行千貫を与える p.613) 天正十年(一五八二)七月二日(小早川隆景が中島大炊助等に境目の始末を頼む p.614) 天正十年(一五八二)八月十三日(小早川隆景が中島大炊助に刑部郷を与える p.615) 石川久智書状 五月三日(石川久智が中島新左衛門の軍功を称える p.616) 小早川隆景書状 三月九日(小早川隆景が備中境目の守護について指示する p.617) 穂井田元清書状 (五月十一日(穂井田元清が中島大炊助に境目の様子を尋ねる p.617) 五月十四日(穂井田元清が中島大炊助の普請見合せを了承す p.618) 井上又右衛門書状写 十月二十日(井上春忠が清水宗治に境目の守護を指示する p.618) 毛利輝元書状写 天正十月(一五八二)七月四日(毛利輝元が中島大炊助に国境の様子を尋ねる p.619) 小早川隆景感状写 文禄二年(一五九三)六月七日(小早川隆景が中島義行の戦功を称える p.620) 織田信長書状写 二月二十二日(織田信長が中島新左衛門に内通を勤める p.621) 穂井田元清書状写 五月二日(穂井田元清が中島大炊助の普請衆任命を喜ぶ p.621) 小早川隆景書状写 九月二十七日(小早川隆景が中島大炊助の功労を称える p.622) 穂井田元清書状写 七月二十六日(穂井田元清が中島大炊助に眼病の治療を促す p.622) 小早川隆景書状写 五月十三日(小早川隆景が中島大炊助妻等のもてなしを謝す p.623)) 中世編Ⅱ家わけ史料細目次 難波関係文書 (清水行宗・景治連署書状 天正十年(一五八二)六月八日(清水行宗等が難波田右衛門に香銭米二俵を送る p.624) 小早川隆景感状 天平十年(一五八二)六月十三日(小早川隆景が難波田右衛門の戦功を称える p.625) 小早川隆景書状 天平十一年(一五八三)七月十日(小早川隆景が難波田右衛門の行賞を行う p.626) 井上春忠書状 七月十二日(難波田右衛門に清水与右衛門跡職を引渡す p.626) 清水与右衛門先給田畠坪付 天正十一年(一五八三)八月十二日(清水田右衛門が清水宗重先給田畠を賜る p.627) 清水与右衛門先給田畠方坪付 天正十一年(一五八三)九月十四日(清水田右衛門が清水宗重先給畠を賜る p.629)) 中世編Ⅱ家わけ史料細目次 禰屋関係文書 (石川久智書状写 (六月二十三日(石川久智が禰屋秀光に備前勢撃退の礼を述べる p.632) 石川久智書状写 (五月十一日 石川久智が禰屋与七郎の竜の口城死守を称える p.633) 三村家親書状写 五月十九日(三村家親が禰屋与七郎等の奮闘を称える p.634) 石川久式書状写 八月三日(石川久式が禰屋七郎兵衛父子に領地を与える p.635) 井上又右衛門書状写 十一月二十日(井上春忠が禰屋七郎兵衛へ輝元の陣替を伝える p.636) 小早川隆景書状写 天正六年(一五七八)五月二十一日(小早川隆景が禰屋七郎兵衛に帰陣を命ずる p.637) 三村親成書状写 (天正六年(一五七八)六月一日 三村親成が禰屋七郎兵衛をいさめる p.638 三村親成が本陣の命に従えと禰屋家臣に伝える p.639) 小早川隆景書状写 (九月七日(小早川隆景が禰屋親光の備前勢撃退を称える p.640) 九月十二日(小早川隆景が禰屋親光の備前勢撃退を称える p.640) 九月十一日(小早川隆景が境の様子を聞くため使者を遺わす p.641)) 井上又右衛門書状写 天正十年(一五八二)四月二十七日(井上春忠が禰屋親光の手柄を称える p.641) 鵜飼新右衛門書状写 天正十年(一五八二)四月二十八日(鵜飼元辰が冠山で負傷した禰屋親光を見舞う p.642) 小早川隆景書状写 天正十年(一五八二)五月九日(小早川隆景が冠山で負傷した禰屋親光を見舞う p.643) 黒田官兵衛書状写 (天正十一年(一五八三)十二月二十日(黒田孝高が禰屋親光に芸州行きを勧める p.644) 黒田官兵衛書状写 (天正十二年(一五八四)三月二十一日 黒田孝高が禰屋親光の懇志に対して礼状を送る p.645) 石川久次書状写 十一月八日(石川久次が禰屋七郎兵衛へ帰陣の事情を伝える p.645) 小早川隆景書状写 (五月二十六日(小早川隆景が禰屋七郎兵衛等の出兵を慰労する p.646) 小早川隆景書状写 (五月十七日 小早川隆景が禰屋七郎兵衛の妻離別を称える p.647)) 中世編Ⅱ家わけ史料細目次 林家文書 織田信長感状写 天正五年(一五七七)十二月五日(織田信長が薩摩国佐用郡諸城攻略の功を称える p.648) 中世編Ⅱ家わけ史料細目次 宝福寺文書 (井山門徒連署宝福寺条々式目 延文六年(一三六一)三月二十三日(宝福寺の諸規定を定める p.649) 井山門徒連署天得庵定書 応安元年(一三六八)三月十八日(天得庵の諸規定を定める p.652) 上津江荘内三別所年貢料足定書 応安元年(一三六八)三月十八日(宝福寺々領の料足分配について定める p.654) 備陽井山宝福禅寺疏文(徹翁義亨が宝福寺の疏文を書く p.655) 井山門徒連署天得庵入庵定書 応安五年(一三七二)五月二十四日(天得庵坊主上洛時の料足を定める p.661) 般若庵遠大興隆之行事定書 至徳二年(一三八五)二月二十四日(般若庵興隆のため年貢料足の規定を定める p.662) 般若庵倉方造営物規式 永享三年(一四三一)四月八日(般若庵倉方造営物の規定を定める p.663) 宝福寺領検地帳 天正四年(一五七六)十一月二十三日(毛利氏が宝福寺領の検地を行う p.664) 蒔田広定寺領寄進状写 慶長十年(一六〇五)六月二十七日(蒔田広定が宝福寺大機長老に寺領を寄進する p.667)) 中世編Ⅲ軍事物細目次 太平記 (船上合戦事(備中の真壁氏等が後醐醍天皇に加勢する p.671) 四月三日合戦事付妻鹿孫三郎勇力事(備中の頓宮又次郎が六波羅攻めで活躍する p.672) 主上自令修金輪法給事付千種殿京合戦事(備中の真壁四郎等が六波羅方について奮戦する p.674) 越後守仲時巳下自害事(真壁三郎等が近江の番場宿で自刃する p.675) 諸国朝敵蜂起事(佐々木信■等が福山城に籠り官軍と戦う p.678) 備中福山合戦事(足利勢が備中福山合戦で勝利をえる p.681)) 中世編Ⅲ軍事物細目次 中国兵乱記 (将軍義稙公、所々御合戦並御上洛之事 p.688 義稙公、中国御政道並二階堂政行備中在国之事 p.689 大内義興、管領職御宥免並備中国御仕置之事 p.691 尼子晴久ヨリ三吉備後ヲ攻事並中国侍大将三吉江加勢之事 p.692 尼子晴久、安芸国江発向之節、備中侍大将、毛利元就江加勢之事 p.693 大内義隆、尼子晴久ヲ責事並播州赤松、備中江出陣之事 p.694 毛利元就、大内義長、陶五郎退治之事 p.696 宇喜多和泉守、備中江働之事 p.697 毛利元就、雲州江働之事 p.699 尼子義久、毛利家江降参之事 p.701 備中侍大将、備前竜口城江籠城之事 p.704 備前野田大炊助、備中侍将軍江計略之事 p.708 備前竜口城江備中侍大将加勢付討死之事 p.708 再竜口城江加勢、小田小太郎討死之事 p.712 宇喜多和泉守、備中ヨリ働之侍死骸ヲ送事 p.714 備前国金川城、宇喜多直家ヨリ責事 p.715 尼子晴久、備中へ働、所々城ヲ攻事 p.717 尼子勢、石川左右衛門尉留主幸山城ヲ責事 p.718 尼子勢、経山城主中島元行攻事■尼子勢敗軍之事 p.719 備前虎倉城主伊賀左右衛門ヲ宇喜多直家攻事 p.724 義輝公将軍宣下■御討死、義昭朝臣都落、織田信長頼給事 p.726 義昭公ヘ将軍宣下■織田信長ト御中絶之事 p.728 将軍御謀■■宇治槇島御籠城付西国落之事 p.730 将軍備後国ヘ御下向、毛利家御頼、■津ニ御在城■三村・石川逆心之事 p.732 備中国松山城主三村一類御退治之事 p.735 同国三村持之城々明退事 p.736 同国荒平山城主川西三郎左右衛門事 p.739 同国鬼身山城没落■上田実親切腹之事 p.740 芸州勢、成羽へ陣替■松山城兵働之事 p.743 備中松山城攻給フ事 p.745 松山城没落■三村元親切腹之事 p.748 石川勝法士三村一族被誅事 p.751 備中国平均、従毛利輝元卿将軍ヘ被行忠賞事 p.752 備前児島常山城没落■上野隆式一類自害之事 p.753 従義昭公、戦功之将ヘ興猿楽能、備中国境目御仕置之事 p.756 中島元行、戦死之者共為供養千部ヲ執行事 p.757 難波船軍付大阪城ヘ粮被籠事 p.758 摂州伊丹城ヘ従毛利家加勢被籠事 p.760 別所長治、毛利家ヘ降参之事 p.761 別所重棟、羽柴秀吉ヘ一身付長治ヘ異見之事 p.764 羽柴秀吉、播州上月城攻給事 p.765 毛利輝元、播州ヘ発向付尼子勝久攻給事 p.766 清水宗治ヘ袮屋一手鈴木・秋山逆心■尼子勝久切腹付山中鹿之助偽テ毛利家ヘ降参之事 p.767 神吉民部ヲ信忠卿責給事 p.771 山中鹿之助被誅事 p.772 備中境目城々御仕置、摂州荒木持之城々ヘ加勢ヲ被籠事 p.775 摂州花熊城ヲ池田信輝責取給事 p.778 宇喜多和泉守逆心之事 p.780 備前児島蜂浜合戦■宇喜多忠家討死之事 p.782) 中世編Ⅲ軍記物細目次 中国兵乱記 (宇喜多直家、備中ヘ働付従毛利家城々ヘ加勢ヲ被籠事 p.783 織田信長郷、清水宗治・中島元行ヘ御方仕様ニト御書参事 p.787 備中国高松城某外要害ヘ従芸州加勢ヲ被籠事 p.788 小早川隆景卿ヨリ清水宗治・中島元行ヘ神文給事 p.789 将軍義昭公ヘ清水宗治・中島元行致参上事 p.791 宇喜多直家病死之事 p.792 従信長卿、備中高松城責■清水宗治・中島元行ヘ神文給事 p.793 織田御次丸・羽柴秀吉、備中宮路山城攻之事 p.795 秀吉卿、備中冠山城攻付城主弥屋七郎兵衛働之事 p.795 秀吉卿、同国日幡城攻付上原元祐逆心之事 p.798 同国鴨庄城攻、桂・上山働付生石逆心之事 p.799 従輝元卿、御次丸・秀吉之御陣ヘ御働之御評議付安国寺妨之事 p.801 御次丸・秀吉之御陣所ヘ高松城内ヨリ夜討之事 p.803 芸州勢、清水・中島在城ヘ狼籍之事 p.806 四月廿七日、高松大合戦之事 p.807 宇喜多責口仕寄付事並城主働之事 p.812 高松城内持口ヲ定事 p.814 御次丸・秀吉卿、高松城水責術之事 p.816 信長郷軍勢、備中ヘ先逹而陣触之事 p.818 秀吉卿陣所ヘ安国寺御越候様ニト元卿へ使者参事 p.820 高松城主ヨリ秀吉卿ヘ可致切腹ト案内之事 p.821 従秀吉卿、高松城内へ御音信被遺事 p.822 清水宗治、嫡子源三郎ヘ書置並白井忠死之事 p.823 清水宗治切腹並検使堀尾茂助音信之事 p.825 中島元行・清水宗重猿掛城へ被召寄事 p.828 清水源三郎ヘ忠賞■中島元行ヘ備中御仕置被仰付事 p.829 輝元卿・小早川隆景ヨリ中島元行へ感状ヲ給事 p.830 蜂須賀彦右衛門尉・黒田官兵衛尉、備中へ分地請取ニ被参ニ付、高橋川切ニ宍戸隆家・中島元行改相渡事 p.831 猿掛山城寺社造営付北条家■能島・来島・因島之事 p.832 備中小平井天神宮之事 p.835 行軍之次第 p.835 一手之侍大将 p.838 朝鮮陣之時、小早川隆景渡海之事 p.840 秀俊御家、中島元行父子立退事 p.841 備中平山村又八郎蘇リ之事 p.843 大坂御陣之時、水野日向守殿御備ニテ中島宇右衛門働之事 p.844) 補遺細目次 (土御門実奉書 永仁四年(一二九六)七月十日(伏見天皇が石清水八幡宮の田上新庄支配を認む p.851) 橘宗将備中国田上本荘西方請所和与状 元応元年(一三一九)十二月十七日(橘宗将が田上本庄西方の年貢を請負う p.851) 備中国田上本荘地頭請所和与状 嘉暦二年(一三二七)三月十五日(地頭源貞綱が田上本庄東方の年貢を請負う p.852) 東光寺毘沙門天立像銘 正慶二年(一三三三)三月(比丘尼一念が大願主となり毘沙門天立像を造る p.853) 薙刀銘 康永三年(一三四四)十一月(水内庄の刀工次久が薙刀を鍛える p.853) 北野社大般若経奥書 応永十九年(一四一二)(惣社天神宮住侶秀海等が大般若経等を書写する p.854) 建内記 文安四年(一四四七)正月二十五日条(万里小路時房が赤浜保の年貢未進に付下知する p.856) 建内記 文安四年(一四四七)正月二十六日条(代官伊達久綱が赤浜村の年貢を請負う p.856) 康正二年造内裏段銭■国役引付 康正二年(一四五六)(日羽郷が内裏造営の段銭を課せられる p.857) 徐■送雪舟詩(雪舟が帰国するとき明の徐■が別れの詩を詠む p.857) 天開図画楼記(明から帰国した雪舟が豊後国天開図画楼に住む p.858) 日本洞上■灯録(華光寺大功円忠が入寂する p.858) 田中広清・城清連署沽却状案 長享三年(一四八九)八月二十三日(田中広清・城清が田上本庄の年貢を売却する p.860) 華蔵院無縫塔銘 明応九年(一五〇〇)十一月十九日(華蔵院四世高先和尚が死亡する p.860) 毛利元就・隆元連署感状 十一月二十二日(小寺十郎左衛門が服部表で敵を討取る p.861) 報恩寺妙見菩薩坐像銘 永禄十年(一五六七)四月六日(仏師秀誉上人が報恩寺妙見菩薩坐像を刻む p.861) 安国寺恵■・穂井田元清連署状 十一月二十三日(宍戸氏が上原・下原等を拝領する p.862) 普賢寺阿弥陀如来立像銘 天正十四年(一五八六)九月(仏師長助が普賢寺の阿弥陀如来立像を刻む p.863) 弥谷寺内大師写経窟鉄扉銘 慶長九年(一六〇四)四月(阿曽の宗右衛門が大師写経窟鉄扉を寄進する p.863)) つづきをとじる |
| ばしょ | |
| ばしょ | 岡山県総社市中央1丁目1 |
| NDCぶんるい | |
| NDCぶんるい | 217.5:岡山県 |
| けんさくキーワード | |
|---|---|
| けんさくキーワード | 郷土資料目次情報 |
| さんこうじょうほうげんまたはいんようじょうほうげん | |
| さんこうじょうほうげんまたはいんようじょうほうげん | [タイトルコード]1005010018890 |
| たいしょうねんれい | |
| たいしょうねんれい | 全年齢, 高校生 |
| きょうどじょうほうのげんご | |
| きょうどじょうほうのげんご | jpn |
| メタデータさくせいねんがっぴ | |
| メタデータさくせいねんがっぴ | 1988 |
| メタデータこうかいねんがっぴ | |
| メタデータこうかいねんがっぴ | 2011-02-24 |
| メタデータこうしんねんがっぴ | |
| メタデータこうしんねんがっぴ | 2011-02-24 |
| このページのURL | |
|---|---|
| このページのURL | http://digioka.libnet.pref.okayama.jp/detail-jp_c/id/kyo/M2008011911435563385 |