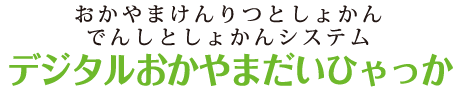きょうどじょうほうネットワーク > 長船町史 史料編 上,考古 古代 中世
長船町史 史料編 上,考古 古代 中世
カテゴリじょうほう
| きょうどじょうほうネットワーク > 目次情報 > 郷土資料目次情報 |
メタデータ
| タイトル | |
|---|---|
| タイトル | 長船町史 史料編 上,考古 古代 中世 (オサフネチョウシ シリョウヘン ジョウ コウコ コダイ チュウセイ) |
| きょうどじょうほうのしゅるい | |
| きょうどじょうほうのしゅるい | もじ |
| さくせいしゃまたはさくせいだんたい | |
| さくせいしゃまたはさくせいだんたい | 長船町史編纂委員会/編集 (オサフネチョウシヘンサンイインカイ) |
| こうかいしゃまたはこうかいだんたい | |
| こうかいしゃまたはこうかいだんたい | 長船町 (オサフネチョウ) |
| きょうどじょうほうのがいよう | |
| きょうどじょうほうのがいよう | 考古 旧石器・縄文・弥生時代 広高山遺跡 p.10 考古 旧石器・縄文・弥生時代 西谷遺跡 p.13 つづきをみる 考古 旧石器・縄文・弥生時代 丸山遺跡 (旧石器・縄文時代 p.15 弥生・古墳時代以降 p.16) 考古 旧石器・縄文・弥生時代 木鍋山遺跡 p.26 考古 旧石器・縄文・弥生時代 長船西遺跡 (的場A地点 p.34 的場B地点 p.39 慈眼院地点 p.40) 考古 旧石器・縄文・弥生時代 船山遺跡 p.41 考古 旧石器・縄文・弥生時代 土師東遺跡 p.42 考古 旧石器・縄文・弥生時代 福里遺跡 p.43 考古 旧石器・縄文・弥生時代 牛文向遺跡 p.47 考古 古墳時代 花光寺山古墳 p.50 考古 古墳時代 土師茶臼古墳 p.61 考古 古墳時代 築山古墳 p.65 考古 古墳時代 牛文茶臼山古墳 p.78 考古 古墳時代 小茶臼山古墳 p.89 考古 古墳時代 船山古墳 p.92 考古 古墳時代 油杉山古墳 p.97 考古 古墳時代 金鶏塚古墳 p.101 考古 古墳時代 亀ヶ原大塚古墳 p.109 考古 古墳時代 大塚古墳群 p.112 考古 古墳時代 大塚古墳群出土の可能性がある装飾須恵器 p.126 考古 古墳時代 磯上字小笠山出土例1 p.126 考古 古墳時代 磯上字小笠山出土例2 p.132 考古 古墳時代 (伝)長船大塚古墳出土例 p.137 考古 古墳時代 (伝)邑久郡出土例 p.142 考古 古墳時代 旧国府村出土例 p.147 考古 古墳時代 大塚峠一号墳 p.152 考古 古墳時代 南浦一号墳 p.154 考古 古墳時代 南浦二号墳 p.158 考古 古墳時代 向山二号墳 p.162 考古 古墳時代 馬塚古墳 p.165 考古 古墳時代 蟋古墳群 p.170 考古 古墳時代 山崎六号墳 p.182 考古 古墳時代 山崎七号墳(本坊山古墳) p.185 考古 古墳時代 山崎八号墳 p.192 考古 古墳時代 桂山十二ヶ乢五号墳 p.193 考古 古墳時代 西山・札崎古墳群 p.203 考古 古墳時代 亀ヶ原古墳群 p.217 考古 古墳時代 西須恵宮ノ尻出土異形陶棺 p.227 考古 古墳時代 木鍋山遺跡 p.229 考古 古墳時代 木鍋山一号窯跡 p.237 考古 古墳時代 花尻南窯跡群 p.241 考古 古墳時代 青木一号窯跡 p.251 考古 古墳時代 佐府池上池一号窯跡 p.254 考古 古墳時代 佐府池上池二号窯跡 p.256 考古 古墳時代 高山北窯跡 p.258 考古 古墳時代 奥池中池一・二号窯跡 p.260 考古 古墳時代 五郎ヶ市池窯跡 p.263 考古 古墳時代 亀ヶ原一号窯跡 p.266 考古 古墳時代 亥子田谷窯跡 p.269 考古 古墳時代 比丘尼岩下窯跡 p.272 考古 古墳時代 桂山林道峠窯跡 p.275 考古 古墳時代 中池西一号窯跡 p.277 考古 古墳時代 車輪文当て具痕のある須恵器 p.279 考古 奈良時代以降 須恵廃寺 p.282 考古 奈良時代以降 服部廃寺 p.304 考古 奈良時代以降 講堂跡南西部回廊の鍛冶炉様遺構の性格について p.323 考古 奈良時代以降 西谷遺跡 p.328 考古 奈良時代以降 小屋谷池一号窯跡 p.333 考古 奈良時代以降 丸山窯跡 p.335 考古 奈良時代以降 生砂(産土)池窯跡 p.336 考古 奈良時代以降 新池窯跡 p.344 考古 奈良時代以降 正伝名池窯跡 p.346 考古 奈良時代以降 油杉窯跡群 p.349 考古 奈良時代以降 一ノ谷窯跡 p.353 考古 奈良時代以降 長船西遺跡(城之内地点) p.355 考古 奈良時代以降 長船西遺跡から出土した鉄滓の組成 p.357 考古 奈良時代以降 福岡遺跡 (市場地点 p.364 殿町地点 p.366 旦過地点 p.371) 古代 中世 編年史料 古代 (先代旧事本紀第十一巻 吉備の各地域の国造の始祖を掲ぐ。大伯国造は佐紀足尼を始まりとす。 p.388 古事記下巻 吉備海部直の娘黒日売と仁徳天皇の恋の歌物語。 p.389 日本書紀巻十四 雄略七年是歳条 吉備海部直赤尾、新羅征伐を命じられて朝鮮にわたり、百済の才伎を招来す。 p.389 日本書紀巻十九 欽明一五年七月条 蘇我稲目らを遣わして、吉備五郡に白猪屯倉を設置す。 p.391 日本書紀巻二十 敏達元年五月条 吉備海部直難波、高麗の国使の送還を命ぜらる。 p.391 日本書紀巻二十 敏達三年一〇月条 蘇我馬子、吉備国に派遣され、白猪屯倉と田部を増やす。 p.391 日本書紀巻二十 敏達一二年七月条 吉備海部直羽嶋ら、日羅を迎える使者として百済にわたる。 p.391 日本書紀巻二十 敏達一二年条 吉備海部直羽嶋、日羅を百済から迎えることに成功す。 p.392 日本書紀巻二十六 斉明七年正月八日条 大伯皇女の命名は大伯海に由来す。 p.392 藤原宮跡出土木簡 藤原宮(694~710)出土の邑久郡貢進物に付されていた荷札木簡。 p.392 続日本紀巻一 文武二年四月三日条 備前国の秦大兄、香登臣の姓を賜る。 p.393 続日本紀巻二 大宝元年八月二一条 備前国などで、蝗・大風の被害。 p.394 続日本紀巻三 慶雲三年四月二九日条 備前国などで飢饉があり、賑恤がなされる。 p.394 続日本紀巻四 和銅元年三月二日条 備前国などで疫病があり、薬が給される。 p.394 平城宮跡出土木簡 平城宮(710~784)出土の、邑久郡関連の木簡。大部分は貢進物の荷札。 p.394 続日本紀巻五 和銅五年七月一五日条 備前など二一ヶ国で、初めて綾綿を織らせる。 p.397 続日本紀巻八 養老五年四月二〇日条 邑久・赤坂二郡の一部を割いて藤原郡を新置す。 p.398 類聚三代格巻一 天平三年六月二四日 備前の壬生、海部などの戸座に時服料・月料を支給す。 p.398 続日本紀巻一五 天平一五年五月二八日 邑久郡新羅邑久浦に珍しい大魚が五二隻も漂着す。 p.398 智識優婆塞等貢進文 天平一七年四月一八日 邑久郡須恵郷の宗我部人足が優婆塞として貢進される。 p.399 続日本紀巻一七 天平一九年二月二二日条 備前国などで飢饉あり、賑恤が行われる。 p.399 続日本紀巻一八 天平勝宝二年六月七日条 備前国で飢饉。 p.399 続日本紀巻二四 天平宝字六年五月一一日条 備前国で飢饉。 p.400 続日本紀巻二四 天平宝字七年五月六日条 鑑真の卒伝に、備前国の水田百姓が鑑真に施入されたことを記す。 p.400 続日本紀巻二四 天平宝字七年七月二六日条 備前国飢える。 p.401 続日本紀巻二五 天平宝字八年正月一六日条 備前国飢える。 p.401 続日本紀巻二五 天平宝字八年三月一四日条 備前国飢える。 p.401 続日本紀巻二五 天平宝字八年八月九日条 山陽道・南海道諸国で旱害。 p.401 続日本紀巻二七 天平神護二年五月二三日条 邑久郡香登郷ら六郷を藤野郷につける。 p.402 続日本紀巻二九 神護景雲三年六月二六日条 邑久郡の人、別部比治らに石生別公の姓を与える。 p.402 続日本紀巻三〇 宝亀元年三月一九日条 備前国仕丁秦刀良、畳作りを永年勤めた功により外従五位下を受ける。 p.402 沙弥勧籍啓 宝亀五年三月一二日 沙弥慈良は邑久郡積梨郡に本貫をもつ。 p.403 続日本紀巻三三 宝亀六年五月一一日条 備前国飢える。 p.403 続日本紀巻三六 宝亀一一年四月七日条 備前国邑久郡の荒廃田百余町を右大臣大中臣清麻呂に賜う。 p.403 続日本紀巻四〇 延暦九年四月五日条 備前国など飢える。 p.404 続日本紀巻四〇 延暦九年四月二九日条 備前国など一四ヶ国が飢える。 p.404 太政官符 延暦一五年一一月一三日 備前国が調として鍬鉄を進貢することを停止する。 p.404 日本後記巻八 延暦一八年六月五日条 前年の不作により、備前国など一一カ国の田租を免ず。 p.404 日本後記巻八 延暦一八年十二月八日条 備前国等の役夫を造宮に充てる。 p.405 日本後記巻八 延暦一八年一二月二八日条 和気広世、備前国の私墾田百町を邑久等八郡の賑救田に充てる。 p.405 日本後記巻一二 延暦二四年六月一〇日条 備前等一一カ国、彩帛をやめ旧によりお絹を貢す。 p.406 新抄格勅符第十巻抄 大同元年 備前国等に神社・寺院の封戸を定む。 p.406 太政官符 大同二年一〇月二五日 備前国等の駅馬を減ず。 p.407 弘仁式主税 弘仁一一年四月二一日 備前等の正税公廨稲・雑官稲を量定す。 p.407 続日本紀巻四 承和二年五月二九日条 備前国等に練糸を減じて生糸を進ましむ。 p.408 続日本紀巻五 承和三年九月三〇日条 備前国の人石生諸上らの本居を改める。 p.408 続日本紀巻六 承和四年二月二〇日条 備前国飢える。 p.408 続日本紀巻七 承和五年四月二一日条 備前国飢える。 p.409 類聚国史巻八四 承和五年五月二七日条 備前国で旱害、窮民に正税を貸与する。 p.409 続日本紀巻一〇 承和八年二月八日条 備前邑久郡安仁神社、名神に預る。 p.409 三代実録巻六 貞観四年五月二〇日条 備前等の瀬戸内沿岸諸国や四国の国々に下知し、海賊を追捕せしむ。 p.409 三代実録巻一二 貞観八年五月二七日条 備前国、旱害により正税を窮民に貸与す。 p.410 三代実録巻一三 貞観八年七月一四日条 備前国、飢饉により賑給す。 p.410 日本紀略前篇一九 元慶六年一二月二一日条 備前国等に漁猟を禁ず。 p.410 三代実録巻四四 元慶七年一〇月一七日条 備前国の公廨稲を割き、?賊を防ぐ兵士料とす。 p.410 三代実録巻四四 元慶七年一二月二二日条 備前等の百姓が、禁野内にて樵蘇することを許す。 p.411 三代実録巻四七 仁和元年二月二一日条 大嘗により備前国百姓の去年の庸を免除す。 p.411 三代実録巻五〇 仁和三年六月二日条 備前等一九ヵ国の貢絹が麁悪なため、国司が譴責される。 p.411 太政官符 寛平九年正月二五日 備前等が貢進する采女の定員を定める。 p.412 太政官符 延喜二年三月一三日 備前国らの田租を穎で徴収することを禁ず。 p.412 太政官符 延喜一〇年一二月二七日 備前等諸国の舂米を加増す。 p.413 貞観交替式 延喜二一年正月二五日 諸国の舂米運京の期日を定め、備前は六月三〇日以前とする。 p.414 延喜式巻七 備前国は大嘗会にあたって供神の雑器を造進す。 p.414 延喜式巻一〇 備前国の郡別式内社歴名。邑久郡では美和・片山日子・安仁の三社。 p.415 延喜式巻一一 備前以西の山陽道諸国に赴任する国司は海路をとる。 p.416 延喜式巻一五 備前国、年料として櫑子・黒米等を進む。 p.416 延喜式巻二〇 備前国等、大学寮の雑用料として舂米・軽物を貢納す。 p.417 延喜式巻二〇 備前国、正税の息利で大学学生の食糧塩を進む。 p.417 延喜式巻二二 美作・備前・備前国の等級及び所轄郡。備前国は上国でかつ近国とされている。 p.417 延喜式巻二二 備前国等に諸家封戸を置くことを禁ず。 p.418 延喜式巻二三 諸国の舂米運京の期限等を定め、備前は六月三〇日以前とす。 p.418 延喜式巻二三 諸国の年料租舂米の量等を定め、備前は二千石とす。 p.418 延喜式巻二三 諸国の年料別貢雑物の規定。備前は筆・麻紙・牛皮となっている。 p.419 延喜式巻二三 諸国が進貢する蘇の規定。備前は十壺で第六番(子・午年)の割りあて。 p.419 延喜式巻二三 美作・備前・備中国等の交易雑物の種類と量の規定。 p.419 延喜式巻二四 備前国等の貢進する糸・絹の種類を定む。 p.420 延喜式巻二四 備前国が貢進する調庸等の品目・量・運送行程についての規定。 p.421 延喜式巻二五 備前国は大豆八〇石を左馬寮の秣料として負担。 p.421 延喜式巻二六 備前国の正税の費目や量についての規定。 p.422 延喜式巻二六 備前国等の不堪佃田・賑給等の程限を定める。 p.422 延喜式巻二六 備前国等の禄物価法。 p.422 延喜式巻二六 備前国等の駅・伝馬の値法を定める。 p.423 延喜式巻二六 備前から京まで雑物を運送するにあたっての功賃の規定。 p.423 延喜式巻二八 諸国健児の規定。備前国は五〇人。 p.424 延喜式巻二八 備前国長嶋に馬牛牧を置く。 p.424 延喜式巻二八 諸国の器仗生産の規定。備前国は横刀十口など。 p.424 延喜式巻三一 備前国、大嘗会に供神料の雑器生産者一人を出す。 p.425 延喜式巻三一 備前国、贄の貢納を負担す。 p.425 延喜式巻三三 備前国、菓子として甘葛煎を蔵人所にお貢納す。 p.425 延喜式巻三四 備前国、雑物として庸米千石を木工寮に貢進す。 p.426 延喜式巻三七 備前国が貢進する薬草と品目と量。 p.426 延喜式巻三九 備前国、年料の贄として氷頭を進める。 p.427 延喜式巻四八 備前国、秣料として大豆八〇石を貢納す。 p.427 貞信公記 承平元年二月一七日条 備前国、秣料大豆を未進す。 p.428 貞信公記 承平二年一二月一六日条 備前国、海賊の事を奏す。 p.428 本朝世紀第四 天慶二年一二月二一日条 備前国等に藤原純友を召さしむ。 p.428 吏部王記 天慶四年六月一一日条 備前国からの使者、純友等の海賊が逃亡したことを報告す。 p.428 本朝世紀第五 天慶四年九月一九日条 備前国、邑久郡桑浜に上陸の凶賊を探索す。 p.429 本朝世紀第五 天慶四年九月二〇日条 備前国などに、凶賊の事によって官符を発す。 p.429 本朝世紀第五 天慶四年九月二二日条 備前国邑久郡桑浜に上陸した海賊、播磨に赴く。 p.430 西宮記巻七 天暦五年三月二〇日 備前国、仁王会の請僧供米を進上することが定められる。 p.430 太政官符 天禄元年九月八日 備前国などに、施米料として年料米の進納を命ず。 p.430 日本記略後篇七 天元元年三月某日条 備前介橘時望、海賊に殺さる。 p.431 中右記所引蔵人信経私記一 長徳三年五月二四日 備前の鍛冶白根安全に、高雄山で節刀を作らせる。 p.431 備前国司解案 長和四年四月二一日 備前国司、邑久郡少領の交替を願う。 p.432 極楽寺陳状 治安三年一〇月五日 備前国片岡庄などが石清水八幡宮寺極楽寺領としてみえる。 p.433 小右記八 長元元年八月二三日条 備前国百姓ら、善状を提出す。 p.434 小右記八 長元二年二月一一日条 備前国百姓の善状を進める。 p.435 僧網牒 天喜五年一二月七日 備前国講師に長増を擬捕す。 p.435) 古代 中世 編年史料 中世 (検非違使移 大治四年三月 平忠盛に海賊を搦め進めさせる。 p.437 中右記七 保延元年四月八日条 p.437 百錬抄第六 保延元年四月八日条 備前守平忠盛に海賊追討を命ずる。 p.438 中右記七 保延元年六月八日条 備前守平忠盛、海賊首を搦め取る。 p.438 中右記七 保延元年八月一九日条 備前守平忠盛、搦め進めた海賊を検非違使に引き渡す。 p.438 中右記七 保延元年八月二一日条 海賊追捕の賞行わる。 p.438 太政官符案 永治元年八月四日 障子内親王家領の香登勅旨庄に対する国郡課役が免除される。 p.439 鳥羽院庁下文案 久安二年五月日 備前国香登庄内の池成田の代わりとして服部郷の田地が加えられる。 p.439 備前国司庁宣案 久安三年一〇月日 p.440 右衛門督家下文案 久安三年一〇月二五日 備前国香登庄に水損の代替用地の加入を沙汰する。 p.440 本朝世紀三九 仁平元年正月二六日条 備前などで失損がひどく、改元がなされる。 p.441 官宣旨 保元三年一二月三日 備前国牛窓別宮・雄島別宮・片岡別宮が石清水八幡宮領としてみえる。 p.442 愚管抄第五 後白河院発願による蓮華王院の造営を清盛が備前国を宛てて行う。 p.444 菩提心院下文案 長寛三年三月二二日 大江遠業、香登庄の下司職を与えらる。 p.444 太政官牒案 長寛三年七月四日 靱負・服部両郷の一部を香登庄に編入したいきさつがみえ、同庄の不輸が認められる。 p.445 権大僧都某譲状案 承安四年一二月一六日 香登庄は阿闍梨隆位が知行していた。 p.446 百錬抄第八 治承元年八月二三日条 大極殿造営の所課に備前国が充てられる。 p.447 玉葉巻二 寿永二年一〇月一七日条 木曽義仲の軍勢、備前・備中で戦う。 p.447 玉葉巻二 寿永二年一〇月二一日条 平氏は備前国まで到り、美作以西は平氏の勢力下に。 p.447 後白河院庁下文案 寿永二年一一月4日 賀茂別雷社領備前国山田庄・竹原庄からの年貢米運上に煩をなさぬように、在庁官人に命ず。 p.448 吉記二 寿永二年一一月八日条 備前守源行家、平氏追討のために発向す。 p.448 吉記二 寿永二年一一月二八日条 備前国東川、西川の付近での源平合戦の消息が伝えられる。 p.448 吾妻鏡第三 元暦元年二月一八日条 梶原景時・土肥実平に美作・備前・備中国等を守護せしむ。 p.449 源頼朝下文案 寿永三年四月二四日 備前国山田庄・竹原庄など賀も別雷社領での武士の狼藉を禁す。 p.449 玉葉巻三 寿永三年六月一六日条 梶原景時、播磨国から備前国に到る。その間に平氏は室泊を襲撃。 p.450 源頼朝下文案 元暦二年正月九日 源頼朝、石清水社領備前国牛窓・雄島・片岡別宮等での武士の狼藉を停止する。 p.451 玉葉巻三 元暦二年六月三〇日条 平頼盛、備前国の知行国主となる。 p.452 吾妻鏡第六 文治二年六月九日条 源頼朝と後白河院との政治折衝の中で、備前国は法勝寺用途にあてられる。 p.452 吾妻鏡第六 文治二年六月二一日条 頼朝、備前を含む西国三七ヵ国の地頭をとどめる。 p.453 吾妻鏡第六 文治二年閏七月一九日条 播磨・備前での武士の乱妨が問題となる。 p.454 玉葉巻二 文治三年一〇月三日条 重源、備前国の荒野を開発して東大寺大仏再建の用途にあてる。 p.454 菩提心院供僧等解案 文治三年一一月日 香登庄に賦課せれた法勝寺九重塔造営用途の免除が領家によって要請される。 p.455 八条院庁下文案 文治六年三月二日 香登庄では、近来旱魃・洪水が発生していた。この年、庄内の池成田を開発す。 p.456 玉葉巻三 建久三年二月一七・一八日条 後白河法皇崩す。遺領に備前国神崎・豊原庄あり。 p.457 玉葉巻三 建久四年四月七日条 p.457 玉葉巻三 建久四年四月九日条 p.457 玉葉巻三 建久四年四月一〇日条 p.458 玉葉巻三 建久四年四月一六日条 備前国、造営料国として東大寺に付され、重源が国務をとる。 p.458 八条院庁下文案 建久四年九月二三日 香登庄下司業資、濫行によって庄内を追却される。 p.459 官宣旨案 建久六年五月七日 重源の要請をうけて、備前国邑久郡内の南北条・長沼・神崎の開発地を東大寺の領地とする。 p.460 太政官符案 建久七年六月三日 備前・備中などの瀬戸内沿岸諸国、重源による泊の修復に協力す。 p.461 重源譲状 建久八年六月一五日 重源、備前国南北条・長沼・神前・野田庄などの所領等を律師定範に譲る。 p.463 明日記第二 建保元年一二月一〇日条 備前国、山門の堂塔修理料国とされる。 p.466 官宣旨 承久三年一〇月二九日 備前・備中両国、鎌倉幕府の知行国となる。 p.467 吾妻鏡第三九 宝治二年八月一〇日条 備前国住人服部左衛門六郎、父祖の功をもとに鎌倉幕府に奉公することを望む。 p.468 関東後教書 文永元年四月二六日 裏作の麦に所当を課すことが禁じられていることから、備前国での二毛作が確認される。 p.468 備前弘法寺禁制 文永六年九月五日 p.469 備前国豊原庄預所下文 文永六年一〇月日 備前国弘法寺禁制が成る。 p.469 一遍上人絵伝第十四段 p.470 一遍上人縁起絵第一 弘安元年(1278)冬、一遍、備前福岡市で布教。 p.471 東大寺注進状案 弘安八年八月 東大寺、備前国長須(沼ヵ)・神崎・南北条につき注進。 p.472 将軍惟康親王家政所下文 正応元年一一月二一日 小早川政景に備前国裳懸庄地頭職が充行われる。 p.473 小早川定心政景譲状 正応二年二月一六日 備前国裳懸庄地頭職などが、小早川政景から子息政宗に譲与される。 p.473 東大寺衆徒等申状案 永仁二年四月日 東大寺、寺領の備前国南北条・長沼・神崎庄の返付を重ねて訴える。 p.474 弘法寺本堂供養請定 正安二年一一月二日 備前国弘法寺本堂供養に大賀島・熊山・豊原らの僧が出席。 p.475 後宇多上皇院宣 嘉元二年一〇月一五日 備前国尾張保を賀茂社領とす。 p.476 洞院公賢奏事法勝寺条々 徳治三年六月一日 備前国服部保は、法勝寺領で保内に鍛冶給があった。 p.476 備前国刀匠熊野参詣願文 元享元年二月二五日 備前国畠田の住人らが熊野信仰によって、太刀を進上したという。 p.476 後宇多上皇院宣 元享元年十月九日 備前国上東郡豆田郷内の荒沼地が、後宇多院によって東寺に寄附される。 p.477 太平記巻二十八 p.477 毛利元春自筆事書案 p.478 大乗院日記目録一 貞和六年 観応元年(1350)十一月十九日、足利尊氏軍が福岡に到着し、しばらく駐留す。 p.478 足利尊氏御判御教書 観応元年一一月二一日 足利尊氏、弘法寺に凶徒退治の祈祷を命ず。 p.479 太平記巻二十九 p.479 松浦秀軍忠状 観応二年七月日 観応元年十二月松、足利尊氏、福岡を発して京都に向かう。 p.480 後村上天皇綸旨写 正平八年五月二二日 備前国須恵保地頭職などが、南朝によって、大興禅寺の造営料所とされる。 p.480 園太暦二十二 文和二年七月二五日条 石橋和義、赤松則祐らと共に、備前守護松田盛朝の軍が入京す。 p.481 道ゆきぶり 応安四年(1371)今川了俊は九州下向の途中、香登を経て福岡に到着。その地の繁栄ぶりを記す。 p.481 室町幕府奉行人連署奉書 応安七年一〇月一三日 金岡東庄に打入り狼藉行為を働いた豊原庄住人の中に須恵弥次郎の名がみえる。 p.482 備前国新田荘上長船村熊野参詣願文 康暦二年三月五日 新田庄内上長船村の人、熊山僧を先達として熊野に参詣す。 p.483 沙弥宗覚浦上田地寄進状案 康暦三年二月二四日 浦上宗覚、備前国磯上保内一色田の一町を大徳寺如意庵に寄進する。 p.483 備前磯上保如意庵分田地注文 至徳元年一〇月日 備前磯上保如意庵田地注文成る。 p.484 浦上景祐田地寄進状 至徳四年五月八日 浦上景祐、備前国磯上保に代えて、小宅庄三職内田地を大徳寺如意庵に寄進する。 p.485 室町幕府管領細川満元奉書案 応永一九年九月一一月日 東寺造営の費用にあてるため、備前国などに棟別銭が賦課される。 p.485 備前国棟別銭沙汰■無沙汰在所注文案 応永二〇年八月日 備前国における棟別銭の納入状況の注文。靭負郷・土師郷・服部郷・磯上保・須恵保・福岡庄南北などがみえる。 p.486 縁秀書状 二月三日 備前国での棟別賦課が実施される。 p.488 伊予法眼縁親書状 六月九日 棟別の事、福岡へ人を遣わし守護の意向を尋ねる。 p.489 快玄書状案 九月二九日 備前国棟別の徴集を児島山臥が行う。 p.489 伊予法眼縁親書状 二九日 棟別の事、福岡へ赴き、守護の力をかりて徴集をはかる。 p.490 某書状包紙 年月日未詳 備前国棟別銭について、近日報告することが告げられる。 p.491 備前国長船住檀那交名願文 応永二九年三月一八日 備前国長船住の檀那ら、熊野に参詣す。 p.491 正通寺本堂礎石銘文 応永三一年一〇月二六日 正通寺本堂礎石に転用されている宝篋印塔が造立される。 p.492 備前国長船住人熊野参詣願文 応永三二年四月八日 備前国長船住人ら、熊野に参詣す。 p.492 看聞御記下 永享八年一一月二四日条 慢西堂、福岡長福寺院主に請われ備前に下向のため暇乞いにやってくる。 p.492 建内記三 嘉吉元年七月二六日条 備前国豊原六郷の野伏、播磨に発向す。 p.493 備前国国衙料所注文案 年月日未詳 備前国国衙の御料所として、土師郷。服部保がみえる。 p.493 蔭凉軒日録 文正元年閏二月一七日条 備前守護山名教之と国人松田元秀が対立との情報がみえる。 p.494 赤松政則袖判難波行豊軍忠状 文明一三年四月七日 応仁元年(1467)五月頃福岡には山名勢の小鴨大和守が用害を構えていたが、その後浦上勢らに追われる。 p.494 応仁別記 応仁元年五月一〇日 p.495 重編応仁記四 赤松勢、播磨・備前に乱入し制圧す。 p.495 尾張保河崎弥六安永田地沽券 文明七年一二月二〇日 尾張保の河崎弥六、山田庄内恒松六郎次郎に田地一段を売却す。 p.496 浦上家系図 文明一五年(1483)冬~文明一六年正月、福岡城に拠る浦上則国らを山名・松田勢が攻撃、合戦す。 p.496 庶軒日録 文明一六年六月二日条 備前福岡の鴨田越中入道が、季弘大叔を訪問す。 p.497 山名政豊感状 文明一七年二月二七日 p.498 山名政豊感状 文明一七年閏三月二〇日 p.498 蔗軒日録 文明一七年二月二三日、三月一日条 文明一七(1485)年二月二二日、山名勢と赤松勢が福岡で合戦。ついで恥じ河原でも戦う。 p.498 浦上則宗寄進状 文明一七年三月一五日 浦上則宗、戦勝祈祷のため、豊原庄内の幕府料所年貢五石を余慶寺に寄進す。 p.498 蔗軒日録 文明一七年閏三月九日条 p.499 蔗軒日録 文明一七年閏三月一四日条 浦上氏、備前国砥石城に戦い、則国は討死す。 p.499 庶軒日録 文明一八年四月一九日条 備前福岡の交易商人が、唐人の画軸を持ってやってくる。 p.499 蔭凉軒日録 長享二年七月二〇日条 赤松政則、備前福岡の敵(山名勢)を退散させる。 p.500 蔭凉軒日録 長享二年七月二一日条 浦上三郎四郎宗助、福岡城に入る。 p.500 蔭凉軒日録 長享二年八月二二日・九月二一日条 備前の刀工長船勝光・宗光の一党、近江国鉤の陣で刀を打つ。 p.500 蔭凉軒日録 長享三年三月九日条 備前土師郷、万寿寺領としてみえるが、この当時不知行であった。 p.500 新納忠続書状 長享三(延徳元)年一二月二七日 薩摩守護島津忠昌より下された長船刀などを、新納忠続から忠明に譲与す。 p.501 伺事記録 延徳二年九月二六日条 備前国尾張保の年貢を、守護赤松政則の被官人が兵粮料と称して押領す。 p.502 蔭凉軒日録 延徳四年五月二日条 備前福岡へ禅孝が帰るに際し、浦上氏への書状を託される。 p.502 本宮某書状 明応六年三月日 熊野山の敷屋源六、備州長舟の鍛冶党を旦那とする。 p.503 土師郷貞宗三郎二郎家助屋敷沽券 明応七年三月二二日 備前土師郷貞壬宗三郎二郎家助、牛窓関浦に所持する屋敷を売却す。 p.503 浦上宗次書状 永正九年閏四月一七日 浦上宗次勢、福岡へ向かう。 p.504 妙興寺一石五輪塔銘文 永正元年六月一三日 p.504 妙興寺一石五輪塔銘文 大永四年八月 p.504 妙興寺一石五輪塔銘文 享禄四年一〇月二八日 p.505 妙興寺一石五輪塔銘文 天文五年六月三日 p.505 妙興寺一石五輪塔銘文 天文八年五一〇日・一一月一九日 p.505 妙興寺一石五輪塔銘文 天文九年三月一日 p.505 妙興寺一石五輪塔銘文 天文一七年七月二六日 p.506 妙興寺一石五輪塔銘文 天文二〇年正月一一日 p.506 妙興寺一石五輪塔銘文 天文二三年二月八日 p.506 妙興寺一石五輪塔銘文 永禄三年二月八日 p.506 妙興寺一石五輪塔銘文 永禄七年八月二二日 妙興寺境内の一石五輪石塔の銘文 p.506 足利義昭書状 元亀四年三月二二日 足利義昭、聖護院道澄に浦上宗景らの参陣を要請す。 p.507 宗将盛書状 三月五日 対馬宗将盛、大内義隆に長船長光作の太刀等を贈る。 p.507 本蓮寺抱分米銭算用状 天正五年一二月二一日 本蓮寺抱分の内に、須恵保内地子銭がみえる。 p.508 羽柴秀吉禁制 天正一〇年三月日 羽柴秀吉、備前福岡に乱妨狼藉の禁制を発す。 p.508 広高八幡宮文字瓦 天正一三年閏七月一三日 広高八幡宮(現美和神社)の舞殿建立を伝える文字瓦が作られる。 p.509 宇喜多秀家知行目録 慶長三年七月二三日 宇喜多秀家によって、備前邑久郡服部など百石が大森隆久の扶持とされる。 p.509) 古代 中世 福岡庄関連史料 中世 (福岡庄作麦畠注文案 嘉応二年 嘉応二年、福岡庄の麦畠の状況 p.512 吾妻鏡第四 元暦二年五月1日条 備前国福岡庄は、崇徳院法花堂領であったが、牢籠のため取り替えられる。 p.513 吾妻鏡第八 文治四年一〇月四日条 頼朝、備前国福岡庄を崇徳院の国忌料にあてる。 p.513 福岡庄吉井村作田内検目録 建長元年 建長元年、福岡庄吉井村の作田の状況。 p.514 福岡庄吉井村畠目録案 正嘉元年 正嘉元年、福岡庄吉井村の作畠の状況。 p.516 一遍上人絵伝第十四段 p.517 一遍上人縁起絵第一 弘安元年(1278)冬、一遍福岡市に布教。 p.517 簡要類聚鈔第一 弘安五年七月二三日 一乗院門跡領の中に福岡庄がみえ、成立以来の由緒が記されている。 p.517 六波羅探題召文案 〔応長元~正和二〕五月二二日 福岡庄吉井村地頭代見日の申状について、六波羅探題よりの召文。 p.518 最勝光院領荘園目録 正中二年三月日 福岡庄など最勝光院領庄園が東寺領に編入された時の状況を示す注文。吉井村は地頭請であった。 p.518 最勝光院領荘園目録抄 備前国福岡庄の概略を記す。 p.523 六波羅御教書 嘉暦二年一〇月二八日 福岡庄吉井村一分地頭頓宮孫三郎ら、年貢抑留を訴えられ六波羅に出頭を求められる。 p.523 六波羅御教書案 嘉暦二年一〇月二八日 福岡庄吉井村の年貢抑留につき、地頭頓宮肥後三郎らが出頭を命じられる。 p.524 六波羅御教書案 嘉暦二年一二月八日 福岡庄吉井村の年貢抑留につき、六波羅探題は地頭代に出頭を命ず。 p.524 関東下知状 元徳元年一〇月二五日 備前国吉井村一分地頭職などについて、幕府は冷泉為相から為成への相伝を認む。 p.525 冷泉為成避状 元徳二年二月一一日 冷泉為成、備前国吉井村一分地頭職を弟の為秀に譲与す。 p.525 式部八郎入道素道代子息忠綱福岡庄吉井村預所職請文 元弘三年一一月一九日 式部忠綱、福岡庄預所として年貢・市場雑物の沙汰を請け負う。 p.525 雑訴決断所牒 建武元年五月二一日 雑訴決断所、福岡庄吉井内下市村における甲乙人の濫妨を制止す。 p.526 光厳上皇院宣 建武三年一二月八日 光厳上皇、最勝光院領福岡庄内吉井村の知行を東寺供僧に認可す。 p.527 足利尊氏御判御教書案 建武五年正月一五日 福岡庄内頓宮三郎二郎跡の所領が、足利尊氏によって佐々木豊前入道に与えられる。 p.527 足利尊氏御判御教書案 歴応三月年八月二二日 福岡庄内頓宮三郎二郎跡が、尊氏によって再び頓宮氏に返還される。 p.528 室町幕府執事高師直施工状案 暦応三年八月二二日 前号史料の尊氏の命令が、執事から備前守護に施行される。 p.528 快円請文 暦応四年閏四月八日 吉井村内八町河原、八日市の預所職について頓宮氏が契状を進め、快円も同様の請文を東寺に提出。 p.529 東寺雑掌光信申状 康永元年五月日 東寺雑掌光信、福岡庄吉井村について、地頭による嘉歴年間以来の年貢抑留・所務押妨を訴える。 p.529 福岡庄吉井村地頭等抑留年貢注文案 嘉歴元年~暦応四年 嘉歴元年~暦応四年の抑留年貢の注文 p.530 室町幕府引付頭人吉良貞家奉書 康永元年七月四日 東寺雑掌光信による吉井村所務・年貢に関する訴えをうけ、幕府は参決を命じる。 p.530 福岡庄惣領地頭左衛門慰嗣請文 康永二年三月日 祐尊、福岡庄吉井村内八町河原の沙汰雑掌となる。 p.531 権少僧都仲我挙状案 四月二日 福岡庄吉井村内雑掌祐尊が、申状を提出。 p.531 権大僧都氏名未詳挙状案 九月二四日 東寺、福岡庄吉井村内八丁河原の寺用年貢対捍を訴える。 p.532 備前国福岡庄吉井村頓宮氏庶子旧領年貢等注進状案 年月日未詳 吉井村地頭庶子跡・年貢の未進分についての注文 p.532 東寺雑掌光信申状 貞和二年九月日 福岡庄吉井村八町河原の支配をめぐって、冷泉為秀と東寺雑掌光信が争う。 p.533 福岡庄吉井村領家年貢難済庶子等注文(折紙) 年月日未詳 吉井村地頭庶子跡年貢の未進分についての注文 p.533 福岡庄文書包紙 年月日未詳 東寺で保管していた備前国福岡庄に関する文書類の目録 p.534 足利尊氏御内書 極月十九日 足利尊氏、備前国吉井村一分地頭職を冷泉為秀領として認可す。 p.535 福岡庄吉井村預所職補任状案 延文二年六月二一日 福岡庄内吉井村預所職が、教密上人に与えられる。 p.535 教密房栄潤福岡庄吉井村預所職請文 延文二年六月二一日 教密房栄潤、福岡庄内吉井村預所の職務を適正に遂行することを請負う。 p.536 太平記巻三十六 福岡庄は頓宮氏の所領で細川清氏が安堵しても、赤松則祐・佐々木道誉のために還住できず、細川清氏の幕府離反の一因となる。 p.536 権律師寄進状写 康安二年五月二〇日 赤松即祐、備前福岡庄を吉祥寺に寄進す。 p.537 室町幕府引付頭人斯波義高奉書 貞治二年一二月二四日 東寺雑掌頼憲が福岡庄内吉井村領家年貢の事で、赤松則祐を訴える。 p.537 左近将監義高書状包紙 貞治三年六月二一日 福岡庄吉井村領家職の事で、左近将監斯波義高より赤松則祐へ書状 p.538 室町幕府引付頭人山名時氏奉書案 貞治五年一二月三日 福岡庄内吉井村年貢について、小国九郎入道の押領がとどめられる。 p.538 福岡庄内吉井村一分地頭職目安案 貞治五年一二月 福岡庄内吉井村一分の証文類を進上す。 p.539 最勝光院方所領文書目録 応安元年一二月 最勝光院方の所領の内に福岡庄がみえる。 p.539 応安三年最勝光院引付(袋綴) 応安三年七月 日 東寺雑掌頼憲、福岡庄吉村の年貢を小国宮内左衛門入道が抑留することを訴える。 p.540 室町幕府引付頭人仁木義尹奉書 応安三年一一月一四日 東寺雑掌頼憲、小国宮内左衛門入道が福岡庄吉村の年貢抑留することをさらに訴える。 p.541 室町幕府引付頭人奉書案 年月日未詳 東寺雑掌頼憲の重ねての訴えにより、小国宮内左衛門入道年貢押領がとどめられる。 p.541 応安六年最勝光院方評定引付(袋綴) 応安六年 東寺最勝光院方で、福岡庄給主の人選について評定がなされる。 p.542 備前散在斗餅田下地注文 嘉慶二年一二月 日 福岡庄内本庄北方に熊野散在田二町五段がみえる。 p.544 備前国棟別銭免除在所注文 応永二〇年四月一一日 備前国棟別銭がこれまで免除された中に福岡庄南北がみえる。 p.545 備前国棟別銭沙汰■無沙汰在所注文案 応永二〇年八月 日 備前国における東寺造営料棟別銭の納入状況を示す注文に、福岡庄南北がみえる。 p.545 浦上政宗書状 六月七日 福岡庄の年貢のうち千疋が、浦上政宗から遠藤弥八郎にあてられる。 p.546 浦上宗景書状 天正二年一〇月六日 浦上宗景、福岡庄南方などを馬場源丞の安堵す。 p.546) 古代 中世 町内所在中世文書(平井家文書) 平井家宛行状巻子 (秀□扶持宛行状 p.548 国富重幸・金光朝勝連署扶持宛行状 p.548 金光秀盛・能勢秀綱連署宛行状 p.548 金光秀盛宛行状 p.548 税所経■書状 p.549 税所秀経等連署書状 p.549) 古代 中世 町内所在中世文書(平井家文書) 平井右兵衛宛感状巻子 (虎満感状 p.550 赤松政村感状 p.550 浦上政宗感状 p.550 豊前守久経感状 p.550) 古代 中世 町内所在中世文書(平井家文書) 『黄薇古簡集』所収文書 (浦上政宗感状 p.551 浦上政宗書状 六月七日 p.551) 古代 中世 軍記物(参考資料) 備前軍記 p.554 古代 中世 軍記物(参考資料) 備前文明乱記 p.576 つづきをとじる |
| ばしょ | |
| ばしょ | 岡山県瀬戸内市長船町服部 |
| NDCぶんるい | |
| NDCぶんるい | 217.5:岡山県 |
| けんさくキーワード | |
|---|---|
| けんさくキーワード | 郷土資料目次情報 |
| さんこうじょうほうげんまたはいんようじょうほうげん | |
| さんこうじょうほうげんまたはいんようじょうほうげん | [タイトルコード]1009810026470 |
| たいしょうねんれい | |
| たいしょうねんれい | 全年齢, 高校生 |
| きょうどじょうほうのげんご | |
| きょうどじょうほうのげんご | jpn |
| メタデータさくせいねんがっぴ | |
| メタデータさくせいねんがっぴ | 1998 |
| メタデータこうかいねんがっぴ | |
| メタデータこうかいねんがっぴ | 2011-02-24 |
| メタデータこうしんねんがっぴ | |
| メタデータこうしんねんがっぴ | 2011-02-24 |
| このページのURL | |
|---|---|
| このページのURL | http://digioka.libnet.pref.okayama.jp/detail-jp_c/id/kyo/M2008011911441063395 |