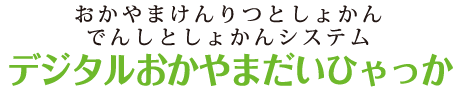きょうどじょうほうネットワーク > 近世日本海運史の研究
近世日本海運史の研究
カテゴリじょうほう
| きょうどじょうほうネットワーク > 目次情報 > 交通文化資料目次情報 |
メタデータ
| タイトル | |
|---|---|
| タイトル | 近世日本海運史の研究 (キンセイニホンカイウンシノケンキュウ) |
| きょうどじょうほうのしゅるい | |
| きょうどじょうほうのしゅるい | もじ |
| さくせいしゃまたはさくせいだんたい | |
| さくせいしゃまたはさくせいだんたい | 上村 雅洋/著 (ウエムラ マサヒロ) |
| こうかいしゃまたはこうかいだんたい | |
| こうかいしゃまたはこうかいだんたい | 吉川弘文館 (ヨシカワコウブンカン) |
| きょうどじょうほうのがいよう | |
| きょうどじょうほうのがいよう | 序論 (一 研究史 p.1 二 分析視角と本書の構成 p.7) 第一章 近世海運の成立と展開 (一 払米市場と廻船 p.28 二 河村瑞賢と近世海運の成立 p.31 三 江戸・大坂幹線と商品流通 p.36 四 北前船と地方廻船の発展 p.42) つづきをみる 第二章 近世の米穀流通と廻船の展開 (一 各港での米穀取扱状況 p.48 二 大坂・江戸への廻米 p.50 三 城米輸送 p.51 四 大坂登米輸送 p.54 五 地方米穀市場と廻船の発展 p.56 六 讃岐国直島の海難史料に見る米穀流通と廻船 p.58) 第三章 近世の商品流通と廻船の発展形態 一 商品流通史料について p.71 第三章 近世の商品流通と廻船の発展形態 二 讃岐国直島と海難 p.75 第三章 近世の商品流通と廻船の発展形態 三 商品流通経路と廻船 p.77 第三章 近世の商品流通と廻船の発展形態 四 廻船市場 (一 大坂周辺地域 p.83 二 北国・山陰地域 p.86 三 山陽地域 p.87 四 九州地域 p.90 五 四国地域 p.92 六 東海地域 p.94 七 小括 p.94) 第四章 菱垣廻船再興策と紀州廻船 p.106 第四章 菱垣廻船再興策と紀州廻船 一 紀州廻船の動向 (一 紀州廻船の登場 p.107 二 明和-弘化期における艘数動向 p.108 三 廻船所有者動向 p.111 四 紀州廻船の隆盛 p.111) 第四章 菱垣廻船再興策と紀州廻船 二 紀州廻船の菱垣廻船への合体 (一 目的と誘因 p.113 二 経過 p.114 三 合体による積荷変化 p.118) 第四章 菱垣廻船再興策と紀州廻船 三 紀州廻船の衰退 (一 衰退の原因 p.120 二 合体後の経過 p.123) 第五章 紀州廻船業者の在村形態 (一 薗家の場合 p.130 二 村上家の場合 p.136) 第六章 有田蜜柑輸送と日高廻船 一 有田蜜柑の出荷形態 p.153 第六章 有田蜜柑輸送と日高廻船 二 有田蜜柑の輸送状況 (一 組株段階での状況 p.156 二 積合・郡段階での状況 p.160 三 嘉永4年における状況 p.164) 第六章 有田蜜柑輸送と日高廻船 三 廻船経営と蜜柑輸送 (一 益久丸の経営 p.169 二 揚力丸の経営 p.175) 第七章 新宮鵜殿廻船と炭木材輸送 (一 新宮廻船と鵜殿廻船 p.181 二 熊野地方の炭木材輸送 p.186) 第八章 尾鷲入津の城米船 (一 史料について p.198 二 城米輸送 p.200 三 城米船 p.203 四 航路と滞船 p.206) 第九章 幕末・維新期の灘酒輸送 p.215 第九章 幕末・維新期の灘酒輸送 一 「一紙帳」と灘酒造地域 p.216 第九章 幕末・維新期の灘酒輸送 二 江戸積・浦賀積樽数 p.219 第九章 幕末・維新期の灘酒輸送 三 輸送廻船 (一 艘数動向 p.222 二 航海日数 p.224 三 難船率 p.225 四 風帆船・蒸気船の登場 p.227) 第九章 幕末・維新期の灘酒輸送 四 酒造家の手船 p.230 第十章 幕末・明治期の赤穂塩輸送と廻船経営 一 赤穂廻船の動向 p.239 第十章 幕末・明治期の赤穂塩輸送と廻船経営 二 個別廻船の経営 p.243 第十章 幕末・明治期の赤穂塩輸送と廻船経営 二 個別廻船の経営 (一 利吉丸の経営 p.244 二 長安丸の経営 p.246 三 盛新丸の経営 p.257 四 彩光丸の経営 p.258 五 天祐丸の経営 p.259 六 元亨丸の経営 p.260 七 有功丸の経営 p.262 八 公正丸の経営 p.263 九 凌雲丸の経営 p.264 十 万全丸の経営 p.265 十一 久徳丸の経営 p.267) 第十章 幕末・明治期の赤穂塩輸送と廻船経営 三 奥藤家の廻船経営と塩取引 p.269 第十一章 近世阿波における廻船経営と手船化 p.279 第十一章 近世阿波における廻船経営と手船化 (一 所有形態 p.280 二 活動状況 p.284 三 収支状況 p.286 四 積荷と手船化 p.291) 第十二章 阿波国撫養における山西家の廻船経営 p.295 第十二章 阿波国撫養における山西家の廻船経営 (一 阿波をとりまく廻船 p.296 二 山西家の廻船活動 p.303 三 徳一丸の経営 p.308 四 幸福丸の経営 p.315) 第十三章 阿波国撫養をめぐる商品流通と廻船 p.324 第十三章 阿波国撫養をめぐる商品流通と廻船 (一 「入船帳」の分析 p.325 二 移入商品 p.332 三 移出商品 p.336 四 廻船経営 p.339) 第十四章 塩飽廻船の水主と備前国南児島 (一 塩飽廻船と廻米 p.348 二 元禄期の瀬戸内海運 p.351 三 味野村の廻船 p.359) 第十五章 讃岐国塩飽廻船の機能 p.369 第十五章 讃岐国塩飽廻船の機能 (一 塩飽廻船の成立と人名制 p.370 二 塩飽諸島と廻船業 p.378 三 廻船業の衰退 p.384) 第十六章 石見国銀山領の城米輸送 (一 大浦湊と城米集荷体制 p.397 二 城米輸送 p.399 三 城米輸送船の航行 p.406 四 運賃と農民の負担 p.410) 第十七章 幕末期における越後国の城米輸送 p.420 第十七章 幕末期における越後国の城米輸送 (一 大坂廻米 p.421 二 西廻り江戸廻米 p.426 三 東廻り江戸廻米 p.428) 第十八章 佐渡国入津船と商品流通 (一 浦川港の客船帳 p.436 二 享保10年「諸廻船入津留帳」 p.440) 結論 (一 廻船の発展類型 p.452 二 廻船と商品流通 p.454 三 廻船の性能 p.456 四 廻船の損益と運賃 p.459 五 廻船の経営形態 p.461 六 廻船と危険分散 p.465 七 廻船の近代化 p.468) あとがき p.471 図一 直島諸島周辺略図 p.75 図二 紀州廻船艘数動向と時期区分 p.109 図三 酒値段と酒運賃との関係 p.121 図四 塩飽諸島略図 p.350 図五 越後国城米積出湊 p.421 表一 蔵米積地および輸送船籍 p.58 表二 蔵米輸送船の動向 p.60 表三 時期別海難件数 p.76 表四 商品別件数一覧 p.78 表五 大坂船籍の他国稼 p.84 表六 船稼形態 p.95 表七 廻船規模別内訳 p.98 表八 船稼・船頭・廻船規模の関係 p.100 表九 比井若一王子神社廻船関係奉納物 p.112 表十 比井廻船積荷一覧 p.118 表十一 米と酒の運賃比較 p.122 表十二 薗家歴代当主一覧 p.131 表十三 天明6年薗家財産引継目録 p.132 表十四 文政9年薗家財産引継目録 p.134 表十五 比井浦歴代庄屋一覧 p.138 表十六 龍神丸新造費用内訳 p.143 表十七 龍神丸の経営状況 p.144 表十八 糸我組蜜柑出荷状況 p.156 表十九 明和7年糸我積合出荷状況 p.160 表二十 有田郡年間蜜柑出荷状況 p.162 表二十一 嘉永4年蜜柑出荷状況 p.164 表二十二 嘉永4年江戸送蜜柑輸送状況 p.166 表二十三 益久丸稼動状況 p.170 表二十四 揚力丸の積荷 p.175 表二十五 鵜殿廻船内訳(天保2年9月) p.185 表二十六 魚崎村江戸積樽数・船数 p.220 表二十七 今津村江戸積樽数・船数 p.221 表二十八 難船艘数・樽数 p.226 表二十九 風帆船・蒸気船の導入 p.228 表三十 文久2年魚崎村酒造家の所有廻船と積荷(1) p.231 表三十一 文久2年魚崎村酒造家の所有廻船と積荷(2) p.232 表三十二 文久2年魚崎村酒造家の所有廻船と積荷(3) p.232 表三十三 慶応2年今津村酒造家の所有廻船と積荷 p.233 表三十四 赤穂塩廻船艘数 p.242 表三十五 利吉丸の活動状況 p.245 表三十六 長安丸の活動状況(1) p.247 表三十七 長安丸の活動状況(2) p.251 表三十八 長安丸の活動状況(3) p.256 表三十九 廻船利益動向と塩価 p.271 表四十 奥藤家の廻船利益動向 p.272 表四十一 天保12年7月山西庄五郎所有廻船 p.283 表四十二 元治2年山西庄五郎手船及び支配船 p.283 表四十三 伊勢丸の利益構成 p.288 表四十四 伊勢丸5か年損益計算 p.290 表四十五 「入船出船通」の内容 p.297 表四十六 積荷と規模との関係 p.299 表四十七 冊子による規模別構成 p.299 表四十八 船籍と規模と積荷の推移 p.300 表四十九 山西庄五郎船の動き p.305 表五十 徳一丸の乗組員と賃金 p.308 表五十一 徳一丸利益構成 p.312 表五十二 幸福丸利益構成 p.317 表五十三 「入船帳」の積荷内容 p.326 表五十四 「入船帳」の積荷と廻船規模の関係 p.328 表五十五 「入船帳」の船籍と廻船規模の関係 p.330 表五十六 「御品仕切帳」における商品額 p.332 表五十七 「諸上納之帳」における米穀移入量 p.334 表五十八 移入米穀の販売先 p.335 表五十九 弘化3年月別塩買入量 p.337 表六十 弘化3年の塩買入先 p.337 表六十一 徳善丸利益構成 p.340 表六十二 他国行船稼一覧 p.352 表六十三 大坂行積荷購入先内訳 p.356 表六十四 塩飽諸島高配分内訳 p.371 表六十五 人名内訳 p.374 表六十六 正徳3年塩飽諸島浦々明細 p.378 表六十七 延宝3年の牛島廻船所有者 p.381 表六十八 宝永2年の牛島廻船所有者 p.382 表六十九 蔵宿別廻船積高 p.400 表七十 大浦湊積出江戸大坂廻米高 p.402 表七十一 江戸大坂廻米船比較 p.404 表七十二 大浦湊入津・出帆・出戻時刻 p.409 表七十三 大浦湊より江戸・大坂廻米運賃高 p.411 表七十四 大浦湊積出江戸大坂廻米諸入用(文政8年) p.412 表七十五 嘉永元年の江戸廻米運賃比較 p.429 表七十六 万延元年越後国海老江湊積建東廻り江戸廻米船 p.430 表七十七 享保~明治16年佐渡浦川港入津の諸国廻船 p.437 表七十八 安永7年以降浦川港山岸屋の客船 p.439 表七十九 船籍と廻船規模 p.442 つづきをとじる |
| ばしょ | |
| ばしょ |
|
| NDCぶんるい | |
| NDCぶんるい | 683.21 |
| けんさくキーワード | |
|---|---|
| けんさくキーワード | 交通文化資料目次情報 |
| さんこうじょうほうげんまたはいんようじょうほうげん | |
| さんこうじょうほうげんまたはいんようじょうほうげん | [タイトルコード]1005010187644 |
| たいしょうねんれい | |
| たいしょうねんれい | 全年齢, 高校生 |
| きょうどじょうほうのげんご | |
| きょうどじょうほうのげんご | jpn |
| メタデータさくせいねんがっぴ | |
| メタデータさくせいねんがっぴ | 1994 |
| メタデータこうかいねんがっぴ | |
| メタデータこうかいねんがっぴ | 2011-02-16 |
| このページのURL | |
|---|---|
| このページのURL | http://digioka.libnet.pref.okayama.jp/detail-jp_c/id/kyo/M2008011918590063591 |