きょうどじょうほうネットワーク > 田原井堰跡 附田原用水路一部、百間の石樋、切抜き
田原井堰跡 附田原用水路一部、百間の石樋、切抜き
カテゴリじょうほう
| きょうどじょうほうネットワーク > 郷土情報ネットワーク > 10 岡山県(行政資料・岡山県のPRビデオなど) > おかやまの文化財 |

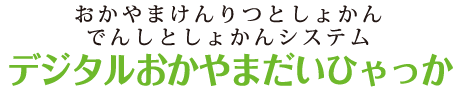
きょうどじょうほうネットワーク > 田原井堰跡 附田原用水路一部、百間の石樋、切抜き
| きょうどじょうほうネットワーク > 郷土情報ネットワーク > 10 岡山県(行政資料・岡山県のPRビデオなど) > おかやまの文化財 |