|
では、続きを説明するよ。
ある日の朝、放射冷却が起こったとすれば、地上からの高さによる気温の変化はどんなふうになっているのだろう?
空気の層の一番下が冷たい地面と接触しているのだから、空気の層の一番下が一番温度(気温)が低くて、そこから離れるほど、つまり高くなるほど気温は上がっているはずだね。 |
|
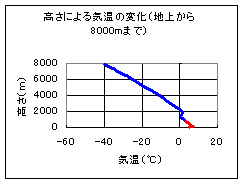 |
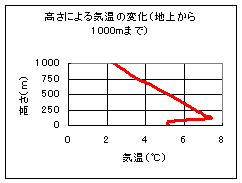 |
第2図 米子での当時の気温の高度変化
(地上から8km高度まで) |
第3図 米子での当時の気温の高度変化
(地上から1km高度まで) |
|
|
上の第2図は、蒜山高原から一番近いところにあって上層大気の様子を測定している鳥取県米子〔よなご〕市でのグラフ参考文献3)なんだ。このグラフの数値が測定されたのは、写真を撮った日の午前9時なんだ。だから、写真の時刻とほとんど違わないときに測定されているんだよ。
(飛行機は米子付近の上空を飛んでいるので、ひょっとしたら測定している気球と飛行機とがすれ違っていたかも・・・・。)
このグラフの見方がわかるかな。縦軸は、地上からの高さをメートル単位で書いてあり、横軸は気温を℃の単位で書いてある。青い太い線(下の方に赤い部分があるがいまは気にしないでね)は、それぞれの高さで測定された気温をつないだ線で、これを見ると高さが変わると気温がどう変わっているかがわかるんだ。たとえば、このときの地面近くの気温は6〜7℃くらい。地上8kmの高さでは、−40℃くらい、ということがわかるね。
おっと、あっさり地面近くで6〜7℃、上の方で−40℃と言ったけど、さっき、「空気の層の一番下が一番温度(気温)が低くて、そこから離れるほど、つまり高さが高くなるほど気温は高くなっているはずだ」と言ったことと違ってるね。
グラフからだと、放射冷却は起こっていないような感じだよ・・・。 |
|
実は、グラフというものは気をつけないとだまされることがあるんだ。
第3図は、、第2図の曲線の赤い部分だけを拡大して書いたものだよ。第3図によると、地上から150mくらいまでは高度が高いほど気温は上がっていて、地上より150m高度のほうが、2℃あまりも高温なことがわかるよ。これでナゾが解けたんじゃないかな。 |
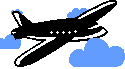 |
※ちょっと一言
グラフは自分が言いたいことを人にわかってもらえるように書くのがポイントなんだ。そういう意味で、いまの場合は図2よりも図3の方がより良いグラフだね。 |
|
|