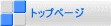 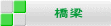 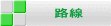 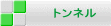 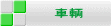 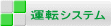 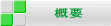
|
トンネル
|

NATM工法による吉備真備トンネル・・・奥に別のトンネルが見える |
井原線は旧山陽道とほぼ並行した平坦な地を行くのでトンネルの数も7つと少なく、最長の妹山トンネルでも960mと、そう
長くない。トンネルの総延長は3.2kmであり全路線延長45km中8%である。
7つのトンネルの内、堀越トンネル・押延トンネル・井原トンネルの3つは、旧国鉄時代に施工され、
工事の方法は低設導坑先進上部半断面工法によって昭和44年にはほぼ完成していた。
その後の第3セクターとして施工された妹山トンネル・吉備真備公園トンネル・谷藤トンネルおよび茶臼山トンネルの4つは、
新しい技術の進歩を取り入れて大部分が全断面掘削によるNATM工法で施行され、平成8年にほぼ完成した。
|
|
| 名前・長さ |
完成 |
方式 |
画像 |
画像 |
参考 |
妹山
940m |
H8.11 |
全断面掘削
NATM工法 |
 |
 |
地質:流紋岩
断面:馬蹄形 |
吉備真備
190m |
H8.3 |
全断面掘削
NATM工法 |
 |
 |
地質:流紋岩
断面:馬蹄形 |
谷藤
650m |
H8.11 |
全断面掘削
NATM工法 |
 |
 |
地質:流紋岩・花崗岩
断面:馬蹄形 |
茶臼山
426m |
H3.6 |
全断面掘削
NATM工法 |
 |
 |
地質:風化花崗岩
断面:馬蹄形 |
堀越
248m |
S44.5 |
低設導坑先進上部
半断面矢板工法 |
 |
 |
地質:粗砂
断面:馬蹄形 |
押延
162m |
S43.12 |
低設導坑先進上部
半断面矢板工法 |
 |
 |
地質:粗砂
断面:馬蹄形 |
井原
624m |
S42.10 |
低設導坑先進上部
半断面矢板工法 |
 |
 |
地質:花崗岩・粗砂の互層
断面:馬蹄形 |
|
トンネル掘削方法としてのNATM技術
トンネル工事は工程の順に、①掘る作業(削岩または掘削と呼ぶ) ②掘ってできた空間を支える作業(支保<しほ>と呼ぶ) ③掘った土砂(ずり)を坑外に運び出す作業(ずり出し) の繰り返しで掘り進められる。それぞれの作業に特有の技術があり、NATM工法は②の支保作業のやり方の一つである。
NATMはNewAustrianTunnelingMethodの略で、1950年ごろオーストリアで考え出された工法で、1960年代にはヨーロッパで採用されはじめ、日本では1970年代になって導入された。
従来の工法は、掘った部分が崩れないように木製の矢板をを充て、木製の柱などでツッパリをしていた。地山の崩れる力の強いほど、多くの厚く太い木材が必要である。1960年ごろから鋼製の支保柱が用いられるようになったが、掘った部分に矢板を当てることは続いた。
鋼製支保工と矢板の組み合わせによる工法を矢板工法と呼ぶ。
それに対してNATM工法では、掘ったあとに矢板を当てる代わりに、コンクリート吹き付けを行いそれを固定する為にロックボルトを用いて地山との間を固定して鋼製支保工で固定する。いずれもそのあとに現在では内面を覆うコンクリートを施工する。矢板と地山の間に隙間ができず密着しているのが特徴である。 |
トンネル掘削の方法
掘る作業は(1)発破掘削方式(2)機械掘削方式(3)人力掘削方式に分類され、その場合断面の掘り方により(1)全断面掘削法(2)部分断面掘削法に分かれる。部分断面掘削法の中にはベンチカット工法と導坑先進工法が、そしてさらに導坑先進工法の中にも頂坑導坑、低設導坑側壁導坑、中央導坑と導坑の位置によって細分化される。
支保作業には(1)矢板工法(2)NATM工法がある。
ずり出し作業には(1)レール式(レールを敷いてトロッコなどで運び出す)(2)タイヤ式(ダンプトラックなどで)(3)ベルトコンベア方式(4)ウィンチなどの方法がある。
実際の工事ではこれらを組み合わせて施工するので、そのトンネルがどう作られたかを示すには、これらの分類に従って、工事工程順に
使われた方法を順次併記して表現する。
表中に記載した方式とはこの表現法による。すなわち井原線のトンネル7つの内、国鉄時代に先行して掘られた3つのトンネルは、いずれも低設導坑先進上部半断面で掘られ、支保は矢板工法によっていた。それに対して第3セクター発足後に再開された4つのトンネルは全断面掘削で掘られ、支保はNATM工法によっていることが分かる。施工時期によって新技術が活用された。 |
トンネル付近の風景
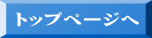
|

